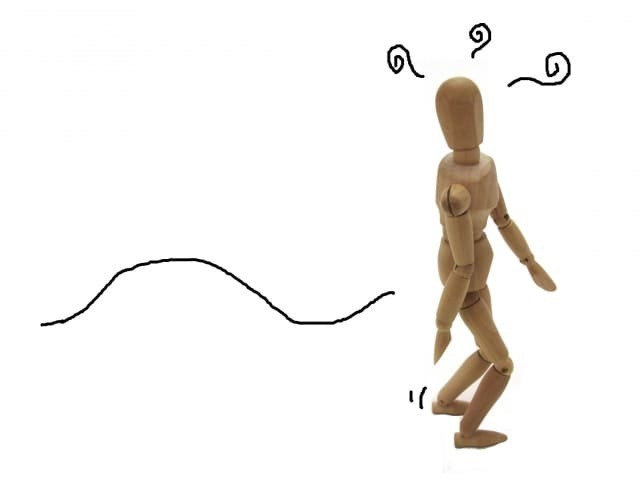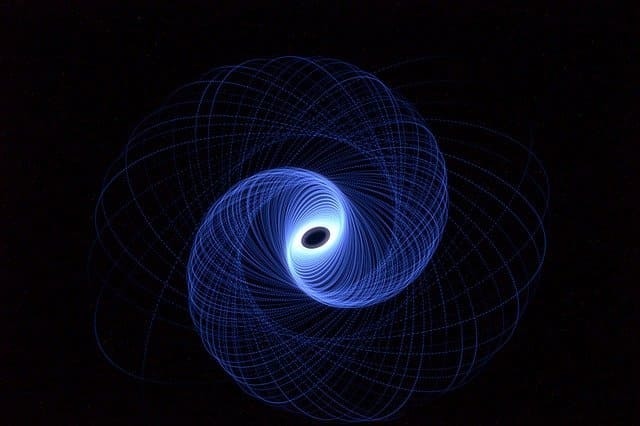低髄液圧性頭痛の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2023年 3月 3日
更新日:2023年 4月 1日
本日は低髄液圧性頭痛について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- 低髄液圧性頭痛とは
- 低髄液圧性頭痛の原因
- 低髄液圧性頭痛の症状
- 低髄液圧性頭痛の改善方法
- 低髄液圧性頭痛のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

低髄液圧性頭痛の原因は、髄液が失われることです。ほとんどの場合は、腰椎穿刺の後に起こります。
腰椎穿刺を受けた人の最大3分の1の人に低髄液圧性頭痛が起こると言われています。起こるまでの時間は、処置の数時間から1~2日後です。
腰椎穿刺は、腰にある2つの脊椎の間に針を入れて脊柱管から髄液のサンプルを採取する処置のことです。腰椎穿刺を行った後、針を刺した場所にできる小さな穴から、髄液が漏れ続けてしまうことがあるのです。
髄液の漏れに対して新しい髄液の産生が少ない場合は、脳の周りの液体の量が減ってしまいます。そのため、低髄液圧性頭痛が起こるのです。
主な原因
・外傷による髄液漏れ
外部からの強い衝撃によって脊椎や硬膜が損傷し、髄液が漏れることがあります。
・処置による髄液漏れ
髄液を調べたり脊髄麻酔後に発生することがあります。
・脊髄硬膜の自然破裂
明らかな原因がないにもかかわらず、脊髄の硬膜に小さな穴や裂け目ができることがあります。
・髄液の過剰排出
髄液が過剰に排出されることも低髄液圧の原因となります。
① 髄液吸収の異常
髄液が正常よりも速く吸収されてしまい、圧力が低下する髄液吸収の異常やシャントによる過剰排液が原因になります。
・ 髄液の生産不足
髄液の産生量が減少することで髄液圧が低下します。
・脱水症状や血液量減少
全身の水分不足や血液量の低下により髄液の生産が減少します。
・先天性や構造的な問題
先天的な体の構造や異常が原因で髄液漏れや圧低下を引き起こすことがあります。
・結合組織疾患
マルファン症候群やエーラス・ダンロス症候群などの結合組織異常により硬膜が脆くなり、漏れやすくなることがあります。
・クモ膜嚢胞
脊髄や脳に嚢胞が形成され、これが破裂して髄液漏れを引き起こすことがあります。
・激しい身体活動
重いものを持つ、過度のストレッチ、激しい咳やくしゃみなどが硬膜に圧力をかけ、髄液漏れを誘発する場合があります。
・長時間の体位変化
長時間の前屈姿勢や頭を低くする姿勢が原因になることもあります。
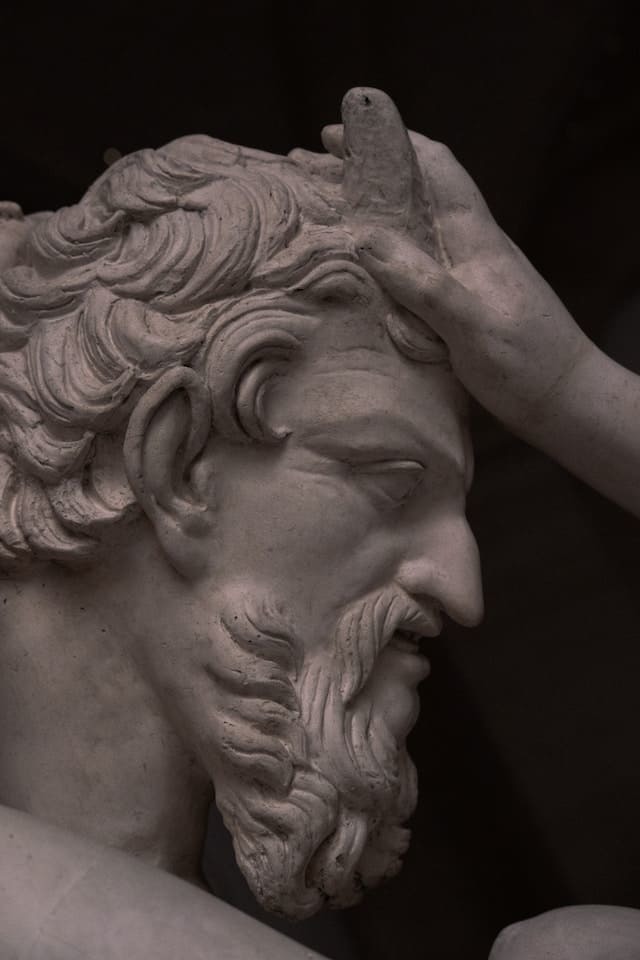
低髄液圧性頭痛の症状は、強い痛みのある頭痛です。頭痛は、座っているときにも立っているときにも起こりますが、横になると軽くなることもあります。
頸部の硬直や首の痛み、吐き気が起こることも多く、場合によっては嘔吐がみられることもあります。
主な症状
・頭痛
立ち上がったり座ったりすると悪化し、横になると改善します。前頭部や後頭部に痛みを感じやすく激しい痛みではなく、鈍い痛みが持続します。
・神経症状
頭が重く、圧迫されるような感覚、めまい、立ちくらみやふらつき感、耳鳴り、耳の閉塞感、視覚異常や感覚異常が起こります。
・全身症状
全身のだるさ、疲労感が続き、吐き気や嘔吐、首や肩のこりを感じます。
・精神的症状
注意力が散漫になり、気分の落ち込み、抑うつ感、不安感を伴うことがあります。

低髄液圧性頭痛の改善方法は、安静にすることと、十分に水分を摂取することです。痛みに対しては痛み止めを使います。
横になった時に痛みが軽くなることもあるため、痛みを軽くするためにはできるだけ横になっておくことが良いでしょう。
安静にしていてもなかなか改善しない場合は、自家血を硬膜外に入れて血液が固まることで硬膜の裂け目を塞ぐという方法を行うこともあります。
主な改善方法
・安静にする
横になることで髄液圧が一時的に回復し、脳の下垂を軽減する。
・水分摂取の増加
体内の水分を補給することで髄液の産生を促進する。
・カフェインの摂取
カフェインは血管を収縮させる作用があり、髄液圧を一時的に改善する場合がある。
・鎮痛薬の使用
一時的に痛みを和らげます。
・血液パッチ療法
硬膜の穴をふさぎ、髄液圧を正常に戻す。
・生理食塩水や補液療法
脱水状態や髄液の産生をサポートする。
・外科手術
髄液の漏出を根本的に解決する。
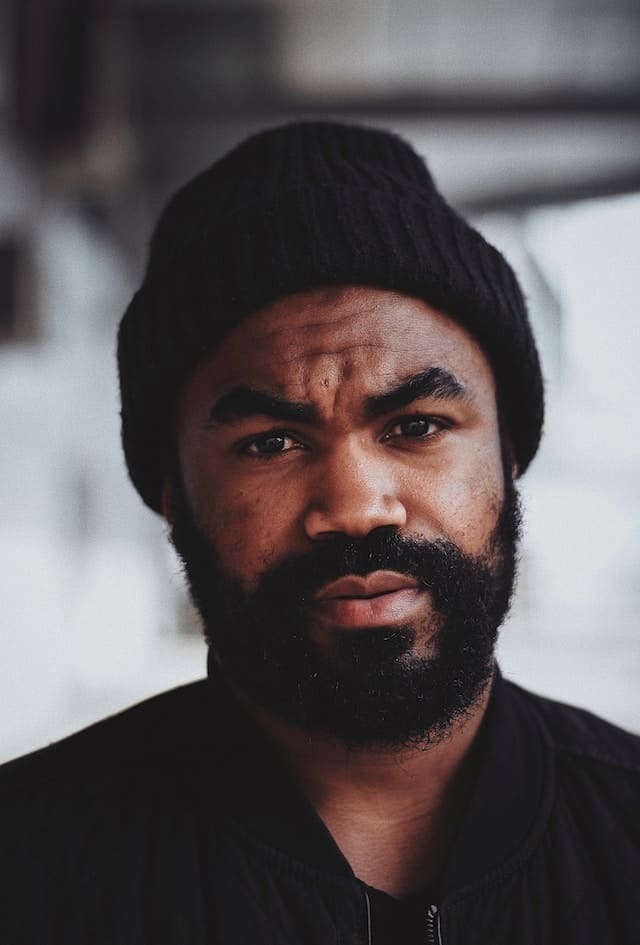
低髄液圧性頭痛であるという判断は、症状と状況によって行われます。腰椎穿刺を受けた後に、低髄液圧性頭痛のような症状が現れた時には、ほとんどの場合調べなくても低髄液圧性頭痛であるということが明らかになります。
腰椎穿刺を受けたことがなく低髄液圧性頭痛のような症状が現れた場合には、MRIなどで脳の画像を見ることもあります。