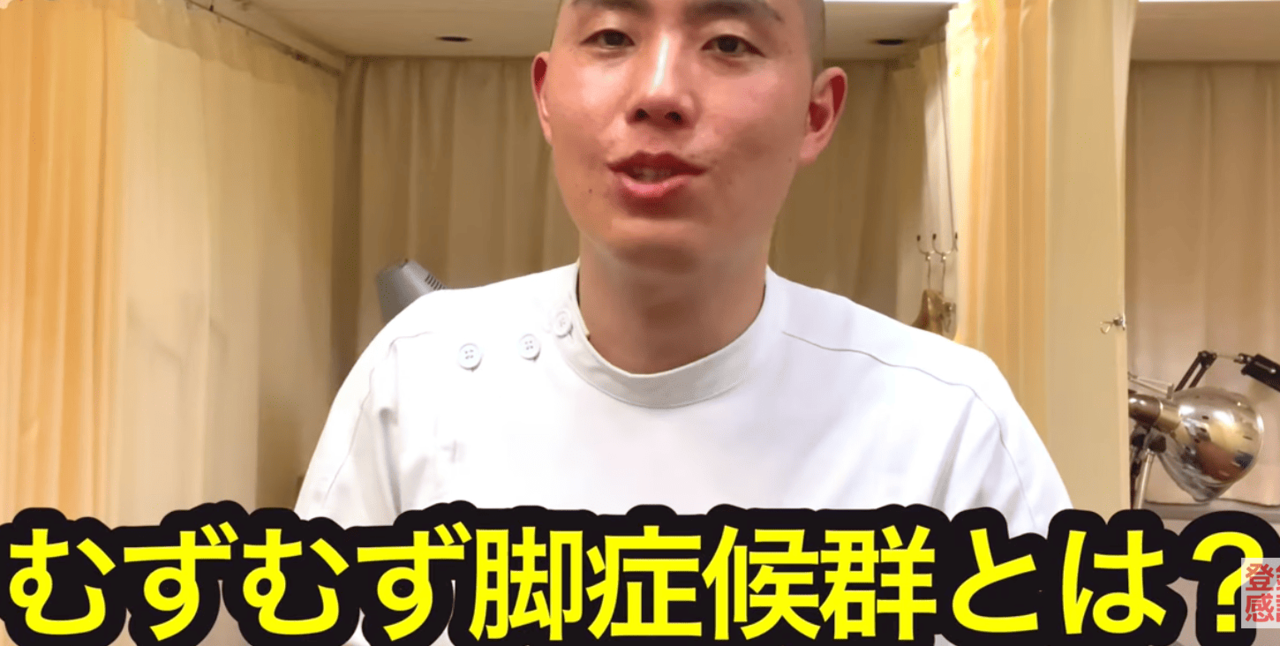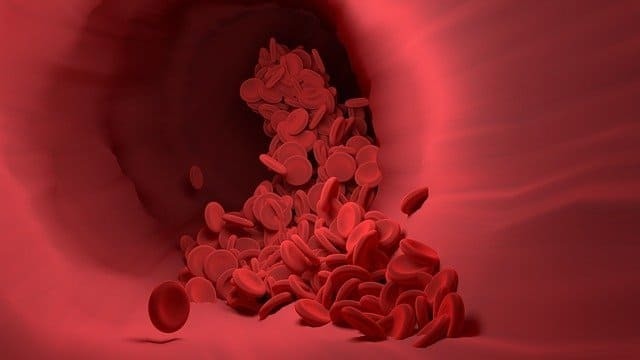むずむず脚症候群の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2019年 12月23日
更新日:2025年 1月15日
本日はむずむず脚症候群について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- むずむず脚症候群とは
- むずむず脚症候群の症状
- むずむず脚症候群の改善方法
- むずむず脚症候群のセルフケア
- むずむず脚症候群のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。
むずむず脚症候群は、身体の末端の不快感や痛みから特徴が付けられた慢性的な病気です。
年齢を重ねるとムズムズして寝れない人はたくさんいます。むずむず脚症候群は当院でも多い病気です。レストレスレッグスシンドロームともいわれ、主に夜間に下肢に不快感やムズムズを感じることが特徴的な神経学的障害です。
症状は休息中に現れ、動かすことで一時的に緩和します。原因は明確には解明されていませんが、遺伝的要素、鉄分不足、脳内のドーパミン濃度の不足、腎臓病、妊娠、薬の副作用などが関与しているといわれています。
主な症状は下肢のムズムズ感や不快感です。症状は夜間に悪化する傾向にあり、休息中に症状が現れます。動かすことで一時的に症状が緩和されます。
改善方法は薬、鉄分補充、生活習慣の改善です。薬はドーパミン受容体に対する薬やコンパル酸、ベンゾジアゼピンなどの薬が処方されやすいです。

むずむず脚症候群という病気は一般的にあまり知名度がなく、知られていません。高齢者には、脚の皮膚がかゆくなる症状の起きる皮膚掻痒症という皮膚科の病気があります。
しかし、皮膚掻痒症で起こるかゆみは脚の表面の皮膚のかゆみです。このかゆみは、脚をかいたりすることによっておさまります。
むずむず脚症候群の場合、そのむずむずという病名にもあるように、脚の深い部分にむずむず、ジリジリなどの不快感が症状として現れます。脚をかいたとしても不快な症状がおさまることはありません。
このかゆみは夜眠る時に現れます。そのため、むずむず脚症候群で不眠障害に苦しんでいる人も多いです。このかゆみ症状は、足を動かすと一時的に無くなります。しかし、眠ろうとした時に再びむずむず、ジリジリの不快感が出てきてしまいます。眠りについた後も、むずむず脚症候群のもうひとつの症状である周期性四肢運動が現れます。
周期性四肢運動の症状は、寝ている間に20~30秒の間隔で足首をカクッカクッと蹴るようなけいれんです。この症状が起きることによって睡眠中に目覚めてしまい、眠れなくなってしまいます。
むずむず脚症候群で悩んでいる人の50~80%がこの周期性四肢運動をかゆみと合わせて発症しているといわれています。
主な症状
不快な感覚:しばしばこの感覚を「むずむず感」、「くすぐったさ」、「痛み」、「痺れ」、「引きつり」などと表現します。この感覚は休息時に最も悪化し、特に座ったり横になったりしたときに感じられます。
動かす衝動: 不快な感覚は、脚や腕を動かす強い衝動を引き起こします。動きは、患者にとっては一時的に症状を軽減する役割を果たします。
夜間の症状の増加: 症状は、夕方や夜間に特に悪化します。これは就寝前やベッドでの休息時に特に顕著であり、結果として睡眠の質が大幅に低下します。
不眠: しばしば不眠症を引き起こし、これは疲労、集中力の欠如、日中の眠気、抑うつなど、さまざまな他の健康問題を引き起こす可能性があります。
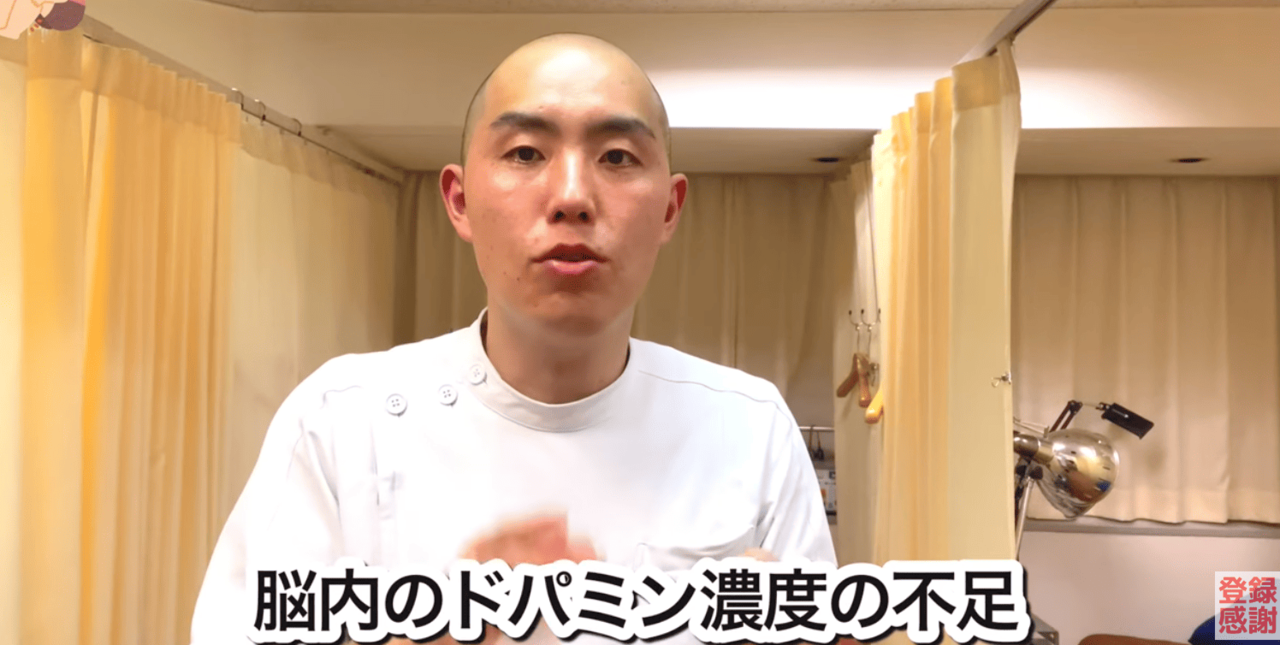
むずむず脚症候群は白人に多く約5~15%で、アジア人には約2~5%前後といわれています。ただし、60歳以上になると約5%以上いるといわれており高齢になるほど多くなります。当院でも非常に来院の多い病気です。
むずむず脚症候群の男女比は1:2で、女性が男性の2倍です。むずむず脚症候群になるメカニズムはまだ不明です。
しかし、最近、脳内で神経細胞の間で信号のやりとりをするのに重要な神経伝達物質のドーパミンの作動性神経細胞の機能低下と関係していることがわかりました。
ドーパミンは、人間が手や足を動かしたり、いろいろな運動をする際、機械の潤滑油のように円滑に進むための働きをします。
主な原因
ドーパミン異常: ドーパミンは、脳内で神経細胞間の通信を助ける神経伝達物質です。ドーパミンのバランスが崩れると、脳が体の動きを正常に制御できなくなり、症状を引き起こす可能性があります。
遺伝的要因: 家族間で発生する傾向があり、特に症状が若年に現れる場合は、遺伝的要因が強く関与していると考えられています。
鉄欠乏: 鉄の不足は、ドーパミンの生産に影響を与え、症状を引き起こす可能性があります。
慢性的な病気: 一部の慢性的な病気、例えば腎臓病、糖尿病、末梢神経症、関節リウマチなどはリスクを高める可能性があります。
妊娠: 妊娠は一時的に症状を引き起こす可能性があり、特に妊娠後期にそのリスクが高まります。しかし、出産後に症状は通常消えます。
薬物: 特定の薬物は症状を誘発または悪化させる可能性があります。これには抗精神病薬、抗うつ薬、一部の抗ヒスタミン薬、カフェインなどが含まれます。
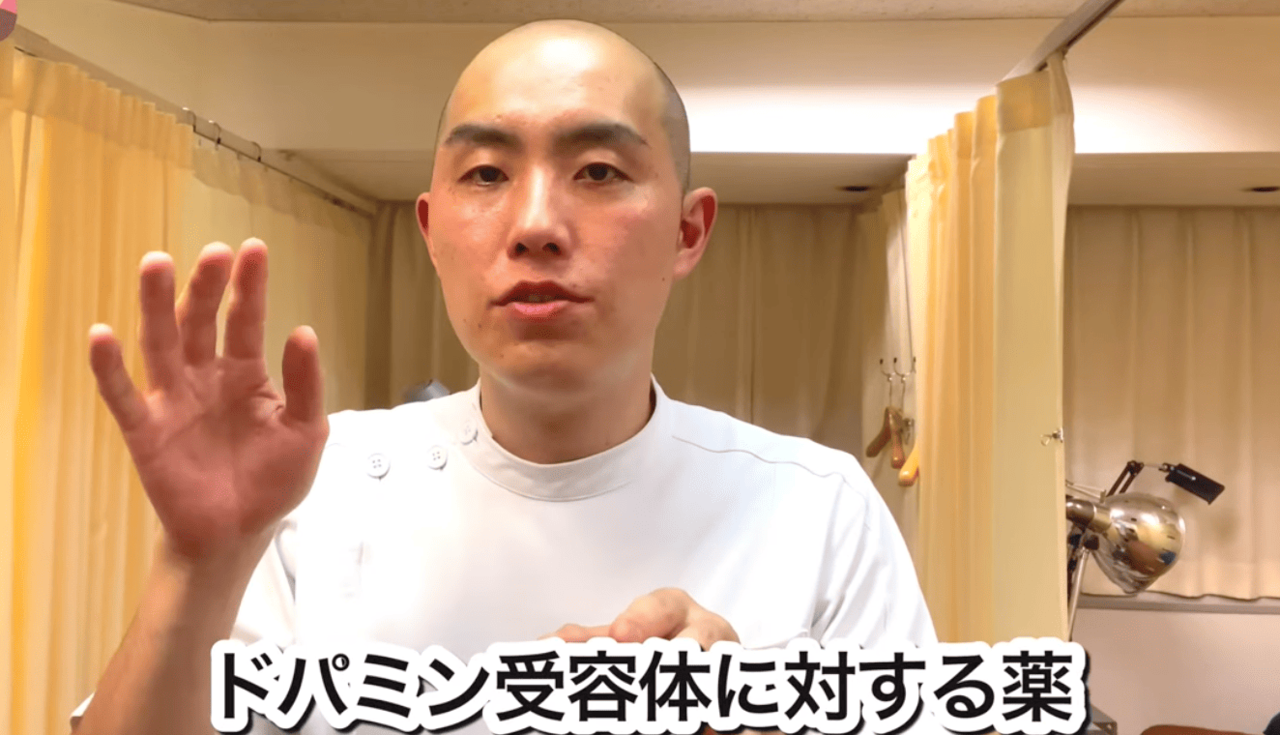
むずむず脚症候群の改善法は、生活習慣の改善とマッサージ、薬を使った方法が中心です。
生活習慣の改善で重要なことは、症状を悪化させる要因となるカフェインを避けることです。夕方以降はコーヒーや紅茶、日本茶は飲まないようにしてください。
深酒はしないことも大事です。筋肉の疲れが強いときは、十分なマッサージを行うかマッサージを受けてください。軽症であれば、これだけでも症状は改善します。
しかし、重症の場合は生活習慣の改善に加えて薬を使った改善方法を行います。
主な改善方法
・自己管理とライフスタイルの変更
生活習慣の改善: 適度な運動、バランスの取れた食事、良い睡眠習慣の維持など、健康的な生活習慣を実践することが症状を管理するのに役立ちます。
カフェイン、アルコール、タバコを避ける: これらの物質は症状を悪化させる可能性があります。
ストレッチと運動: 定期的な適度な運動は症状を軽減する可能性があります。しかし、過度な運動は症状を悪化させる可能性もあります。
・薬
ドーパミン作動薬: ドーパミン作動薬は最も一般的に処方される薬で、中枢神経系のドーパミンレベルを増やすことで症状を軽減します。
α2δリガンド: ガバペンチン(ノイロチン)やプレガバリン(リリカ)などは、神経系における異常な興奮を抑制し、症状を軽減する可能性があります。
ベンゾジアゼピン: クロナゼパム(リボトリル)やテマゼパム(レスタリル)などのベンゾジアゼピンは、症状が強い場合や、他の方法が効果的でない場合に用いられます。
鉄補給: RLSは時折、鉄の不足と関連しています。鉄補給は、特に血液を調べた時に鉄の低下が確認された場合に有用であり得ます。
・非薬物
CBT: CBTは、病気に対する理解を深め、不適切な行動や思考パターンを変えることで、症状を軽減するのに役立つことがあります。
リラクゼーション: ヨガ、マインドフルネス瞑想、深呼吸、進行性筋肉リラクゼーションなどのリラクゼーション技術は、ストレスを減らし、睡眠を改善し、症状を軽減するのに役立つことがあります。
温熱/冷却: 温湿布や冷湿布を使用することで、一時的な症状の緩和が得られる場合があります。
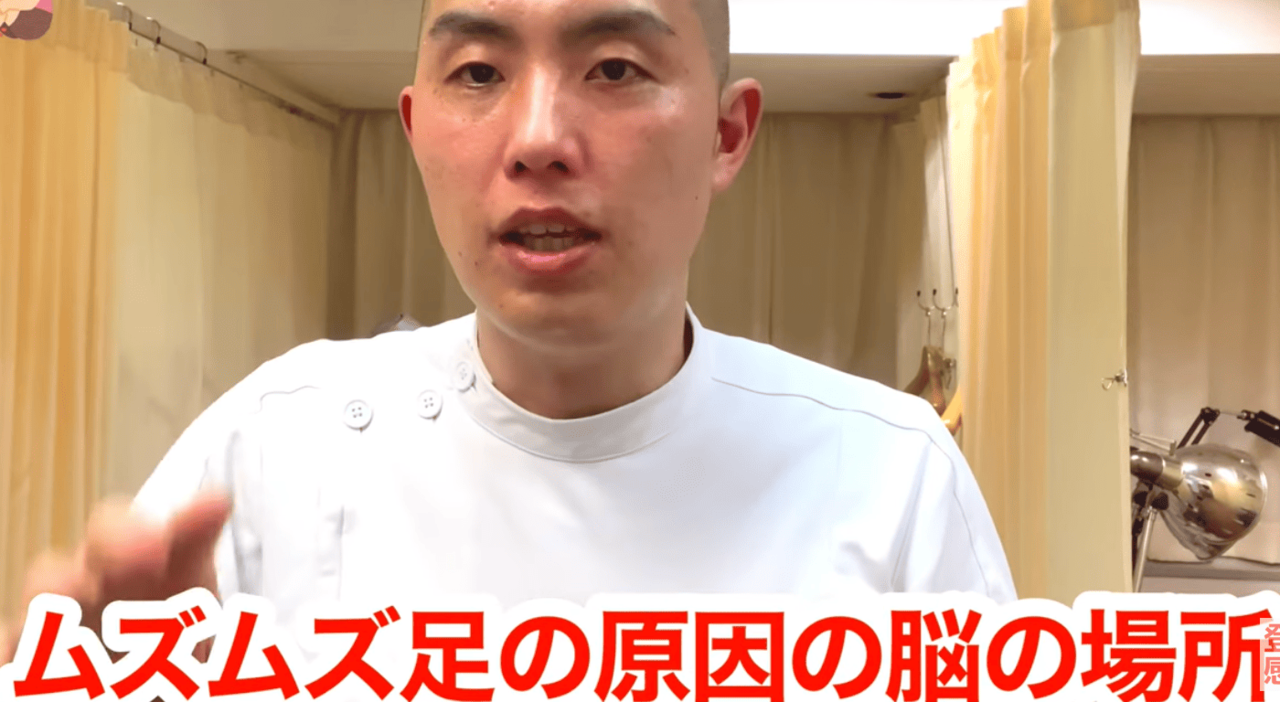
むずむず脚症候群の回復の機序は、脳内のドーパミン濃度を適切な状態に維持して神経伝達のバランスを整えることで症状が軽減されることです。
ドーパミンは脳内のいくつかの場所で生成され、分泌されます。
主な分泌場所は2つです。
①黒質
中脳に位置し運動制御に関与します。
ここで生成されたドーパミンは大脳基底核に送られて運動機能の調節に役立ちます。
②腹側被蓋野
中脳に位置して情報集計や快楽、モチベーションに関与します。ここで生成されたドーパミンは前頭前皮質や側坐核に送られ、報酬系や快楽、モチベーションの維持に関与します。
むずむず脚症候群の症状は主に黒質で生成されるドーパミン不足や神経伝達物質のバランスの乱れによって引き起こされると報告されています。そのため、ドーパミン濃度を適切に維持し神経伝達のバランスを整えることが症状の改善につながります。
むずむず脚症候群とドーパミンの関連性についてはいくつかの研究が存在します。2011年に行われたエアール・マッケイによる論文ではドーパミンに対する薬の使用によってむずむず脚症候群の症状が緩和されることが報告されています。
また、この研究ではドーパミン濃度の低下やドーパミン状態の機能不全が症状に関与していることも報告されています。
むずむず脚症候群は日常生活に大きな影響に与える症状ですが、適切な改善方法やライフスタイルの改善を行うことで症状の緩和が可能です。きちんと症状を理解して適切なサポートを受けることが重要なのです。
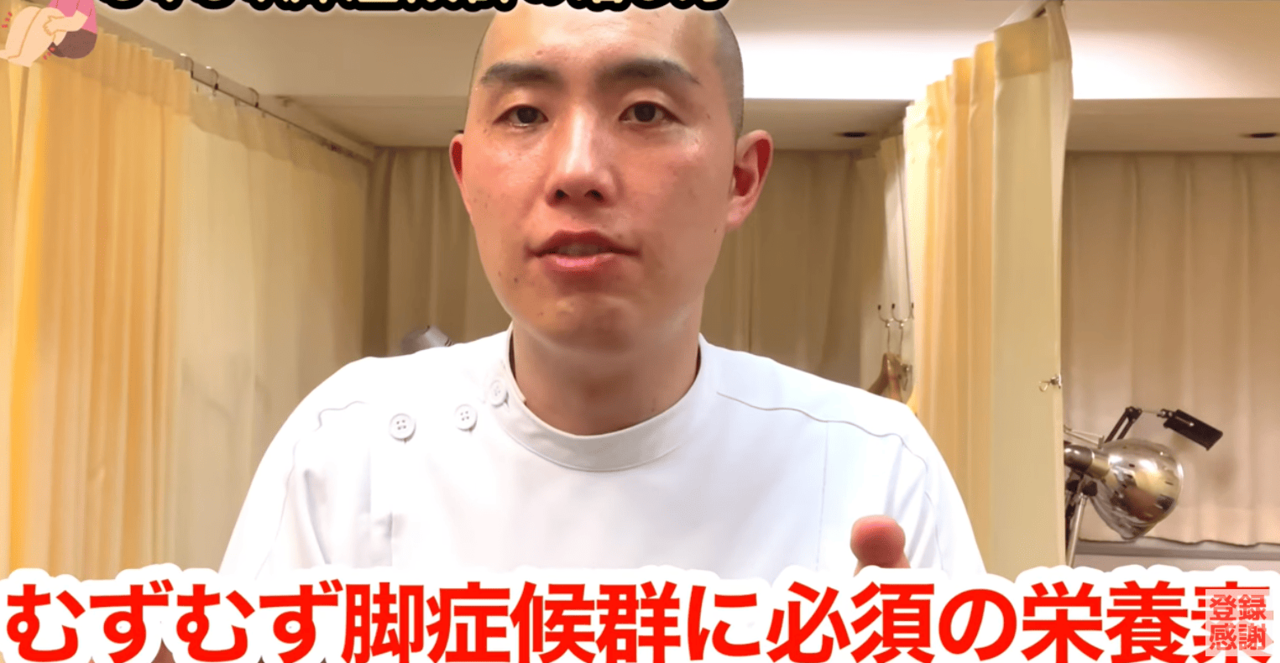
むずむず脚症候群の症状を緩和するために摂取するべき栄養素は、鉄分、ビタミンB、マグネシウムです。これらの栄養素を摂取することで症状が緩和されます。
鉄は酸素輸送に関与します。鉄分不足はドーパミン生成にも影響を与えるためむずむず脚症候群には必須の栄養素です。
ビタミンB群は神経機能の正常化に役立ちます。特にビタミンB6とB12が神経伝達物質の生成に関与します。
マグネシウムは筋肉や神経のリラックス効果があり、神経伝達のバランスを整えることが期待できます。
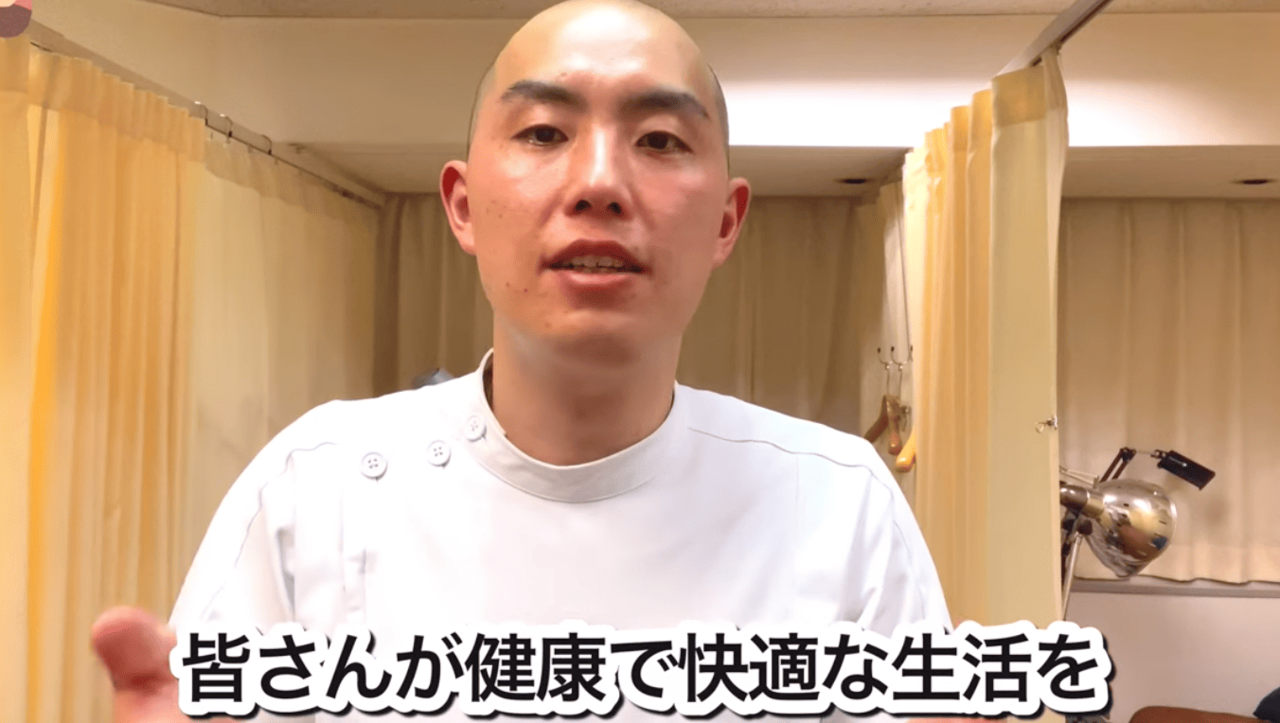
むずむず脚症候群の改善には、規則正しい生活を意識して心がけること、ウォーキングなどの軽い運動をすることが必要です。
さらに、夜寝る前にストレッチやマッサージなどをすることで筋肉をほぐすことも改善に効果を発揮します。自分で生活習慣を見直しても改善に取り組んでもあまり症状が改善しない場合、薬を服用して改善を試みることになります。
現在、日本ではむずむず脚症候群の症状を和らげる薬はいくつかあります。生活習慣の改善や軽い運動、ストレッチやマッサージなどで効果が見られない場合でも、これらの薬の服用によってむずむず脚症候群の症状の改善は十分に期待できます。
むずむず脚症候群は日常生活に大きな影響を与える症状ですが、きちんと理解して対処することで症状を和らげることが可能な病気です。