夜泣きの鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2019年 12月23日
更新日:2021年 5月 15日
本日は夜泣きについて解説させていただきます。
☆本記事の内容
- 夜泣きとは
- 夜泣きの原因と症状
- 泣き声の仕組み
- 夜泣きの改善方法
- 夜泣きのまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。
夜泣きのについて多くの本では、「生後半年頃から1歳半ぐらいの赤ちゃんにみられる、夜間の理由のわからない泣き」とされています。
夜泣きが始まる時期や夜泣きが続く期間、夜泣きする時間帯、夜泣きの程度は子供によって様々です。多くの場合は生後3ヶ月から1年半前後に起きやすいといわれています。中には、2歳を過ぎても夜泣きしてしまう子供もいます。反対に全く夜泣きがない子供もいます。
夜泣きが出るのは2回出る場合もあります。1回目は生後半年ごろに夜泣きが起き、2回目は1歳半ごろに出る、などのことがあるのです。
昼間は非常に元気よく遊んでおり、寝る前までは機嫌がよかったにもかかわらず、夜中になって急に泣きだし、泣き止まないという状態が生後半年頃から1歳半ぐらいの乳幼児には多くあります。
抱っこをしたりオムツを換えたり何か対策をすることで泣くのをやめて寝ることもありますが、ほぼ一晩中泣き続けるということもあります。

夜泣きの原因はまだ明らかになっていません。しかし、知能の発達や睡眠のバランス、日中に感じる色々な刺激が関係していると言われています。
夜泣きは、かまい過ぎや言葉のかけ過ぎ、昼間の人ごみ、あやし過ぎ、など色々なことで神経が高ぶったり、刺激になったりし、寝ぼけた状態で泣いてしまうことなのです。
さらに、ストレスが溜まることも夜泣きの原因だと言われています。
乳幼児は、泣くことが仕事です。大声をあげて泣くことで腹筋や脳の運動をしているのです。
泣くことは親や周りの世話をしてくれる人たちに対しての合図でもあります。お腹が空いた時ややオムツが濡れた時、気温が高くて暑い時や、気温が低くて寒い時、具合が悪い時などに泣くことで伝えようとするのです。
主な原因
・生理的要因
① 睡眠サイクルの未成熟
新生児や乳児は成長途中であり、睡眠サイクルのリズムが未発達です。レム睡眠中は脳が活発に働いており、刺激に敏感になるため、ちょっとした変化で目が覚めやすくなります。
② 成長ホルモンの分泌
夜間に分泌される成長ホルモンの影響で脳や身体が急速に発達します。成長過程で神経系が活発になり、夜間に脳が刺激を受けることで覚醒しやすくなります。
③ 消化器の未成熟
乳児の消化器系は未成熟で、ガスが溜まりやすく腹部不快感を感じることがあります。そのため腹痛やガスによる不快感が原因で泣き出すこともあります。
④ 歯の生え始め
生後6か月頃から歯が生えてきます。歯茎の痛みやかゆみが夜間に強くなり、眠りを妨げることもあります。
・環境的要因
① 室温や湿度の変化
部屋の温度や湿度が適切でないと、不快感から目を覚ましやすくなります。暑すぎる、寒すぎる、乾燥しているなど、快適な睡眠環境が保たれていない場合、夜泣きが増えます。
② 照明や音の刺激
夜間の照明や外部からの音が刺激になります。環境の変化に敏感な乳幼児は、わずかな音や光でも目を覚ましやすいです。
・心理的要因
① 不安感・分離不安
乳幼児期には親から離れることへの不安が強くなる時期があります。睡眠中に目が覚め、親がいないことに気づくと不安になって泣いてしまいます。
② 昼間の刺激過多
昼間に多くの刺激を受けた場合、脳が興奮状態のまま夜を迎えることがあります。すると、昼間の刺激が処理しきれず夜間に泣いてしまうことにつながります。
③ 生活リズムの乱れ
就寝時間や起床時間が毎日一定でない、昼寝の時間が長すぎるなどの要因で睡眠リズムが乱れることで夜間の覚醒が増えます。
・病気・体調不良による要因
① 風邪や鼻づまり
呼吸がしづらい状態になると、夜間に目を覚ましやすくなります。風邪や鼻づまりによる呼吸困難が不快感となり、泣くことで助けを求めます。
② 耳の痛み
中耳炎などで耳が痛むと、特に横になったときに痛みが増し、夜泣きにつながります。
③ 皮膚のかゆみ
皮膚の炎症や乾燥によるかゆみによる不快感が睡眠を妨げます。
・遺伝的要因
一部の研究では、夜泣きの頻度やパターンは遺伝的要素も関与しているとされています。親が夜泣きが多かった場合、子どもも夜泣きをしやすい傾向があります。
・その他の要因
① 新生児反射の影響
新生児特有のモロー反射や驚愕反射により乳児が自ら目を覚ましてしまうことがあります。
② 母乳やミルクの問題
母乳やミルクの量が足りない、逆に飲み過ぎて消化不良を起こしているなど空腹感や腹部の不快感で目を覚ますことがあります。

夜泣きは6ヶ月以降の子供によく見られます。一般的には、夜泣きのピークは7~9ヶ月で、多くは2歳までに終わると言われています。
乳幼児の泣き声は大人にとってうるさいと感じることがあります。乳幼児の泣き声はわざわざうるさく聞こえるようにできているとも言われています。
もし、乳幼児の泣き声が心地よい声の場合、親が注意を向けず危険から守ることができない可能性があります。うるさい、泣き止ませたいと思うために親は色々な手段を使い世話をします。
親が子供の泣き声をうるさいと感じることは、進化の過程できた、生きるための仕組みなのです。
子供が泣いた時、親は色々と考え精神的にも肉体的にも疲れることがあります。しかし、原因不明で泣くことも多いです。生きていくための仕組みであると考えることで思い詰めずに対応することができるかもしれません。
注意が必要な夜泣きの特徴
・病気や体調不良が原因の夜泣き
① 発熱や体調不良を伴う夜泣き
夜泣きとともに発熱、咳、鼻づまり、下痢、嘔吐などの症状がある場合、風邪、中耳炎、胃腸炎、尿路感染症などの可能性があります。
② 耳を触る、頭を押さえるなどの仕草を伴う夜泣き
夜泣き中に耳をしきりに触ったり、頭を押さえたりする場合、中耳炎や頭痛の可能性があります。
③ 激しい腹痛を伴う夜泣き
泣き方が激しく、お腹を押さえたり、足を引き寄せるような動きをする場合、腸重積症、ガスによる腹痛、便秘の可能性があります。
・環境によるストレスが原因の夜泣き
① 引っ越しや保育園の開始など生活環境の変化後の夜泣き
昼間の機嫌も悪く、不安定な状態が続く場合は環境の変化によるストレスや不安が原因かもしれません。
・心理的要因による夜泣き
① 悪夢による夜泣き
泣きながら目を覚まし、怖がって親を求める場合、昼間の刺激が強すぎたり、不安を感じる出来事があったなどで悪夢を見ていることがあります。
② 夜驚症
突然泣き叫び、目を見開いているが意識がなく、翌朝は記憶がない場合、ノンレム睡眠中に脳が部分的に覚醒することで起こる夜驚症の可能性があります。
・その他の注意すべき夜泣き
① 泣き方がいつもと違う夜泣き
これまでとは明らかに異なる激しい泣き方、長時間泣き続ける場合は何らかの痛みや体調不良が隠れている可能性があります。
② 泣く前に呼吸が止まる
泣く直前に呼吸が一時的に止まるような動きをする場合、睡眠時無呼吸症候群、けいれんなどの可能性があります。
大人が夜泣きをすることはありますか?
一般的に夜泣きと言えば乳幼児期の現象を指しますが、大人にも同様の現象が見られることがあります。ただし、大人の場合は夜泣きというよりも、夜間の異常行動や不眠症状として表現されることが多いです。
これらは複数の原因によって引き起こされます。医学的には以下のような状態や病気が関連します。
・夜驚症
・悪夢障害
・睡眠時無呼吸症候群
・ストレスや不安による睡眠障害
・うつ病や不安障害
・更年期障害
・月経前症候群(PMS)、月経前不快気分障害(PMDD)
・神経変性疾患や認知症
・アルコールや薬物の影響
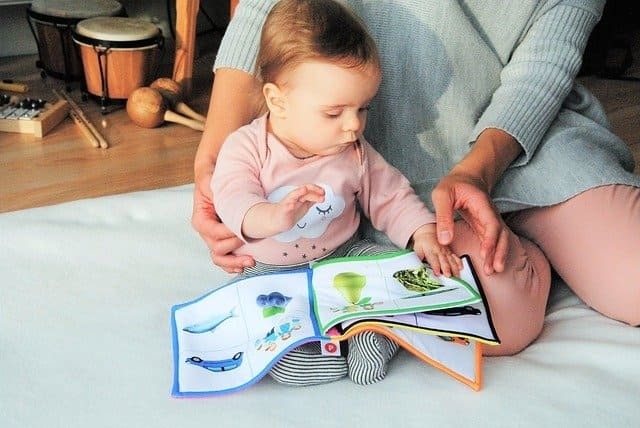
夜泣きを改善させる確実な方法はありません。色々な手段を試している間に、寝てしまうことが多いです。夜泣きは時間が経てば改善します。
抱っこで安心させたり、音や音楽などを軽く聞かせたり、思い切って一度起こしたりする方法で泣き止むこともあります。
さらに生活リズムを整えることが大事です。朝に起き夜に眠るという生活リズムが整えば、上手に睡眠を取ることができるようになることもあります。昼寝はほどほどにし、昼間はよく遊ばせて、夕方の遅い時間にはあまり寝ないように気をつけると良いでしょう。
夜泣きの対処法
・環境を整える
① 室温・湿度の管理
室温は20~22℃、湿度は50~60%程度が理想です。
② 照明を工夫する
就寝時には暗めの照明を使い、昼夜の区別をつけましょう。
③ 音や刺激を減らす
寝室を静かにし、外からの音を遮断します。また、強い光やテレビなどの刺激は避けましょう。
・規則正しい生活リズムを作る
① 決まった時間に寝かせる
毎日同じ時間に寝かせる習慣をつけましょう。
② 日中に十分な活動をさせる
昼間に適度な運動や外遊びをさせ、エネルギーを発散させておきましょう。
③ 昼寝の時間を調整する
昼寝の時間が長すぎると夜に寝つきにくくなるため、昼寝の長さを調整します。
・寝かしつけの工夫
① 寝る前のルーティンを作る
毎晩同じ流れを行い、寝る前の合図を作ることで安心させることができます。
② スキンシップを増やす
寝る前に優しく抱っこしたり、背中をなでたりしましょう。
③ 眠くなる前に布団に入れる
完全に眠くなる前に布団に入れることで、自力で寝る力を育てることで、夜中に目が覚めても泣かずに再び眠れるようになります。
・夜泣きが始まったときの対応
① 無理に起こさない
夜泣きの最中に無理に起こすと、かえって混乱し泣き続けることがあります。
② 過剰に反応しない
過剰に反応すると、夜泣きが親を呼ぶ手段として定着する可能性があります。
③ 授乳や水分補給をする
空腹や喉の渇きが原因の場合、授乳や水分補給を行います。
夜泣きに対しては鍼灸も効果的な場合があります。これは、医学的にも一定の効果が証明されています。
鍼灸で皮膚刺激を定期的に行うと、乳幼児の自律神経を安定させることにつながります。さらに、呼吸機能に活力も与えます。鍼灸は自律神経の安定や呼吸機能を活発にするための安全で効果が期待できる方法です。

赤ちゃんの夜泣きが始まる時期は、母親が1人で頑張ってしまうことが多いです。しかし、父親にもできることはたくさんあります。夫婦で協力して子育てをしていくことが大切です。
子供の夜泣きで夜中に何度も起こされると、追い詰められた気持ちになることもあるかもしれません。夫婦で協力して乗り切ってください。
父親は直接子供を泣きやませることができない場合、母親に対して気を配り言葉をかけたりすることも良いでしょう。色々な形で母親を支えることが、親子関係や夫婦関係にとって非常に大切なことです。
また、辛い時は我慢せず、周りの人の助けを借りたり、相談したりすることも大事です。
・身柱
・鳩尾
身柱
身柱は、精神的な高ぶりを抑えるツボです。そのため、ヒステリーやイライラに対して使われます。
小児の夜泣きをしているときや情緒不安定なときにも非常に有効です。他にも、感冒や咳、喘息などの呼吸器の問題にも効果的です。
鳩尾
鳩尾は、精神的な緊張をほぐす効果があります。そのため、精神的な疲れやイライラ、緊張によって起きる食欲不振や不眠などに有効です。
気持ちが張っているときには、鳩尾を刺激することで、緊張がほぐれリラックスできます。
ツボの位置と押し方
身柱
身柱は、第三胸椎棘突起の真下にあります。
夜泣きに対して使うときは、赤ちゃんを抱っこして、肩甲骨の間を上から下へ掌でゆっくり擦ります。ポイントはゆっくりと優しく擦ることです。
鳩尾
鳩尾は、肋骨が交わる骨の端から1~2㎝下がったところにあるくぼみにあるツボです。
押すときは、両手の人さし指と中指と薬指を立てて押します。ポイントはゆっくりとじんわりと押すことを意識することです。
スプーンでさする方法
子どもをうつ伏せにしてスプーンの腹で体をさする方法も効果的です。頭から首の付け根、背骨からお尻まで、上から下にさすります。このとき、スプーンの後を手が追いかけるようにスプーンと手で交互にさすることがポイントです。
優しく声を掛けたり、歌を歌いながら行うと良いでしょう。何度か繰り返し、さすったところが少し赤くなったり、子どもの頬が赤くなったら、十分に刺激が与えられたという合図になります。




