鍼灸が“痛み”を軽減するしくみ
【鎮痛効果のメカニズムについて解説】
○本ページの内容
- 「痛み」について
- 鍼灸がなぜ「痛み」を軽減できるのか
- 「痛み」と「自律神経の関係」

投稿者の吉田です。
このページを書いている私は、施術スタッフや鍼灸師として9年間臨床に携わり、多くの女性利用者様のお体を対応してきました。
その経験を記事にまとめておりますので、ぜひ最後まで御覧ください。

痛みというのは、身体がダメージを受けていることを知らせるための防衛反応であり、病気やケガで損傷した組織を修復する間、体を動かさないよう警告するためにも発生します。痛みは自身の身体を守る上で非常に大事な反応であり、その感じ方や程度は軽いものから、我慢できるが不快なもの、耐えがたいものまで様々です。
また、短期間で急性の痛みもあれば、長く続く慢性的な痛みもあります。このように、痛みには様々な種類がありますが、ここでは分かりやすく3つに分けて解説していきます。
侵害受容性疼痛
指先や足先に何か尖ったものが触れた際に感じるチクッとした痛み。
これを“侵害受容性疼痛”といいます。
体内には血管や神経が張り巡らされておりますが、外から何らかの刺激が加わると、身体の末梢部分に存在するセンサーである、“侵害受容器”がそれを感知し、その電気信号が脊髄を通って脳に伝わり「痛い」と感じる仕組みになっています。
神経性疼痛
長時間の同じ姿勢や使い過ぎにより、神経が圧迫されたりなど障害され、神経周囲に炎症が生じたりして感じる痛みです。これを“神経障害性疼痛“といいます。坐骨神経痛などがこれにあたります。
心因性疼痛
家庭や職場環境などで積み重なったストレスにより、脳の信号に何らかのトラブルが生じて発生します。首、肩、腰に痛みを感じることが多く、頭痛や顔面痛を訴える方もいます。このタイプの痛みが非常に厄介な理由として、器質的な変化が見られず、病院の検査で発見が不可能です。そのため原因が分からず長引くことが多いのが特徴です。
鍼灸の鎮痛効果は、上記で解説した痛みすべてに対応しています。
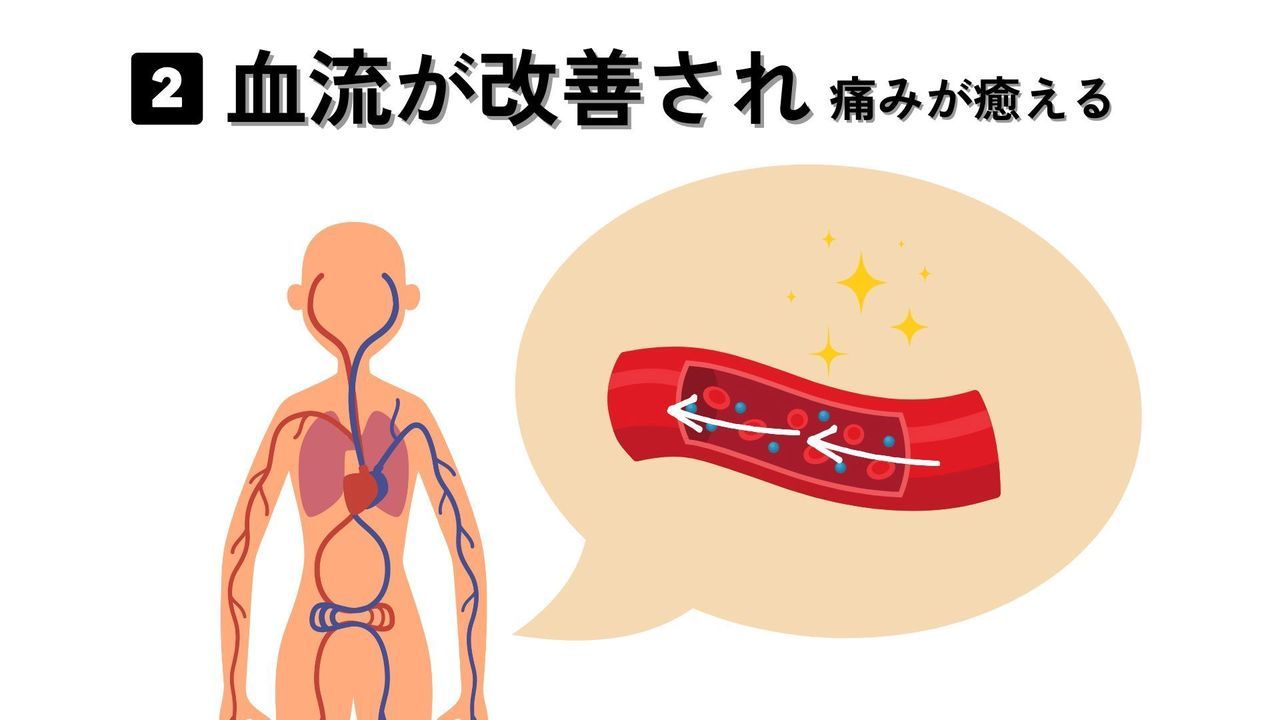
筋肉が緩んで血管が広がり、血の流れが良くなります。
血流が滞ると老廃物が溜まり、痛みの原因になりますが、それを血流改善することにより、体が痛みを自然に癒やす環境を整えることができます。
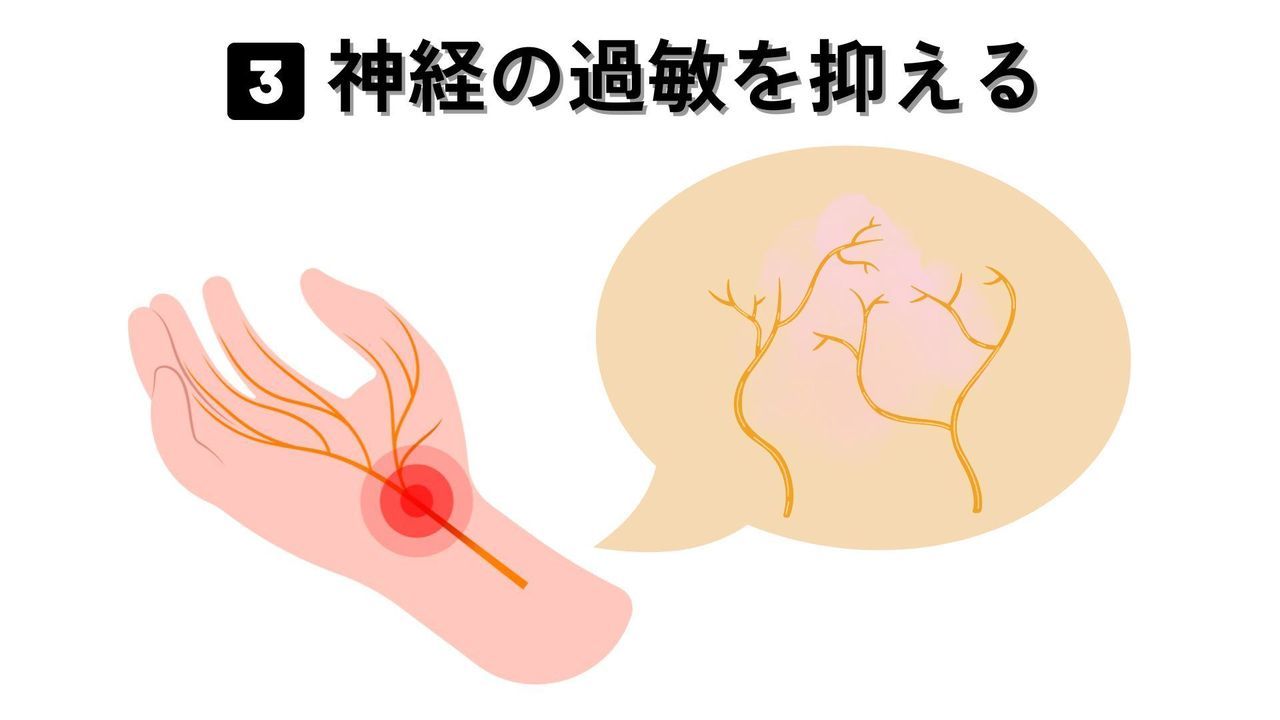
痛みは、ある場所の神経が過剰に興奮して引き起こされます。
鍼灸はその過敏になった神経の反応を落ち着ける効果があり、「痛みを感じやすい状態」が改善されます。

鍼灸は、体のリズムを調整する神経である、自律神経のバランスを整える効果があります。自律神経の乱れは痛みを感じやすくなることがあります。鍼灸によって体全体の緊張がほぐれ、心も体もリラックスすることで痛みの軽減につながります。

鍼やお灸による「別の刺激」が入ることで、
まとめ
鍼灸は、単に痛みを軽減するだけでなく、身体全体のバランスを整え、自然治癒力を高めます。現代医学が得意とする急性症状の対応と、東洋医学が得意とする慢性症状や体質改善を組み合わせることで、より豊かな健康生活を目指せます。もし慢性的な痛みや不調に悩んでいる場合は、一度鍼灸を試してみてはいかがでしょうか。鍼灸が対策の選択肢になれば幸いです。




