後部硝子体剥離の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2021年 8月11日
更新日:2025年 2月19日
本日は後部硝子体剥離について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- 後部硝子体剥離とは
- 後部硝子体剥離の原因
- 後部硝子体剥離の症状
- 後部硝子体剥離の改善方法
- 後部硝子体剥離のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

後部硝子体剥離の原因は、加齢です。
硝子体は、年齢を重ねることでコラーゲン線維が縮み網膜から離れて前の方に動いていきます。元々は透明なゼリー状で網膜とくっついていた硝子体が、年齢を重ねることで網膜面から離れ水晶体の方向に動くのです。
後部硝子体剥離では、最終的に視神経乳頭で強く網膜にくっついている硝子体の部分まで離れてしまいます。
硝子体剥離は、60歳代の約50%、70歳代では約70パーセントの人が発症すると言われています。白内障の手術した場合は手術の後、1年以内に発症することもありるとされています。
主な原因
・加齢による硝子体の変化
(1) 硝子体の液化
硝子体の成分は、約98%が水分で、コラーゲンとヒアルロン酸がゼリー状の構造を作っています。加齢により、硝子体内部のヒアルロン酸が分解され、水分が多くなりゼリー状の性質が失われ、液化した部分が増えることで、硝子体が収縮し、網膜から剥がれます。
(2) 硝子体皮質の後方移動
硝子体が液化、収縮すると、硝子体皮質が網膜から剥がれて後方へ移動します。特に、視神経乳頭から剥がれることで、後部硝子体剥離が起こります。
(3) 加齢によるコラーゲン線維の変化
硝子体を支えるコラーゲン線維が劣化し、構造が崩れることで硝子体が網膜から剥がれやすくなります。
・眼の外傷や手術の影響
(1) 外傷による硝子体剥離
眼球に強い衝撃が加わると、硝子体が急激に変形し、網膜から剥がれます。スポーツや事故などで起こりやすいです。
(2) 白内障手術後の硝子体変化
白内障手術で水晶体を摘出すると、眼の内部環境が変化し、硝子体の液化が進みます。手術後に発生しやすいです。
・炎症・病的変化による硝子体剥離
(1) ぶどう膜炎
ぶどう膜炎が発生すると、炎症により硝子体の変性が進行しやすくなり硝子体が網膜から剥がれやすくなります。
(2) 糖尿病網膜症
糖尿病による網膜血管障害が進行すると、新生血管が発生し、それに伴い硝子体と網膜の接着が変化し、硝子体が剥離しやすくなります。
(3) 黄斑円孔
硝子体が網膜の中心部を引っ張ることで、黄斑円孔ができやすくなります。
・生活習慣、環境要因
(1) 眼精疲労・ストレス
長時間のスマホ、PC作業により眼精疲労が進むと、硝子体が網膜を引っ張る力が強くなり、剥離しやすくなります。
(2) 血流障害、高血圧
網膜の血流が悪くなると、硝子体や網膜の組織の老化が進行し、硝子体剥離が起こりやすくなります。
(3) 喫煙、栄養不足
喫煙は血管を収縮させ、網膜や硝子体の栄養供給を低下させるため、加齢変化を促進します。

後部硝子体剥離の主な症状は、飛蚊症です。他にも光視症や霧視も現れます。
後部硝子体剥離が起こると、硝子体の後部の膜が網膜にうつるため、明るい場所を見見たとき、虫や糸くずが飛んでいるように見えるのです。この症状は、目をこすったり瞬きをしたりしても消えることはありません。
光視症は走るような光を感じることです。これは、硝子体によって網膜が刺激を受けることで起こる症状です。
霧視は、硝子体の引っ張りにより網膜血管に傷がつき硝子体出血が起こった場合に起こります。
主な症状
・飛蚊症
・光視症
・視界のかすみ
・視力低下
・視野欠損
突然飛蚊症が増えた、強い閃光が続く、視野の一部が黒くなる、カーテンがかかったように見える、急激な視力低下などの症状がある場合は要注意です。

後部硝子体剥離に効果的な改善方法はありません。
後部硝子体剥離は症状が進むと、他の病気につながることがあります。そのため、眼科にいくことは非常に大切です。
他の病気引き起こした場合、手術などが必要になることもあります。他の病気を発症しないためにも、眼科に行き、医者と一緒に経過をみることが大切なのです。
主な改善方法
・自然経過観察
飛蚊症や軽度の光視症のみで視力低下や視野欠損がない場合は経過観察を行います。
・レーザー
網膜裂孔が発生したが、まだ網膜剥離には進行していない場合や網膜の一部が薄くなっており剥離リスクが高い場合、飛蚊症が急激に増え裂孔の疑いがある場合に行います。
・ 硝子体手術
網膜裂孔が進行し網膜剥離が発生した場合や大量の硝子体出血があり視力低下が著しい場合、強い飛蚊症が続き日常生活に支障がある場合に行います。
・薬
後部硝子体剥離自体を改善する薬はありませんが、症状の軽減や合併症の予防に薬を使うことはあります。カルバゾクロムやトラネキサム酸、ラタノプロスト、抗VEGF薬を使います。
・生活習慣、セルフケア
軽度の後部硝子体剥離の場合やレーザーを行った後の再発予防を行う場合、網膜の健康維持をしたい場合に行います。目を強くこすらない、急な頭の動きを避ける、適度な運動を行い血流を改善する、長時間のスマホやPC作業を避け目を休めるなどが有効です。
・ 鍼灸
眼精疲労やストレスの軽減、血流促進による回復補助、飛蚊症の軽減に効果的です。
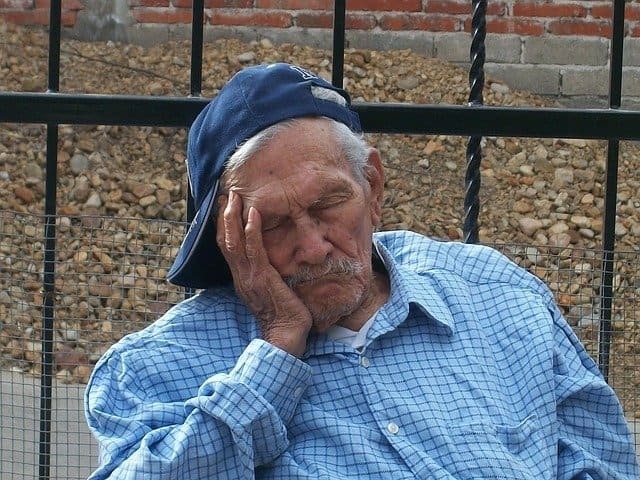
後部硝子体剥離は加齢で起こる老化現象です。そのため、基本的には今まで通りの生活を送って問題ありません。
しかし、中には注意が必要な場合もあります。硝子体が網膜から離れるとき、網膜も一緒に強く引っ張ってしまうことが稀に起こるのです。すると、網膜剥離や硝子体出血を起こしてしまうことがあります。
眼科で経過を見ておくことで異変があった時にも早期発見につながります。後部硝子体剥離が起こった時は眼科に行くことをお勧めいたします。
後部硝子体剥離自体は、多くの人が50~60歳以降に経験するもので、加齢に伴う正常な変化ですが、症状の管理や網膜の病気の予防のために適切なケアを行うことが推奨されます。
特に飛蚊症が急に増えた、光視症が頻繁に起こる、視野の一部が欠ける、網膜裂孔や網膜剥離のリスクが高いと病院で言われた、強度近視で網膜が薄くなっているなどの症状がある場合は、眼科で定期的に調べながら、生活習慣の見直しや血流改善を行うことが望ましいです。
おすすめ記事
- 特に対応することが多い症状
- 筋肉、骨のお悩み
- 消化器のお悩み
- 皮膚のお悩み
- 神経のお悩み
- 循環器のお悩み
- 眼のお悩み
- 耳鼻咽喉のお悩み一覧
- 泌尿器のお悩み一覧
- 女性のお悩み一覧
- 脳神経のお悩み一覧
- 子供のお悩み一覧
- がんの種類一覧
- 内分泌のお悩み一覧
- 自律神経のお悩み一覧
- 鍼灸・東洋医学について




