薬害性難聴の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2021年 5月23日
更新日:2025年 2月10日
本日は薬害性難聴について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- 薬害性難聴とは
- 薬害性難聴の原因
- 薬害性難聴の症状
- 薬害性難聴の改善方法
- 薬害性難聴のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。
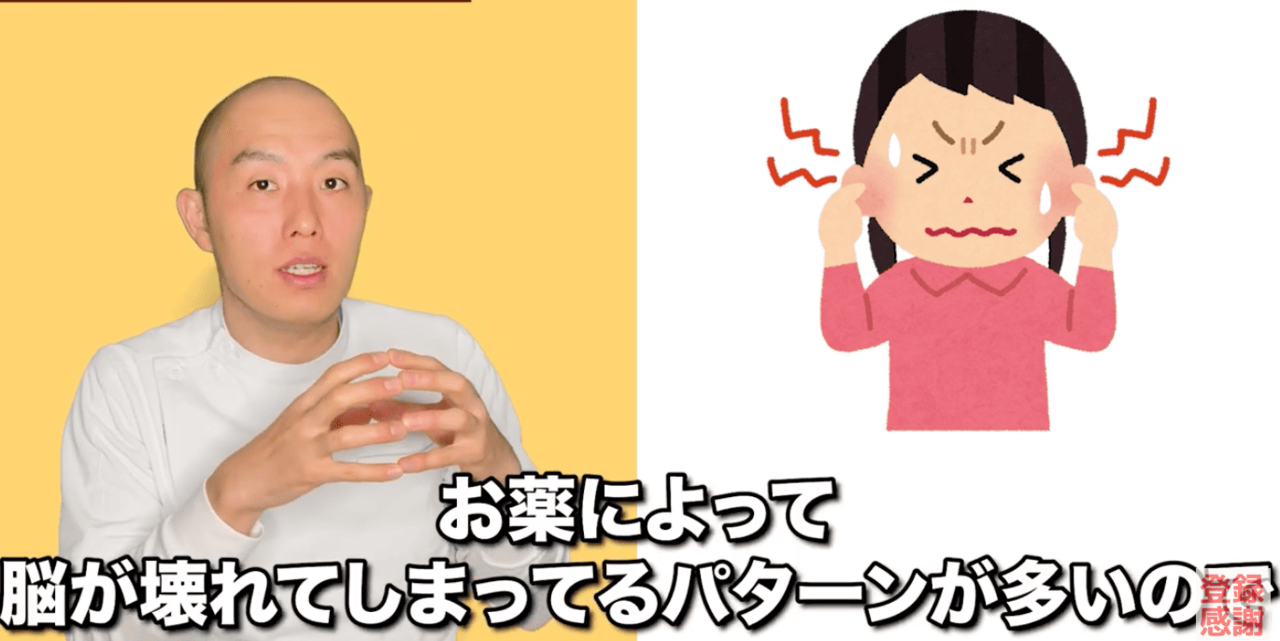
薬害性難聴の原因は薬です。主に、抗菌剤であるアミノグリコシド系やグリコペプチド系などが原因になる可能性のある薬剤とされています。
心不全などに対して使われることのあるループ利尿薬、抗がん剤の白金製剤、解熱鎮痛剤として使われることのあるアスピリンなどのサリチル酸製剤も薬害性難聴の原因となる可能性がある薬剤です。
アミノグリコシド系の抗菌薬や白金製剤が原因の場合、改善することが難しい難聴が起こることが多いです。マクロライド系の抗菌薬やループ利尿薬、サリチル酸製剤が原因の場合は、一時的な難聴がほとんどです。
原因となる薬
1. アミノグリコシド系抗生物質
例: ゲンタマイシン、ストレプトマイシン、ネオマイシンなど。
これらは強力な抗生物質で、特に結核や重度のバクテリア感染症の改善に用いられますが、耳毒性が強いため、聴力損失を引き起こすリスクがあります。
2. 白金系抗がん剤
例: シスプラチン、カルボプラチンなど。
白金系抗がん剤は広範囲のがんの改善に用いられますが、耳毒性が知られています。
3. ループ利尿薬
例: フロセミド(ラシックス)。
これらの利尿薬は、急性腎不全や心不全の改善に用いられることがありますが、高用量では耳毒性を示すことがあります。
4. 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
例: アスピリン、イブプロフェンなど。
これらは通常は耳毒性が低いですが、大量または長期間の使用により耳鳴りや一時的な聴力低下を引き起こすことがあります。
5. マラリア改善薬
例: キニーネ。
キニーネはマラリアの改善に用いられますが、耳毒性があり、特に高用量で使用された場合に聴力損失を引き起こす可能性があります。
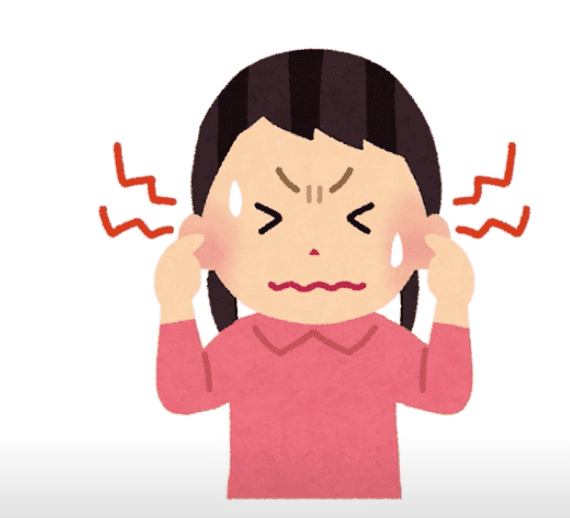
耳鳴りについて
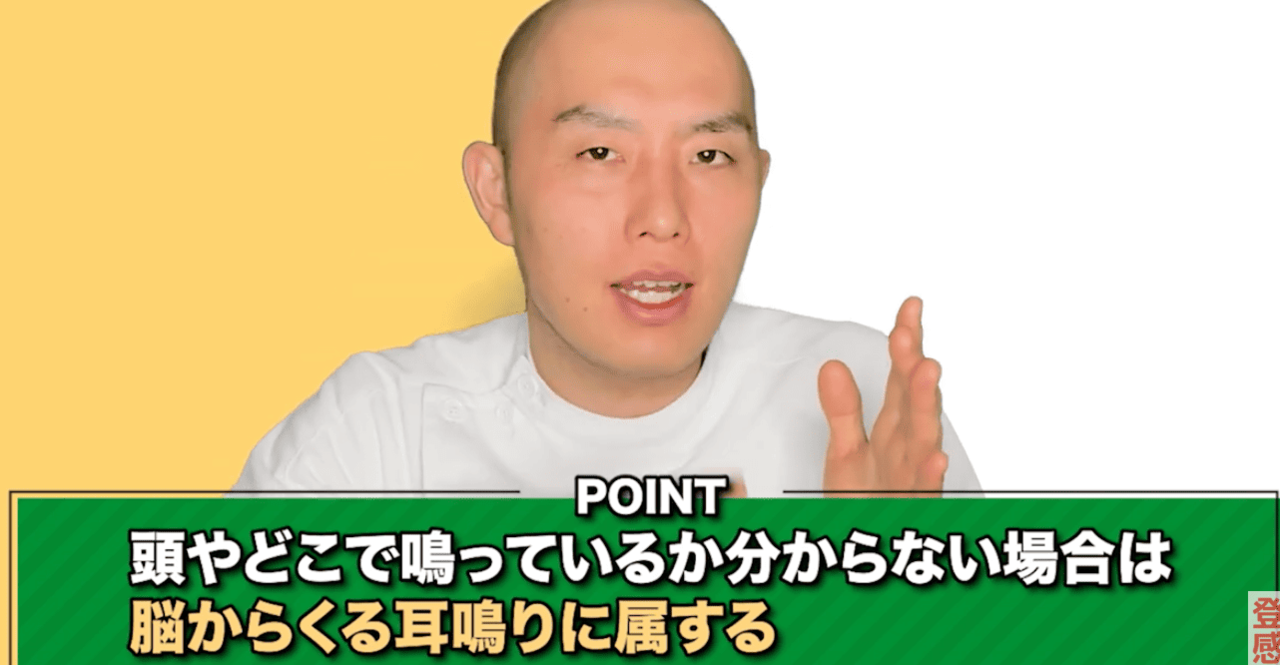
耳鳴りは多くの人が経験する症状です。耳鳴りは病気ではありません。人間が持つ生理反応の1つです。そのため、耳鼻科では改善が苦手で慣れるか紛らわせるかの2択になります。
耳鼻科などにおける耳鳴りの改善方法はTPTや補聴器不安薬の処方が一般的です。一方で鍼灸院に来る人は全ての改善方法を経てきた人がほとんどのため改善しやすいタイプに属します。
耳鳴りには脳からくるものと耳からくるものがあります。中でも脳からくる耳鳴りは鍼灸が適しています。脳からくる耳鳴りの判断方法は、耳を塞いで耳鳴りがどこで鳴っているか認識することです。耳で一定の高い音が鳴っている場合は耳からくる耳鳴りに属します。頭やどこでなっているかわからない場合は脳からくる耳鳴りに属します。
鍼灸で改善を行うと耳鳴りが徐々に変動します。うるさい日があったり静かな日があったりするのです。うるさい日が何日も続いたら急に静かになったりというように増減を繰り返していくとそのあとだんだん回復していき、幅が狭くなってきて0の日が出てきます。
最終的に0〜2を繰り返すようになりそこまでいくと日常生活に支障もなくなります。耳鳴りを忘れている時間の方が多いため、気にならなくなって改善したと喜んでくれる方がほとんどです。
耳からくる耳鳴り
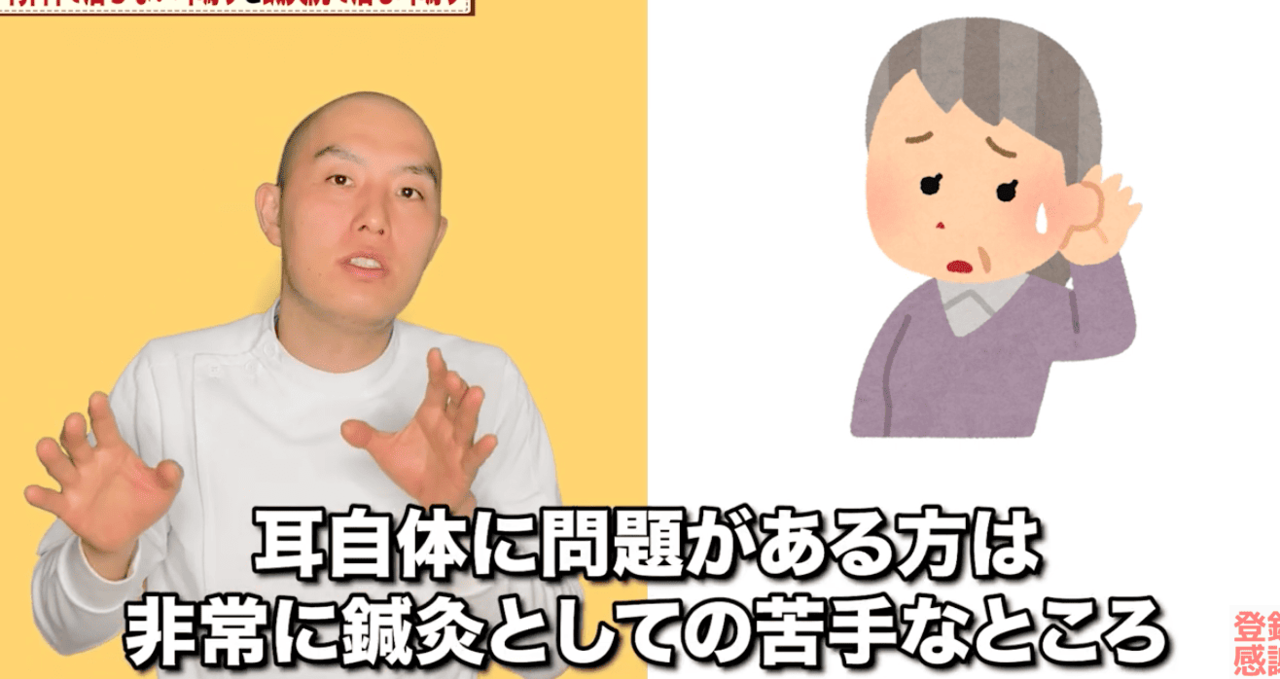
耳からくる耳鳴りの場合は耳鼻科も鍼灸も苦手です。耳からくる耳鳴りで1番多いタイプは、老人性難聴や突発性難聴、メニエール病、外傷や騒音性難聴などです。耳自体に問題がある場合は鍼灸でも苦手です。
メニエール病や突発性難聴の後の症状は鍼灸では得意ですが、耳の状態が悪化した場合は耳の回復力次第で改善するかしないかが決まります。
当院では、突発性難聴で悩んでいる人は36時間以内のステロイド服用を推奨しています。また、再発する人も多いためステロイドの常備も当院ではお勧めしています。
初期の対応が今後の耳鳴りや耳の状態を左右するため、全く聞こえなくなったり高音域の耳鳴りが急に現れたりした場合はすぐに耳鼻科に行ってほしいと思います。鍼灸やセルフケアで対処するのも良いですが突発性難聴だった場合は後の経過が非常に悪くなるため早くステロイドの処方を受けてほしいです。
耳鼻科や鍼灸院でも力になれない耳鳴りは薬害です。当院でもインフルエンザとコロナワクチンと抗うつ剤で耳鳴りが起こった方がいましたが、未だに院長の経験上では改善したことがありません。あらゆる手を尽くしても耳鳴りに変動がなかったのです。
通常耳鳴りは施術をすると強くなったり下がったりするような回復の兆候が見られます。悪化することはいいことではありませんが、悪化することで原因にあたっているという1つの指標になるためその場合力になれる可能性があります。
薬害の場合は薬によって脳が壊れてしまっているパターンが多いため、耳にアプローチしたり強い刺激を与えられても音の変動が一切ないのです。薬害と思われる人は施術を受けていくとわかります。回復の兆候がないため本人も改善しないと自覚するケースが多いです。そのくらい施術を受けても変わらないのです。こうなると対応策としては慣れるしかありません。
当院では薬害が疑われる場合3〜6回の施術を受けてもらいます。この間に何も変わらなければ当院で改善するのは難しいとお話ししています。薬害は非常に恐ろしいのです。
耳垢をとるアプローチや注射や手術などの物理的なアプローチで起きた耳鳴りも当院では改善したことがありません。耳の中はデリケートなため改善方法を選択する際は医師と必ず相談してほしいです。
耳鳴りで亡くなった人はいないと病院で軽くあしらわれることも多いですが、実際に人生の質を限りなく下げてしまう症状です。特に薬害に関しては非常に辛い状態を垣間見ることがあり悲しい思いをすることもあります。
実際にあることを知るだけでも健康寿命を伸ばしたり健康の知識を深めるきっかけになっていただけると嬉しいです。
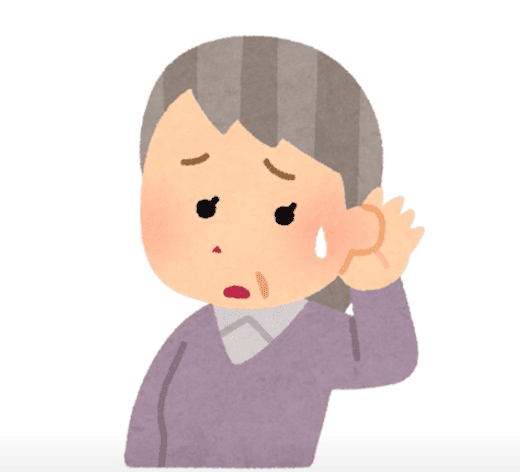
薬害性難聴の主な症状は、耳鳴りや耳の閉塞感などです。
中でも、アミノグリコシド系の抗菌剤や白金製剤を使った時に起きる難聴では、日常生活であまり使わない高音の領域の音が中心に聞こえにくくなります。そのため、その場合は難聴よりも耳鳴りや耳の閉塞感を先に感じることが多いです。
ループ利尿剤やサリチル酸製剤を使った時に起きる難聴では、低音の領域の音から高音の領域の音まで全般的に難聴が起きます。
難聴や耳鳴りなどの耳の症状に合わせて、めまいや浮動感などの平衡障害の症状が現れることもあります。
主な症状
聴力低下: これは薬害性難聴の最も一般的な症状で、片耳または両耳で聴力が低下します。この症状は徐々に進行することも、突然発生することもあります。
耳鳴り: 耳鳴りは、耳なりの形で聴覚障害が始まることがあります。これは、キーンという音、サイレンのような音、または他の連続的な音として現れることがあります。
平衡感覚の問題: 薬害性難聴は時に平衡感覚にも影響を及ぼし、めまいやバランスの問題を引き起こすことがあります。
音の歪みや感度の変化: 特定の周波数の音が聞こえにくくなったり、普通の音が非常に大きく聞こえたりすることがあります。

一般的に薬害性難聴を改善するためには、薬剤の使用を中止することが必要です。
しかし、アミノグリコシド系抗菌剤や白金製剤が原因で薬害性難聴が起こった場合は薬剤を中止しても改善することは難しいです。そのため、早期発見することが大切です。
薬害性難聴を予防することも非常に大切です。家族などに薬害性難聴者が起こった人がいる場合は、薬を使う前に遺伝子を調べておくことで予防につながります。
さらに心配な場合は薬を使う前に耳鼻咽喉科に行き、聴力を調べ、薬を使ってからも定期的に調べに行くことで自分で聴力を管理しておくことをお勧めします。
主な改善方法
1. 原因薬剤の中止
薬害性難聴が疑われる場合、最も重要なステップは、原因となる薬剤の使用を直ちに中止することです。
2. 代替薬剤の検討
薬剤が重要な改善に必要な場合は、耳毒性のない代替薬剤への変更を検討します。
3. 聴力の評価とモニタリング
定期的な聴力の調べを通じて、聴力損失の程度を評価し、進行をモニタリングします。
4. 聴覚補助装置の利用
聴力損失が重度の場合は、補聴器などの聴覚補助装置の使用を検討します。
5. コミュニケーションのサポート
専門家によるコミュニケーションのサポートやリハビリテーションが提供されることがあります。
6. サポートとカウンセリング
聴覚障害に対応するためのサポートや心理的カウンセリングを提供し、生活の質を改善します。
聴覚補助装置
1. 補聴器
補聴器は、外耳道に装着し、周囲の音を増幅する装置で、軽度から重度の聴力損失に対応する様々なタイプがあります。補聴器には、耳掛け型、耳穴型、耳道型など多様な形状があり、患者の聴力レベル、耳の形、個人的な好みに応じて選択されます。デジタル補聴器は、特定の周波数を増幅するなど、カスタマイズが可能です。
2. 骨伝導補聴器
骨伝導補聴器は、音を骨を通じて内耳に直接伝えることで聴覚を補助します。伝導性難聴や混合性難聴のある人、または通常の補聴器を使うことができない人に適しています。
3. コクリアインプラント
コクリアインプラントは、重度の感音難聴に対する手術による方法です。内耳に電極を直接埋め込み、音を電気信号に変換して聴神経に直接刺激を与えます。聴覚が大幅に低下した人にとって、効果的な聴覚回復手段の一つです。
4. その他の補助装置
FMシステムや赤外線システムなど、特定の状況で使用される特別な聴覚補助装置もあります。電話、テレビ、警報システム用の補助装置も存在します。
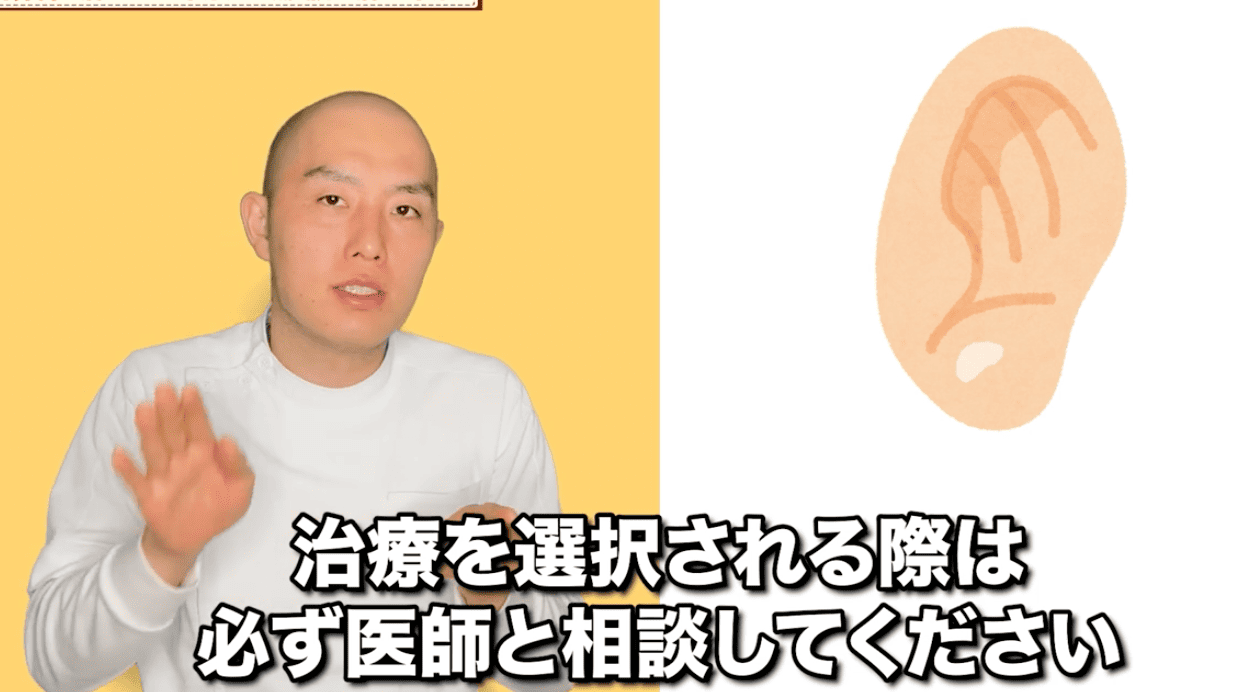
薬害性難聴は難聴に自分で気がつくまでに時間がかかることもあります。その場合、気がつかない間に難聴が進んでしまっていたということになってしまう可能性もあります。
周りに、聞き返すことが多くなった、テレビを見ている時の音を急に大きくする、声をかけても気がつかなくなった、などの状態が見られる人がいた場合、その人は聴力が低下しているかもしれません。
気がついた場合は、病院に行くことを勧めてみても良いでしょう。
・聴宮
・完骨
・聴会
聴宮
聴宮は、聴覚の要所という意味を持つツボであることがツボの名前の由来であると言われています。耳鳴りや難聴など、主に耳に現れる症状を改善するときに使われるツボです。
そのため、薬害性難聴に対しても改善の効果が期待できます。他にも、頭痛や歯の痛みにも効果的であるとされています。
完骨
完骨は、内臓への血流を促し、副交感神経を整える効果があります。内臓だけでなく、顔の周りの血流も促してくれるため、吹き出物などに対しても効果を発揮します。
耳の近くにあることから、耳の症状にも効果を発揮するといわれており、耳鳴りや難聴、めまいの改善に使われることもあります。そのため、薬害性難聴にも効果が期待できるのです。
聴会
聴会は、難聴や耳鳴りなど聴覚に関する症状に対して効果を発揮するツボです。そのため、薬害性難聴で聞こえが悪い時に刺激をすることで改善の効果が期待できるのです。
聴会は、他にも腰痛や膝の痛みにも効果を発揮すると言われています。
聴宮

聴宮は、耳の前に三角形の突起物がある前の口を開けるとくぼむ場所にあります。耳門というツボの指1本分下に下がったところが聴宮なのです。
耳鳴りや耳詰まりなど耳の不調を感じたとき、中指の腹を使って押しましょう。
完骨

完骨は両耳の後ろにある出っ張った骨の下の端の後ろ側のくぼんでいる場所にあります。
押すときは、親指でゆっくり上に押し上げるようなイメージで押しましょう。 完骨は幸せホルモンであるセロトニンの分泌を安定させる効果もあるため、リラックスしたい時にもお勧めです。
聴会

聴会は、耳珠の下のすぐ前で、下顎骨の後縁にあります。聴宮の少し下にあるツボなのです。
聴会だけを押すのではなく、聴宮と一緒に押すことでより効果が期待できます。聴会を人差し指を使って、聴宮を中指を使って一緒に押しましょう。




