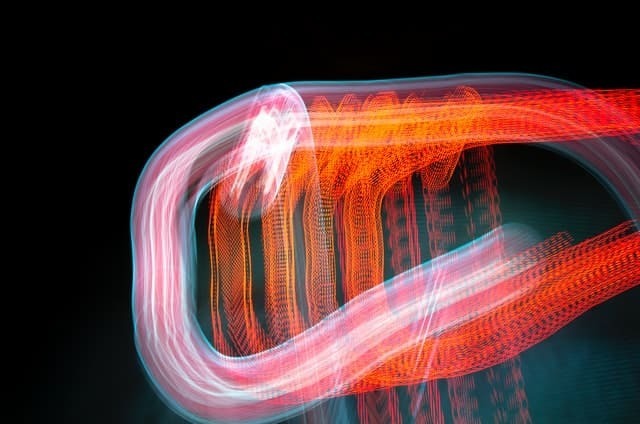小脳梗塞の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2022年 5月23日
更新日:2025年10月 5日
本日は小脳梗塞について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- 小脳梗塞とは
- 小脳梗塞の原因
- 小脳梗塞の症状
- 小脳梗塞の改善方法
- 小脳梗塞のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。
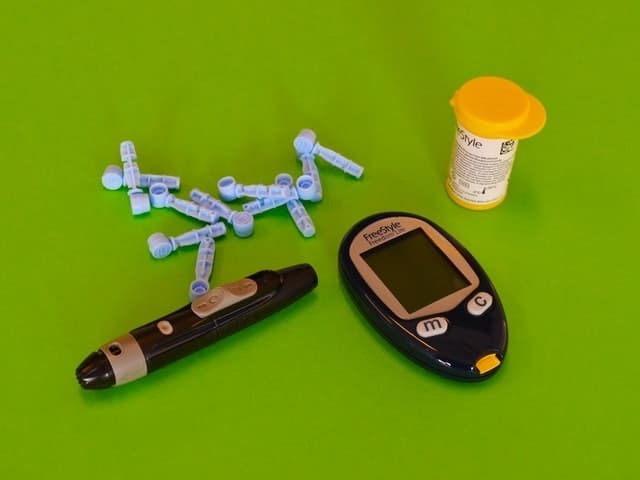
小脳梗塞の原因は主に4つあります。1つ目の原因は、高血圧です。高血圧が原因の場合は、脳の細い血管が詰まり、ラクナ梗塞と呼ばれます。
2つ目の原因は、高脂血症や高血圧や糖尿病などの生活習慣病です。生活習慣病が原因の小脳梗塞は、脳の太い血管が動脈硬化を起こして血管に血栓ができ、詰まるります。この場合をアテローム血栓性脳梗塞と呼びます。
3つ目の原因は、心房細動です。心房細動は高齢者に多く起こる不整脈です。心房細動が原因で起こった場合、心臓でできた血栓が脳まで運ばれて詰まる心原性脳梗塞と呼ばれます。これは、心臓病を持った人に起こることが多いです。
4つ目の原因は、椎骨動脈解離です。これは、小脳や脳幹梗塞で特徴的な脳梗塞で、若い人に発症することが多いです。椎骨動脈解離は、首を回したり過度のマッサージをしたりすることが原因で起こります。
主な原因
小脳には、「上小脳動脈」「前下小脳動脈」「後下小脳動脈」という3本の主要な動脈が走っています。これらの血管のどれかが血栓や塞栓で詰まると、その支配領域の神経細胞が酸素不足に陥り、小脳梗塞が発生します。
① 血栓性(血管が詰まるタイプ)
脳や首の血管そのものに動脈硬化が起こり、血流が途絶えるタイプです。主に高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、加齢、慢性的なストレスや睡眠不足が背景にあります。
② 塞栓性(他の場所から血の塊が飛んでくるタイプ)
心臓や頸動脈でできた血栓が流れ、小脳の血管を塞ぐタイプです。心房細動、弁膜症、心筋梗塞の既往、人工弁の装着、大動脈プラークが背景にあります。
③ 血流低下性(血圧低下などによるタイプ)
血管が詰まるわけではなく、一時的な血流低下で小脳に十分な酸素が届かなくなるタイプです。重度の脱水、外傷や手術による出血性ショック、心臓のポンプ機能低下、血圧が急激に下がるなどの背景があります。このタイプは高齢者や持病を持つ人に多いです。

小脳梗塞の症状は、めまい、吐き気、嘔吐、耳鳴り、難聴などです。
ろれつが回らなくなったり、ぼーっとしたり、立ったり座ったりするときにバランスが取れなくなったり、歩くときにふらふらしたり、転んだり、上手く手足が動かせなくなったりすることなども現れます。
脳梗塞の症状では、片側の手足に力が入らなくなったり麻痺したりすることが多くありますが、小脳梗塞では力は入り麻痺もありません。しかし、スムーズに動かすことができなくなります。
主な症状
① めまい
特に回転性のめまいが起こります。前庭神経障害と似ていますが、小脳性めまいは体幹のふらつきが強く、眼振が顕著です。嘔吐を伴うことも多く、急に立てなくなったり歩くと倒れそうになったりします。
② 体のふらつき・平衡感覚の低下
歩こうとするとまっすぐ歩けず、左右に揺れ、片側性の場合障害側に体が傾きます。手足を動かしても、狙ったところに正確に届かなかったり書字や箸を使う動作がぎこちなくなったりします。
③ 言葉のもつれ
ろれつが回らず、話しづらくなり、一語一語が途切れるような断続的な話し方になります。
④ 眼振・眼球運動障害
目が左右、上下に小刻みに揺れ、物が揺れて見えます。眼球の協調運動が崩れ、焦点を合わせづらくなります。特に上小脳動脈や前下小脳動脈の障害でよくみられます。
⑤ 頭痛・嘔吐
強い後頭部痛や項部の痛みや小脳の浮腫よって頭蓋内圧の上昇が起こります。吐き気や嘔吐を伴い、脳出血と間違われることもあります。重症化すると、意識障害や呼吸抑制を起こすため、早期発見が極めて重要です。
⑥ 感覚・運動異常
小脳自体には感覚や運動を司る領域はありませんが、脳幹や延髄に近いため、圧迫や虚血が広がると顔のしびれや口の歪み、嚥下困難や構音障害、片麻痺、半身のしびれ、呼吸抑制、意識障害が起こります。

小脳梗塞の改善の目的は、できるだけ後遺症が残らないようにすることです。これは、脳梗塞でも同じです。
発症してから4~5時間以内の場合は、脳の血栓を溶かす薬を使います。最近は、脳の太い動脈が詰まっているとき、足の付け根の血管から脳血管までカテーテルを入れて血栓を回収する改善法も使われています。
小脳の隣には脳幹があるため、小脳梗塞で小脳が腫れると脳幹を圧迫しやすい状態になります。脳幹を圧迫してしまうと命にも関わるため、脳の腫れを防ぐ薬を使ったり手術によって頭蓋骨を外したりすることもあります。
症状が落ち着いた後はリハビリテーションを行い、退院した後は原因となった病気に合わせて再び発症しないように薬を使ったり生活習慣の改善を行ったりすることが大事です。
主な改善方法
① 血栓溶解法
発症から4.5時間以内なら、t-PA点滴が行われます。これは血栓を溶かして血流を再開させる方法です。
② カテーテルによる血栓除去
発症6時間以内であれば、カテーテルを使って血栓を吸い出す方法も行われます。椎骨動脈や脳底動脈が詰まった場合に有効です。
③ 浮腫に対する処置
小脳は頭蓋骨内の限られた空間にあるため、梗塞による脳浮腫が脳幹を圧迫すると呼吸停止や意識障害に至ることがあります。そのため、抗浮腫薬の投与や水分と塩分バランスの厳密管理が行われます。重症例では開頭減圧術も行われます。
④ 抗血小板薬・抗凝固薬による再発予防
原因が動脈硬化や心原性塞栓によるものであれば、再発防止のために薬を継続します。アスピリンやクロピドグレル、ワルファリンやDOAC、スタチン系薬などを使います。
回復期の鍼刺激は、脳血流量が増加し、神経の栄養供給が促されます。小脳性のめまいやふらつきは、前庭神経と眼球運動の連動障害が背景にあるため、鍼灸で首、耳まわり、自律神経系を整えることで、平衡系のリハビリ効果を高めます。
脳卒中後は交感神経が過剰に高まりやすく、不眠、不安、易疲労感が回復を妨げます。鍼灸は副交感神経を高めてリラックス反応を誘発し、自分自身の回復力を最大化する効果もあります。

小脳梗塞は小脳に起こる脳梗塞です。しかし、小脳梗塞を起こした時、小脳だけではなく、同時に脳幹や大脳にも梗塞が起きていることも多くあります。
脳幹や大脳に梗塞が起きると、体の片側に麻痺が起こったり、顔がゆがんだり、話しにくくなったりします。自分の症状に注意して、小脳梗塞だけでは現れないような症状がある場合は、症状に気がついたらすぐに病院に行きましょう。
おすすめ記事
- 特に対応することが多い症状
- 筋肉、骨のお悩み
- 消化器のお悩み
- 皮膚のお悩み
- 神経のお悩み
- 循環器のお悩み
- 眼のお悩み
- 耳鼻咽喉のお悩み一覧
- 泌尿器のお悩み一覧
- 女性のお悩み一覧
- 脳神経のお悩み一覧
- 子供のお悩み一覧
- がんの種類一覧
- 内分泌のお悩み一覧
- 自律神経のお悩み一覧
- 鍼灸・東洋医学について