慢性移植片対宿主病の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2023年 2月 1日
更新日:2023年 2月 8日
本日は慢性移植片対宿主病について解説させていただきます。

☆本記事の内容
- 慢性移植片対宿主病とは
- 慢性移植片対宿主病の原因
- 慢性移植片対宿主病の症状
- 慢性移植片対宿主病の改善方法
- 慢性移植片対宿主病のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

慢性移植片対宿主病は、造血幹細胞移植を行った後に発症する病気です。原因は、膠原病に似ていて自己免疫に関係すると言われています。これは、慢性移植片対宿主病を発症している人のほとんどの人に自己抗体が認められるためです。
発症する頻度は、末梢血幹細胞移植を行った人の約6割、骨髄移植を行った人の約4割であると言われています。
慢性移植片対宿主病の主要な原因は、ドナーの移植片(一般には骨髄や幹細胞)が受け取り手の体(宿主)を「異物」として認識し、攻撃を始めることです。
・免疫応答の不整合
HLA(ヒト白血球抗原)不一致: HLAは、免疫細胞が自分自身と外来物を識別するための重要なマーカーです。HLAが不一致であるほど、GvHDのリスクが高くなります。
マイナーヒストコンパチビリティ抗原(mHA): これも自己と非自己を識別するためのマーカーであり、HLAとは独立しています。mHAの不一致もGvHDの原因となる可能性があります。
・免疫細胞の活性化
T細胞: ドナーのT細胞は、特に攻撃的な役割を果たすことが多いです。
B細胞: これらも攻撃的な反応を示す可能性があり、慢性GvHDにおいてはより注目されています。
樹状細胞: これらの細胞は、T細胞やB細胞を活性化する役割を果たす可能性があります。
・環境的、遺伝的要因
年齢: 年齢が高いほどGvHDのリスクが高まることが示されています。
性別: ドナーと受け取り手の性別の不一致も、GvHDのリスクを増加させる可能性があります。
遺伝的素因: 一部の遺伝子はGvHDの発症に関与している可能性があります。
・病院による処置と関連因子
免疫抑制剤: 移植後の免疫抑制法が不十分または不適切である場合、GvHDのリスクが高くなる可能性があります。
感染症: ウイルスなどの感染症がGvHDの発症を誘発または悪化させる可能性があります。
慢性移植片対宿主病は多くの因子によって引き起こされ、それぞれ個人によって発症の原因や経過が異なる可能性があります。この病気は非常に複雑であり、完全な解明には至っていません。しかし、移植前の詳細なHLAタイピング、適切な免疫抑制法、感染症の管理などが重要な改善戦略とされています。最新の研究によっても、より効果的な予防と改善法が開発されつつあります。

慢性移植片対宿主病は、感染症を合わせて発症したり、生活の質の低下につながったりします。
症状が現れやすい部位は、皮膚、口腔、目、肝臓で、皮膚に起きた場合湿疹が出たり皮膚が硬くなったり、皮膚の色が黒くなったり、皮膚の色が抜けて白くなったり、脱毛が見られたりします。
口腔に起きた場合は、口の粘膜に白い網目のような変化が見られたり食事や歯磨きで痛みが現れたりします。目に起きた場合、充血や目の痛み、目の表面の乾燥などが起こります。
肝臓の場合は、特に症状が現れないことが多いです。しかし、血液を調べると肝機能値の上昇がみられます。
慢性移植片対宿主病は、移植後に特に注意が必要な状態の一つです。以下に慢性移植片対宿主病の病状の主な症状について詳しく解説します。
・皮膚症状
皮膚はcGVHDで最も一般的に影響を受ける器官です。
発赤と湿疹: 皮膚の一部が赤くなり、かゆみや炎症が生じることがあります。
硬化と線維症: 皮膚が硬くなり、動きにくくなる場合があります。
顔面の変色: ピグメンテーションの変化も見られることがあります。
・口腔症状
口内もしばしば影響を受けます。
口内炎: 口の内側が赤く炎症を起こす場合があります。
歯肉炎: 歯肉が腫れたり、出血することもあります。
乾燥と唾液減少: 口が非常に乾燥し、これが食事や話すことに影響を与える場合があります。
・消化器症状
食道炎: 食道に炎症が生じ、食事中に痛みや不快感がある場合があります。
下痢と便秘: 腸の働きが乱れると、下痢や便秘が続くこともあります。
吸収障害: 重度の場合、栄養素の吸収が悪くなることがあります。
・肺症状
呼吸困難: 肺が硬くなり、呼吸が困難になる場合があります。
咳: 長引く咳が生じることもあります。
酸素飽和度低下: 深刻な場合、酸素の供給が不足してくることもあります。
・眼症状
ドライアイ: 眼が乾燥し、痛みや充血を引き起こす場合があります。
網膜症状: 網膜に影響を受け、視力が低下する可能性があります。
・その他の症状
関節と筋肉の痛み: しばしば関節痛や筋肉の硬化が報告されます。
疲労感: 一般的な体力の低下や疲労が見られます。
cGVHDの症状は多岐にわたるため、多職種のチームが関与することが一般的です。
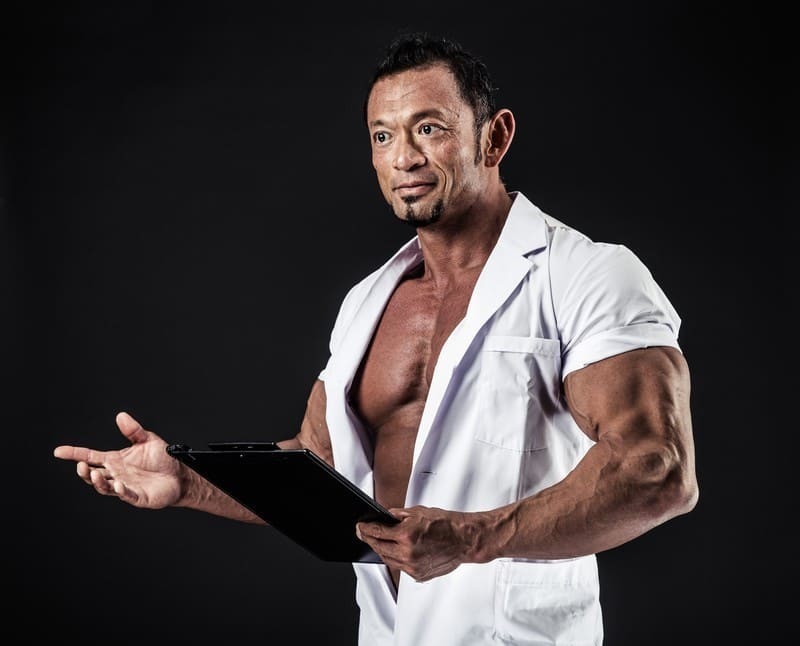
慢性移植片対宿主病の改善方法は、副腎皮質ステロイドを使うことです。他にどのような改善を行うのかについては、症状の程度や現れている症状によって違います。改善を始める時期や改善の強度についても厳密ではありません。
予後不良因子があるかどうかや感染症を発症しているかどうか、病変の進むスピードはどうかなど色々なことを考えた上で改善方法が決められます。
慢性移植片対宿主病は、骨髄や血液幹細胞移植後に生じる可能性のある、非常に厄介な合併症で、改善方法は個人によって異なるため、一概に「これが最良の改善法」と言うわけにはいきません。以下に紹介する改善法は一般的なものであり、個々の症状や体調に応じて医師が適切な改善方法を選定します。
・免疫抑制法
ステロイド: 通常、初めてcGVHDの判断がされた場合、最初の改善方法としてステロイド(例: プレドニゾロン)が用いられます。
効果: 免疫反応を抑制して炎症を減少させます。
副作用: 長期使用による副作用(骨粗鬆症、高血圧、糖尿病等)に注意が必要です。
カルシニューリン阻害剤: タクロリムスやシクロスポリンが使用される場合があります。
効果: T細胞の活性化を抑制し、免疫反応を下げます。
副作用: 腎機能への影響、高血圧、高血糖等があります。
・免疫調整薬
MMF(ミコフェノレート・モフェチル): ステロイドと併用されることが多い。
効果: T細胞とB細胞の増殖を抑制することで、免疫応答を調節します。
副作用: 胃腸障害や骨髄抑制が起こる場合があります。
リトキシマブ: B細胞を標的としたモノクローナル抗体。
効果: B細胞の数を減少させ、その活性を抑えます。
副作用: ウイルス感染のリスクが上がる場合があります。
・症状に対する対処
皮膚症状: ステロイドクリームやタクロリムス軟膏が用いられます。
眼症状: 人工涙液やステロイド点眼液が用いられることがあります。
口腔症状: ステロイドを含む口内洗浄液が推奨される場合があります。
・その他の方法
光線(Photopheresis): 血液成分を分離し、特定の光線で処理した後、体内に戻す方法です。
幹細胞ブースト: 同じドナーからの追加の幹細胞を移植する方法です。
慢性移植片対宿主病の改善方法は、多職種によるアプローチを行うことが大事です。
慢性移植片対宿主病の改善方法には様々な薬物が用いられますが、主には免疫抑制薬が中心となります。以下はその主な薬物についての詳細です。
・ステロイド(例:プレドニゾロン)
対象者: 大多数に対して初めてのラインとして用いられる。
目的: 免疫反応を抑制し、炎症反応を減少させる。
効果: 速やかな症状の改善が見込まれる場合が多い。
副作用: 長期使用による骨粗鬆症、高血圧、糖尿病、感染症のリスク増加など。
・カルシニューリン阻害剤(例:タクロリムス、シクロスポリン)
対象者: ステロイドに反応しない、または副作用でステロイドが使えない場合。
目的: T細胞の活性を抑制し、免疫反応を抑える。
効果: 免疫系の過活動を抑え、cGVHDの症状を緩和。
副作用: 腎障害、高血圧、高血糖、感染症のリスク増加。
・ミコフェノレート・モフェチル(MMF)
対象者: ステロイドと組み合わせて用いられることが多い。
目的: T細胞とB細胞の増殖を抑制。
効果: cGVHDの症状の進行を抑える。
副作用: 胃腸の障害、骨髄抑制、感染症のリスク。
・リトキシマブ
対象者: B細胞が関与すると考えられるcGVHDの症状がある場合。
目的: B細胞の数と活性を抑える。
効果: B細胞関連の症状(例:皮膚症状、口内炎など)の改善。
副作用: 感染症のリスク、血液数値の変動。
・その他の薬物
シクロホスファミド、アザチオプリンなど: これらも免疫抑制薬として用いられる場合がありますが、一般的には他の選択肢が尽きた場合に検討される。
各薬物には多くの副作用や相互作用があり、体調や症状によっては適用できない場合もあります。したがって、改善を行うときは専門の医師による判断と監修のもとで行われるべきです。

慢性移植片対宿主病の改善を行うときには、副作用の対策を行うことが大事です。例えば、定期的に糖尿病になっていないかを確認したり、骨密度の確認をしたりすることが必要です。
感染症を防ぐためには、ST合剤という抗菌薬や、アシクロビルという抗ウイルス薬を内服することが多いです。
おすすめ記事
- 特に対応することが多い症状
- 筋肉、骨のお悩み
- 消化器のお悩み
- 皮膚のお悩み
- 神経のお悩み
- 循環器のお悩み
- 眼のお悩み
- 耳鼻咽喉のお悩み一覧
- 泌尿器のお悩み一覧
- 女性のお悩み一覧
- 脳神経のお悩み一覧
- 子供のお悩み一覧
- がんの種類一覧
- 内分泌のお悩み一覧
- 自律神経のお悩み一覧
- 鍼灸・東洋医学について




