リドル症候群の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2022年 12月 3日
更新日:2025年 8月11日
本日はリドル症候群について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- リドル症候群とは
- リドル症候群の原因
- リドル症候群の改善方法
- リドル症候群の症状
- リドル症候群のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。
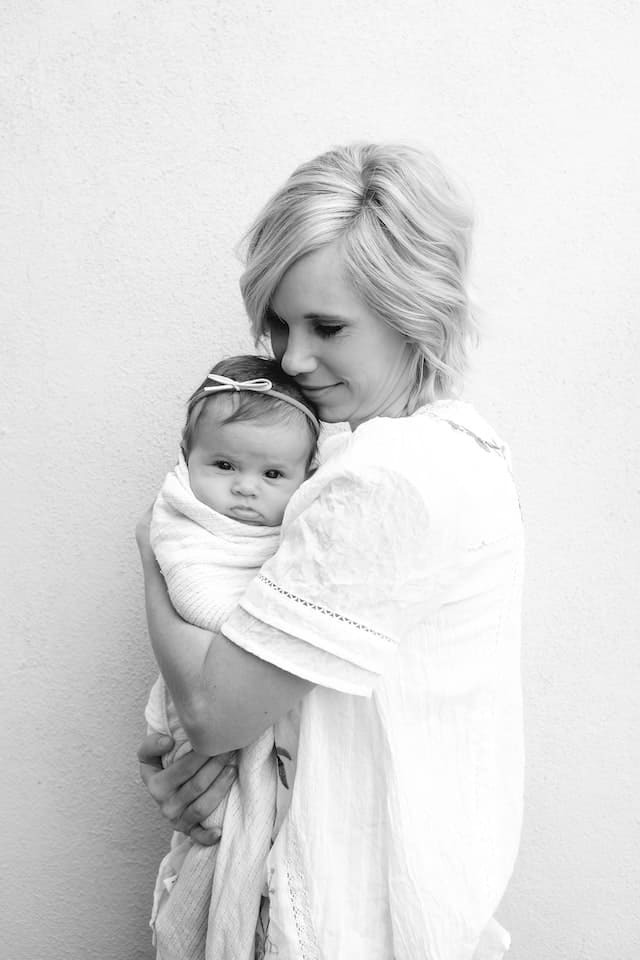
リドル症候群の原因は、遺伝子の異常です。原因となる遺伝子は、腎皮質集合管尿細管の管腔側膜に局在するアミロライド感受性上皮ナトリウムチャンネルの遺伝子であるということがわかっています。
アミロライド感受性上皮ナトリウムチャネルはα、β、γの3つのユニットからできていますが、中でもβもしくはγに遺伝子の異常が起きた時、リドル症候群を発症します。
遺伝の形式は、常染色体優性遺伝です。原因となる遺伝子は上皮型ナトリウムチャネルのサブユニットで、SCNN1B(βサブユニット)で、SCNN1G(γサブユニット)です。
これらの遺伝子の変異によって、ナトリウムチャネルの機能が異常になります。

リドル症候群の改善方法は、トリアムテレンやアミロライドを使うことです。
1日2回、トリアムテレンを100~200mg摂取することと、1日1回アミロライドを5~20mg摂取することが改善に効果を発揮すると言われています。
これは、トリアムテレンやアミロライドナトリウムは、ナトリウムチャネルを遮る作用があるためです。
主な改善方法
・ENaC阻害薬の使用
アミロライドやトリアムテレンは直接ENaCをブロックし、ナトリウム再吸収を防ぐことで、血圧を下げ、低カリウム血症も改善します。
・食事
減塩することで、ナトリウムの負荷を減らし、症状を和らげます。カリウム補給をすることで、低カリウム血症に対処します。
・一般的降圧薬との併用
必要に応じて、ACE阻害薬やARBなどの降圧薬を補助的に使用しますが、根本的な改善はENaC阻害薬で行います。

リドル症候群の症状は、頭痛や嘔吐などの重度の高血圧の症状やしびれや筋力の低下、四肢麻痺、多飲や多尿などの低カリウム血症によって現れる症状などです。
高血圧は10歳代に発症することが多く、低カリウム血症による症状は思春期以降に現れることがほとんどです。
主な改善方法
・高血圧
幼児期から思春期からすでに血圧が高いことが多く、持続的で、しばしば重度の高血圧になります。改善しなければ成人早期に脳卒中や心不全のリスクが高まります。
・低カリウム血症による症状
ナトリウムが体内に過剰に入ると、代わりにカリウムが尿から出ていくため、低カリウム状態になります。筋力低下や筋肉のけいれん、こむら返り、不整脈や倦怠感や集中力低下が見られます。
・代謝性アルカローシスによる症状
カリウムと一緒に水素イオンも失われるため、体がアルカリ性に傾きます。手足のしびれやめまい、吐き気が見られます。重症の場合は意識障害が起こることもあります。

リドル症候群を改善するためには、トリアムテレンとアミロライドを使うことが有効です。薬を使うことと合わせて食塩の制限をきちんと行うことも非常に重要です。
〈具体的に塩分を制限する方法〉
- 醤油、味噌、ソースは「かける」より「少量をつける」
- 減塩タイプの調味料に切り替える
- 出汁や酢、香辛料で味を補う
- ハム、ソーセージ、ベーコン、漬物、インスタント麺は控える
- コンビニ弁当や惣菜も気を付ける
- ラーメンやスープ類は汁を残す
- ドレッシングは別添にしてかけすぎない
- 野菜や果物をしっかり摂る
- 魚や肉は「味付け加工品」より「生鮮品」を選んで自宅で調理する




