| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 ~ 21時 | 副院長 | そうぜん | そうぜん | 副院長 | そうぜん | そうぜん | 副院長 |
ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2022年 7月 3日
更新日:2025年 9月 5日
本日はゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病とは
- ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病の原因
- ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病の症状
- ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病の改善方法
- ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。
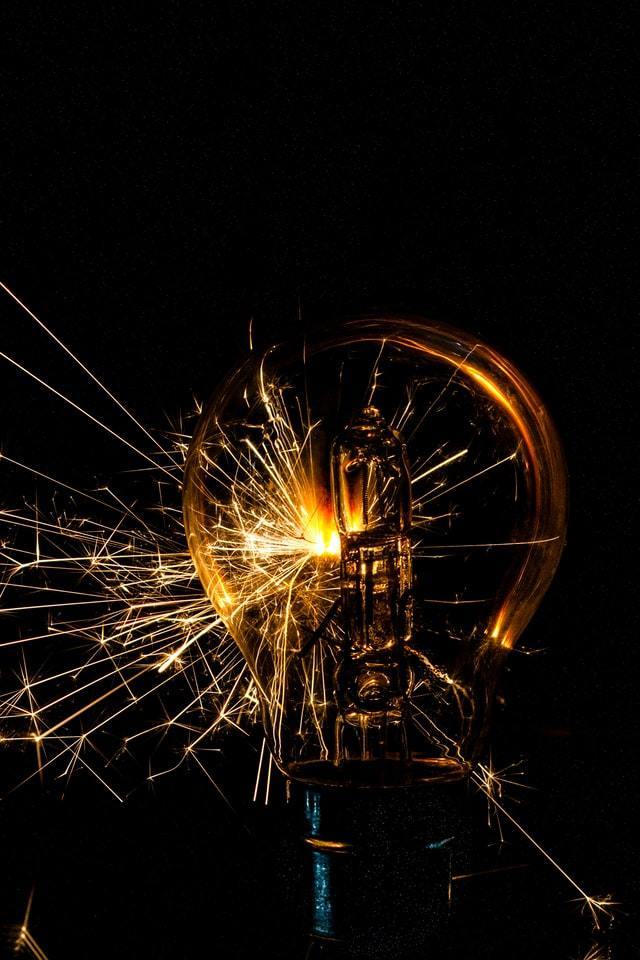
ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病の原因はプリオン蛋白遺伝子に変異があることです。ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病を発症している人の脳には異常なプリオン蛋白が多くあることがわかっているのです。
しかし、異常なプリオン蛋白によってなぜ脳に障害が起きるのかということについては詳しくはわかっていません。
ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病を発症した人の中に同じ病気を発症している人もいますが発症していない人もいます。遺伝子による発症についても今のところわかっていないのです。
主な原因はプリオン蛋白の異常です。私たちの体には プリオン蛋白という正常なタンパク質があります。GSSでは、このPrPをつくる遺伝子に変異が生じています。遺伝子の変化により、正常のPrPが異常に折りたたまれた構造に変化しやすくなります。
一度異常型プリオンができると、正常のPrPを次々と異常型に変えてしまいます。この連鎖反応により異常プリオンが脳内でどんどん蓄積し、神経細胞が障害を受けます。結果として、神経の脱落や海綿状変化が進みます。
遺伝形式は常染色体優性遺伝です。変異を持つ親から子へ50%の確率で受け継がれるため家族歴を持つケースが多いのが特徴です。
クロイツフェルト・ヤコブ病もプリオン病ですが、GSSはCJDよりもゆるやかに進行する傾向があります。主に小脳失調で始まることが多く、認知症症状は後期に出ることが多いです。

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病の症状は、ふらつきやめまい、認知症などです。
ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病はプリオン病のひとつです。プリオン病とは、異常なプリオンたんぱくが脳に蓄積することで脳神経細胞が障害され、行動異常や認知症などの症状が現れる疾患群のことです。
発症の最初期には、小脳や末梢神経の障害を示す症状が現れます。初期症状は、小脳失調、言葉のもつれや筋肉のこわばりや震え、手足のしびれや感覚異常などで、これらの症状は徐々に悪化していきます。
病気が進行すると、運動や認知の機能にさらに広がりを見せます。歩行障害の進行や筋力低下、感覚障害、視覚障害や難聴が起こることもあります。
さらに進行すると、中枢神経全体に影響が及び、生活に大きな支障をきたします。認知症症状や言語障害、けいれん発作や嚥下障害が起こります。寝たきり状態になり、最終的には呼吸筋や嚥下機能の低下によって、合併症が命に関わることが多いです。
症状の特徴
- 小脳失調が初期に目立ち、バランスや歩行障害が最初に現れる
- 認知症は後期に出ることが多い
- 進行はゆっくりで平均5〜10年かけて進行する
- 遺伝性で家族内で似た症状が見られることもある

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病の改善方法は、今のところありません。
ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病を発症すると、2~10年で全身が衰弱したり肺炎を起こしたりして命に関わります。
病気の進行は止められなくても、症状による負担を減らすことはできます。
運動症状への対応としては、リハビリテーションや補助具の使用を行います。けいれん発作は抗けいれん薬でコントロールし、筋肉のこわばりには筋弛緩薬を使用します。嚥下障害には専門家の指導や、食事形態の工夫、認知症症状には精神症状への薬を使用します。

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病を発症しても、日常生活を送る上で特別に注意することはありません。
しかし、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病に他の人が感染することを防ぐため、献血をすることはできません。
病院に行くときもゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病を発症していることをきちんと医師に伝える必要があります。
おすすめ記事
- 特に対応することが多い症状
- 筋肉、骨のお悩み
- 消化器のお悩み
- 皮膚のお悩み
- 神経のお悩み
- 循環器のお悩み
- 眼のお悩み
- 耳鼻咽喉のお悩み一覧
- 泌尿器のお悩み一覧
- 女性のお悩み一覧
- 脳神経のお悩み一覧
- 子供のお悩み一覧
- がんの種類一覧
- 内分泌のお悩み一覧
- 自律神経のお悩み一覧
- 鍼灸・東洋医学について




