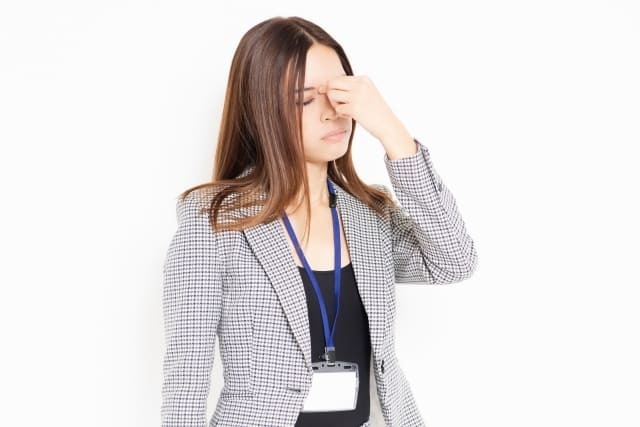統合失調症の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2019年 12月23日
更新日:2021年 5月 15日
本日は統合失調症について解説させていただきます。
統合失調症は、こころや考えがまとまりづらくなってしまう、およそ100人に1人弱がかかる比較的頻度の高い病気です。幻覚や妄想という症状が特徴的な精神的な病気で家庭や社会で人と関わりながら生活を営むことが困難になります。
思春期から40歳くらいまでに発病しやすい病気です。
他の多くの精神疾患と同様、慢性の経過をたどりやすく、幻覚や妄想が強くなる傾向にあります。
「感覚・思考・行動が病気のために歪んでいる」ことを自分で振り返って考えることが難しくなりやすいという特徴を持っています。
統合失調症の症状は大きく「陽性症状」「陰性症状」「認知機能障害」の3つに分けることができます。
- あるはずないものが見え、聞こえるはずのない声が聞こえる陽性症状
陽性症状の特徴は、「妄想」「幻覚」「思考症状」です。なかでももっとも多くみられるのが、実在しない人の声が聞こえる幻聴でその声は、自分に対する悪口や噂であったり、何かの命令であったりします。その他、見えないものが見える、普通なら感じないような身体の症状を感じる体感幻覚、幻嗅、幻味などが起こることもあります。
- 感情表現が乏しくなり意欲が低下する陰性症状
喜怒哀楽の表現が乏しくなり、他者の感情表現に共感しにくくなります。話の理解できなかったり、会話が成り立たなくなります。自発的に何かを行おうとする意欲もなくなってしまい、いったん始めた行動も続けるのが困難になってきます。これらが慢性的に続き、自分の殻に閉じこもり、他者とのコミュニケーションをとらなくなります。
- 生活に困難をきたす認知機能障害
認知機能とは、記憶、思考、理解、計算、学習、言語、判断などの知的な能力を指しますが、統合失調症の場合はこれらの機能障害がみられ、生活や社会活動が困難になります。物事を覚えるのに非常に時間がかかるようになり、目の前の仕事や勉強に集中したり、考えをまとめたりすることができなくなります。また、判断力も低下し優先順位をつけてやるべきことを判断したり、計画を立てたりすることができなくなります。
・妄想
被害妄想:他人が自分を害しようとしているという考え。
誇大妄想:自分が特別な力や使命を持っていると信じる。
関係妄想:無関係な出来事が自分に関連していると考える。
・幻覚
聴覚幻覚:他人の声が聞こえる、命令される。
視覚幻覚:実際には存在しないものが見える。
触覚幻覚:何かに触られている感覚がする。
・思考の混乱
話の一貫性の欠如:話が飛び飛びになる、脈絡がなくなる。
急速な思考の変化:次々と考えが浮かび、集中できない。
・感情の平板化
無表情:顔の表情が乏しい。
感情の欠如:喜怒哀楽の反応が薄い。
・意欲の低下
無気力:何もする気が起きない。
社会的引きこもり:人との交流を避ける。
・思考や行動の貧困
会話の減少:話すことが少なくなる。
興味の喪失:趣味や興味を持たなくなる。
・記憶障害
短期記憶の低下:最近の出来事を覚えていない。
学習能力の低下:新しい情報を学ぶのが難しい。
・注意力の低下
集中力の欠如:一つのことに集中できない。
作業の中断:途中で作業を投げ出してしまう。
・抑うつ
悲しみや絶望感:持続的な悲しみや無力感。
興味の喪失:日常の活動に対する興味や喜びの欠如。
・双極性症状
躁状態:異常なほど活発でエネルギッシュになる。
抑うつ状態:気分が極端に沈む。
統合失調症の原因はまだはっきりとわかっていませんが、脳内で情報を伝える神経伝達物質のバランスがくずれることが関係しているのではないかといわれています。また、大きなストレスがかかることなども関係あるようです。
いくつかの統合失調症の脳について調べた研究で、脳の萎縮が確認されたこと、前頭葉や側頭葉という脳の部位が比較的小さいこと、海馬や扁桃体という記憶や五感情報に関与する部位がとくに左側で小さいこと、脳の前側、思考やアイデア、感情をコントロールする部位‘‘前頭葉‘‘の機能低下が報告されています。
しかし、これらが発症にどのように関与しているのかについてはまだわかっていません。原因は1つではなく、さまざまな原因が複雑にからみ合って発症すると考えられています。
考えられる要因1
お腹の中にいるときのウイルス感染や栄養不良、そして出生時の無酸素状態などで脳の機能的な障害が生じたのではないかと考えられています。
成長期の神経系の発達や成熟に影響を与えてしまい発症に至るとの一説もありますが、これら妊娠期の障害があったからといって発症するわけではなく、危険因子の1つにすぎません。
考えられる要因2
一定の性格傾向があることが知られています。静かでおとなしく、控えめな性格、神経質かと思えば全く無頓着であったり、ふとした事で傷つきやすいなどの気質の人がなりやすい傾向にあります。
また、人と交わるのが苦手で、一人でいることを好む傾向もしばしば見られます。すべての人に当てはまるわけではありませんが、発症と何らかの影響があるのではないかと思われています。
考えられる要因2
一定の性格傾向があることが知られています。静かでおとなしく、控えめな性格、神経質かと思えば全く無頓着であったり、ふとした事で傷つきやすいなどの気質の人がなりやすい傾向にあります。
また、人と交わるのが苦手で、一人でいることを好む傾向もしばしば見られます。すべての人に当てはまるわけではありませんが、発症と何らかの影響があるのではないかと思われています。
・家族歴と遺伝
家族歴:統合失調症の家族歴がある人は、発症リスクが高まります。親や兄弟姉妹に統合失調症を発症している人がいる場合、その発症リスクは一般の人よりも高くなります。
双生児研究:一卵性双生児の一方が統合失調症である場合、もう一方が統合失調症を発症する確率は約50%です。二卵性双生児の場合は約15%とされています。このことから、遺伝的要因が統合失調症の発症に大きく寄与していることが示されています。
・遺伝子研究
候補遺伝子:統合失調症に関連する特定の遺伝子がいくつか特定されています。これらの遺伝子は、神経伝達物質の調節やシナプス機能に関与しています。
多遺伝子モデル:統合失調症の発症には、単一の遺伝子ではなく、複数の遺伝子が関与していると考えられています。これにより、遺伝的要因と環境要因の相互作用が重要となります。
・ドーパミン仮説
ドーパミン過活動:統合失調症の脳内では、ドーパミンが過剰に活性化しているとされ、これが幻覚や妄想に関連しています。ドーパミンD2受容体の異常が特に重要とされています。
ドーパミン過活動の根拠:抗精神病薬はドーパミン受容体をブロックすることで効果を示し、これがドーパミン過活動仮説を支持しています。
・その他の神経伝達物質
グルタミン酸:グルタミン酸のシステムも統合失調症に関与しているとされています。グルタミン酸NMDA受容体の機能低下が陰性症状や認知機能障害に関連していると考えられています。
セロトニン:セロトニンも統合失調症の病態に関与している可能性があり、特に新しい抗精神病薬の一部はセロトニン受容体をターゲットにしています。
・出生前および出生時の要因
妊娠中の感染:母親が妊娠中に感染症にかかると、胎児の脳発達に影響を与える可能性があります。例えば、インフルエンザやトキソプラズマ症などです。
栄養不足:妊娠中の栄養不足も、胎児の脳発達に悪影響を与えることが知られています。
・生活環境とストレス
都市部での生活:都市部に住むことが統合失調症の発症リスクを高めるとされています。これは、都市生活に伴うストレスや社会的孤立が影響している可能性があります。
ストレス:強いストレスやトラウマが統合失調症の発症を引き起こす引き金になることがあります。
・神経発達の異常
神経発達仮説:統合失調症は、胎児期から思春期にかけての脳発達過程での異常によって引き起こされるという仮説です。これには、神経細胞の移動、シナプス形成、神経回路の構築などが含まれます。
・脳構造の異常
脳画像研究:統合失調症の脳画像研究において、脳の構造的異常が観察されています。具体的には、前頭葉や側頭葉、海馬などの特定の脳領域の体積減少が報告されています。

統合失調症は抗精神病薬による薬での改善が欠かせません。特に急性期には薬の使用が中心になります。
しかしそれだけでは幻覚や妄想などの症状が完全には消えなかったり、病気による生活のしづらさが残ったりします。
薬と精神科リハビリテーションの併用が重要になってきます。
統合失調症は慢性疾患ですので、長期にわたって、医師-本人-家族の連携が必要になってきます。気になることがあればなんでも伝え合うことが大切です。
統合失調症の薬
中心となる薬は「抗精神病薬」です。脳内で過剰に活動しているドーパミン神経の活動を抑えることで症状を改善する作用があります。
抗精神病薬は、定型抗精神病薬と非定型抗精神病薬とに分けられます。
- 定型抗精神病薬
陽性症状に効果があり、幻覚・妄想や考えをまとめられないといった症状を緩和します。
【副作用】定型抗精神病薬は副作用として、手がふるえる、体が硬くなるなど、パーキンソン病様の症状と似ている錐体外路障害が起きることがあります。また、プロラクチンが上昇するので女性の場合、生理が止まる、乳房がはる、乳汁分泌が見られ、男性の場合は性欲減退が見られます。
のどの渇き、便秘、排尿障害、記憶障害などが起こるもの特徴です。
- 非定型抗精神病薬
陽性症状にも効果的ですが、陰性症状や認知機能障害に対する効果も期待できます。錐体外路症状の副作用が少なく、陰性症状に対しての効果は、定型抗精神薬より期待できます。
鍼灸は施術を受ける個人に対する副作用が非常に少ないことが認められております。
統合失調症に対する鍼灸の効果について、いくつかの主要なポイントを説明します。
1. 精神的な安定
鍼灸は、リラクゼーション効果が高く、ストレスを軽減するのに役立ちます。これにより、統合失調症の症状である不安や緊張が緩和されることがあります。具体的には、以下のような効果が期待されます。
不安の軽減:経穴を刺激することで、副交感神経が活性化され、不安感が和らぎます。
ストレスの低減:鍼灸でのリラクゼーションにより、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が減少します。
2. 気分の改善
鍼灸は、神経伝達物質のバランスを調整することにより、気分を改善する効果があります。例えば、セロトニンやドーパミンの分泌が調整され、気分の安定が図られます。
セロトニンの増加:鍼灸による刺激が、セロトニンの分泌を促進し、気分を高める効果があるとされています。
ドーパミンの調整:統合失調症に関連するドーパミンの不均衡を整えることができます。
3. 身体的な健康の向上
統合失調症は、精神的な症状だけでなく、身体的な不調も伴うことがあります。鍼灸は、全身の健康を改善し、身体的な症状を和らげるのに役立ちます。
不眠の改善:鍼灸は睡眠の質を向上させる効果があります。特定の経穴を刺激することで、リラックス効果が得られ、睡眠障害が改善されます。
消化機能の向上:鍼灸は消化機能を調整し、食欲不振や胃腸の不調を改善するのに役立ちます。
4. ホルモンバランスの調整
鍼灸は、ホルモンバランスを調整する効果があります。これにより、統合失調症の症状を緩和することが期待されます。
ホルモン分泌の調整:鍼灸は、内分泌系に働きかけ、ストレスホルモンや性ホルモンの分泌を調整します。
1. 薬
・抗精神病薬
第一世代抗精神病薬(定型抗精神病薬):クロルプロマジンやハロペリドールなどが含まれます。これらの薬は、主にドーパミンD2受容体をブロックすることで陽性症状を抑えますが、錐体外路症状などの副作用があることがあります。
第二世代抗精神病薬(非定型抗精神病薬):リスペリドン、オランザピン、クエチアピン、アリピプラゾールなどが含まれます。これらの薬は、ドーパミン受容体だけでなく、セロトニン受容体もブロックすることで、陽性症状と陰性症状の両方を改善することができます。副作用として体重増加や代謝異常がありますが、錐体外路症状は少ないです。
・薬の管理
投薬の継続:医師の指示に従い、定期的に薬を服用することが重要です。薬を中断すると再発のリスクが高まります。
副作用の管理:副作用が現れた場合は、医師に相談し、適切な対処法を見つけることが大切です。
2. 心理社会的改善
・認知行動療法(CBT)
症状管理:自分の思考パターンを理解し、症状に対処するための具体的なスキルを学ぶのに役立ちます。
再発予防:ストレスやトリガーを特定し、それに対処する方法を学ぶことで、再発を予防することができます。
・家族のサポート
家族のサポート:家族が統合失調症について理解し、適切なサポートを提供できるようにするための方法です。
コミュニケーションの改善:家族間のコミュニケーションを改善し、安心して生活できる環境を作ることが目的です。
・社会技能訓練(SST)
社会的スキルの向上:効果的に社会生活を送るために必要なスキルを学ぶことができます。これには、対人関係のスキルや問題解決のスキルが含まれます。
自立支援:就労支援や日常生活のサポートを通じて、自立を促進します。
3. 生活習慣の改善
・規則正しい生活
睡眠の確保:十分な睡眠をとることは、精神的な健康を保つために非常に重要です。
バランスの取れた食事:栄養バランスの取れた食事を摂ることで、全体的な健康状態を改善できます。
・運動
定期的な運動:運動はストレスを軽減し、気分を改善するのに役立ちます。散歩やヨガ、軽いジョギングなど、無理のない範囲での運動が推奨されます。
・ストレス管理
リラクゼーション法:瞑想、深呼吸、マインドフルネスなどのリラクゼーション法を取り入れることで、ストレスを軽減し、症状の管理に役立てます。
趣味や活動:趣味や楽しい活動に参加することで、気分を改善し、社会的つながりを維持することができます。
4. 定期的なフォローアップ
医師との定期的な面談:定期的な診察を受けることで、改善の効果を評価し、必要に応じて計画を調整することができます。
症状の早期発見:症状が悪化する前に早期に介入することで、再発を防ぐことができます。