ライ症候群の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2022年 11月23日
更新日:2025年 4月14日
本日はライ症候群について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- ライ症候群とは
- ライ症候群の原因
- ライ症候群の症状
- ライ症候群の改善方法
- ライ症候群のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

ライ症候群の発症は、ウイルス性の病気に続いて起こります。先行するウイルス性の病気の代表的なものは、インフルエンザや水疱瘡です。
しかし、なぜウイルス性の病気に感染した後にライ症候群を発症するのかということについては明らかになっていません。
ライ症候群の発症には、いくつかのリスク因子との関係が考えられており、代表的なものにインフルエンザや水疱瘡などを発症した時に内服する解熱鎮痛剤の一部が言われています。
ただし、全ての人が解熱鎮痛剤を内服することでライ症候群を発症するわけではありません。そのため、個人が発症のリスク因子を持っているとも言われています。
リスク因子のひとつは、脂肪酸の代謝に関わる先天的な代謝の異常です。普段は特に症状がなくてもインフルエンザなどのウイルス性の病気にかかった時、症状が現れることがあります。
脂肪酸の代謝に関わる代謝異常があり、ウイルス性の病気にかかっているときに一部の解熱鎮痛剤を内服するという幾つかの要因が重なることでライ症候群の発症につながることがあると考えられています。
主な原因
①:ウイルス感染との関連
インフルエンザA型、B型、水痘(VZV)、RSウイルス、コクサッキーウイルスなどのウイルス感染の回復期にライ症候群が発症するケースが多いです。感染時に肝臓やミトコンドリアに負担がかかると、アンモニアや乳酸などの有害物質の代謝が滞り、結果として高アンモニア血症や脳浮腫を引き起こすリスクが高まります。
②:アスピリン(サリチル酸系)の使用
アスピリンは、ライ症候群との関連で最も有名な因子でウイルス感染時に解熱剤として使われていましたが小児がインフルエンザや水痘を発症している時にアスピリンを使用すると、ミトコンドリアの機能障害が引き起こされ、脂肪肝や脳障害のリスクが大幅に上がります。そのため現在は、小児にはアスピリンを原則使用しないというガイドラインが世界的に採用されています。
③:ミトコンドリア機能障害(代謝異常)
ライ症候群は、本来は遺伝的な代謝異常の表現型のひとつとも考えられており、特に以下の代謝経路の異常が関与しているとされています。脂肪酸β酸化異常症、ミトコンドリアDNA異常、尿素回路異常などの代謝異常を持つ小児は、ウイルス感染やアスピリン使用といった外的ストレスによってミトコンドリア機能が破綻しやすく、ライ症候群を発症するリスクが高まります。

ライ症候群の初期症状は、乳児の場合下痢や多呼吸、年長児の場合吐き気や頻回の嘔吐です。
症状が進むと、中枢神経障害に関係して、完全に眠ってなくてもうとうとした状態になったり少しのことですぐに不機嫌になったり、異常興奮が見られたり、手足の麻痺やけいれんが現れたりします。
さらに病状が進むと、意識消失から呼吸停止に至ります。
主な症状
①中枢神経症状(脳浮腫による)
最も重篤で、生命に関わるのがこちらの症状です。初期には、持続的な嘔吐、強い眠気、無気力、行動の変化が起こります。中期には、意識混濁、反応が鈍くなる、錯乱、せん妄状態、異常な発言、意味不明な行動がみられ、進行時には、昏睡、けいれん発作、呼吸異常が起こります。
②肝障害(脂肪変性による)
もう一つの特徴が肝臓の機能障害で、外見上は症状が目立ちにくいものの、血液で明らかになります。黄疸は出ないのに、AST、ALTは高度に上昇します。高アンモニア血症や低血糖が見られます。
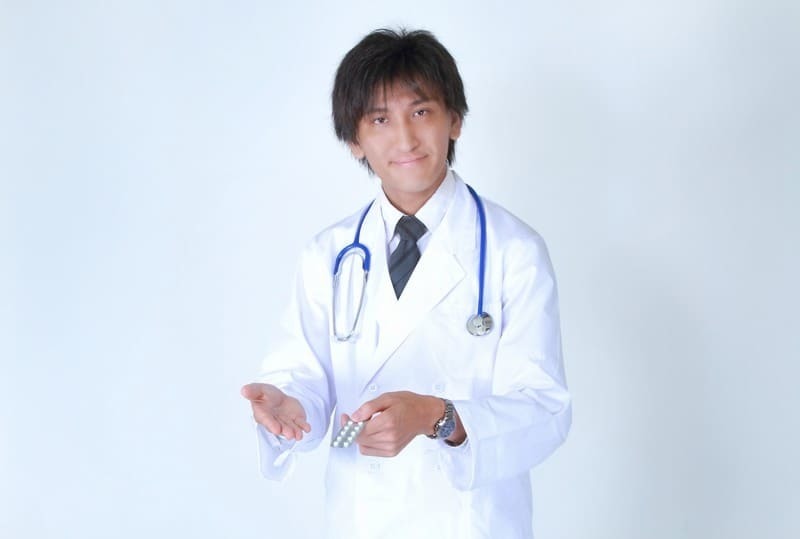
ライ症候群の改善の中心は急性脳症と肝機能障害に対して行います。
急性脳症に対しては、脳の腫れを改善させるために、挿管管理の上呼吸回数を増やしたり水分制限を行ったり、浸透圧利尿剤を投与したりして改善に取り組みます。
肝機能障害に対しては、ビタミンKの投与や新鮮凍結血漿輸血などを行うことで出血傾向の改善に取り組みます。
主な改善方法
①:脳浮腫のコントロール
ライ症候群で最も致命的なのは脳浮腫による脳ヘルニアです。以下のような対策で脳圧を下げることが最優先です。
・浸透圧利尿薬の使用→マンニトールや高張NaCl液を点滴して脳圧を下げる
・頭部の位置調整→頭をやや高くして静脈還流を改善(頭部30度挙上)
・人工呼吸管理→CO₂濃度を下げることで頭蓋内血管を収縮させ、脳圧を下げる
・抗けいれん薬の投与→けいれんによる酸素消費と脳圧上昇を抑える
②:肝機能のサポート
ライ症候群では肝臓の脂肪変性が起こり、アンモニアや毒素が体内にたまるため、それを下げる方法が重要です。
・高アンモニア血症への対処→アンモニアを下げるためにラクツロース、アルギニン、ナトリウムベンゾ酸などを使用
・血糖管理→低血糖を防ぐためにグルコース点滴を行う
・出血傾向の管理→肝機能障害に伴う凝固不全にはビタミンKや新鮮凍結血漿を投与する
③:代謝の安定化と全身管理
・酸塩基バランス→血液pHの調整する
・体温管理→解熱剤はアスピリン以外を使用する
・水分・電解質の調整→点滴による水分・ナトリウムの厳密な管理を行う

ライ症候群は予防が非常に重要です。子供の発症を回避するためにはライ症候群と強く関係していると考えられている一部の解熱鎮痛剤を避けることが大事になります。
インフルエンザや水疱瘡などで病院の小児科などに行った場合はライ症候群を引き起こすリスクがないとされている薬が処方されています。
自己判断で家にある解熱鎮痛剤を使うのではなく医師の指示のもとで使うことがライ症候群の予防につながります。
ライ症候群の予防には、アスピリンの使用を避けることが最も重要です。アスピリン(サリチル酸系薬)は、ミトコンドリア機能を阻害し、肝臓や脳の代謝に悪影響を与える可能性があります。特にウイルス感染時の小児に使用すると、ライ症候群を引き起こすリスクが高くなります。
小児に解熱剤を使う場合は、タイレノールなどのアセトアミノフェンを選びましょう。市販薬を使うときはアスピリンが含まれていないか確認しましょう。
商品名に「バファリン」「ケロリン」「エキセドリン」などがある場合、注意が必要です。
おすすめ記事
- 特に対応することが多い症状
- 筋肉、骨のお悩み
- 消化器のお悩み
- 皮膚のお悩み
- 神経のお悩み
- 循環器のお悩み
- 眼のお悩み
- 耳鼻咽喉のお悩み一覧
- 泌尿器のお悩み一覧
- 女性のお悩み一覧
- 脳神経のお悩み一覧
- 子供のお悩み一覧
- がんの種類一覧
- 内分泌のお悩み一覧
- 自律神経のお悩み一覧
- 鍼灸・東洋医学について




