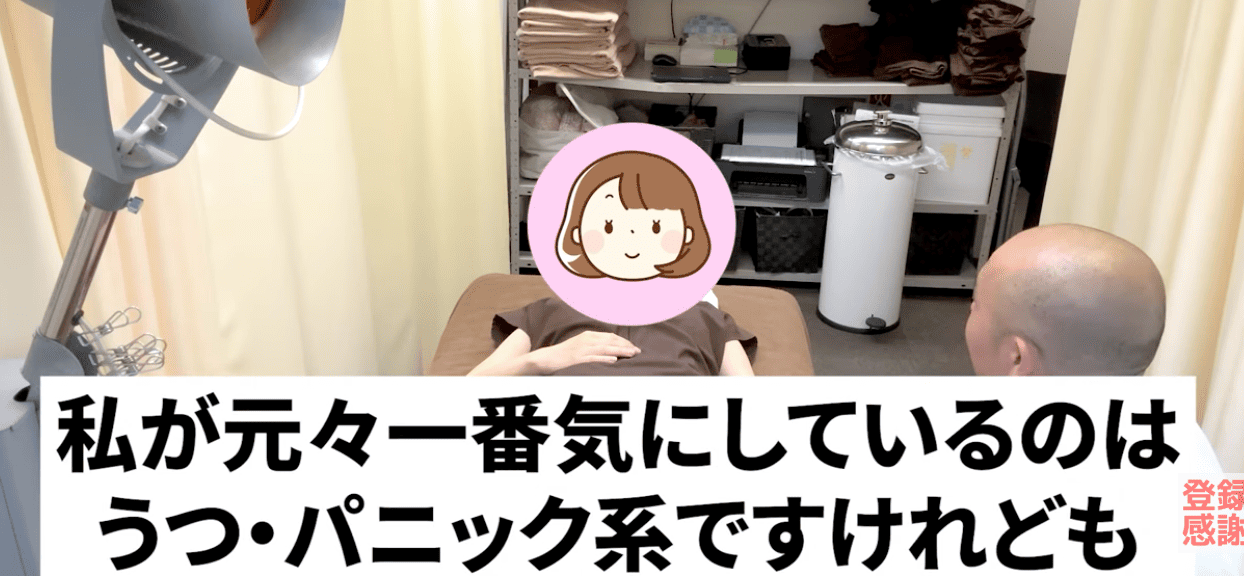パニック障害の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2019年 12月23日
更新日:2024年 10月15日
本日はパニック障害について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- パニック障害とは
- パニック障害の原因と症状
- パニック障害の改善方法
- パニック障害の予防とまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。
パニック障害で起こる発作は非常に強く、死への危険を察知して警告を発信し生き延びるための反応で起こると言われています。
心筋梗塞の症状に似ているため、激しい苦しさで死んでしまうのではないかと感じてしまいます。しかし、救急車を呼んで病院へ運ばれても内科系で体に異常はなく、場所を移動し時間がたつと症状も嘘のように消えます。
災害や敵など命の危機に直面した時、脈が早くなり汗をかいたり、恐怖で血の気がひき手足が震えたり、大声で叫び逃げだしたくなったりといったパニック状態に陥ります。
特に、電車やエレベーターの中などといった狭く閉じられた空間でよく発作が起こります。そのため外出が困難になり、仕事が出来なくなってしまうケースも見られます。
パニック障害は発作から始まります。はじめは発作だけですが、くりかえすうちに、発作のない時に予期不安や広場恐怖といった症状が現れるようになります。うつ症状をともなうこともあります。

本来パニック状態は災害や敵など命の危機に直面した時に起こります。
命の危険から逃れるために有利な反応で、本来人間に備わった正常プログラムです。しかし何らかの理由によりそのプログラムが誤作動を起こして反応することをパニック発作といいます。
心理的な要因が多くかかわっていると思われていますが、脳神経機能の異常の可能性もあります。現在、パニック障害になる割合は100人のうち1~2人と多く、男性より女性の方が発症率は高いです。
過労、睡眠不足、ストレス、風邪など環境や心身の不調がパニック障害を引き起こす要因としてあげられ、家族歴があると発症リスクが高まるとも知られています。
パニック障害の発作で死ぬことはありません。狭く閉じ込められた空間で起こることが多いですが、人によってはなんでもない時にパニック状態のような反応が起きることがあります。
何もきっかけがない時にこうした症状が起きると、人は皆、心臓や胃や気管支などの病気を考えます。そのため始めは、循環器や呼吸器や消化器に行くことが多いです。
しかし、どんなに調べても異常が見られないので、周囲からは理解されにくく、処置しにくい病気でもあります。
パニック障害になりやすい人はもともと不安や恐怖心が強いタイプで、幼いころから内気で人見知りが強い方に多いです。また、高い所や閉い所、犬や猫などの動物が怖いなど言う人は、なりやすい性質を持っているといえます。
しかし、大人になってからの過度なストレスや疲労がピークに達し、本来は楽天的な性格の方でも神経質で繊細になってしまい病気が起こるケースもあります。
パニック障害の原因
・遺伝的要因
パニック障害の発症には、遺伝的な影響が大きいとされています。家族や親族にパニック障害を持つ人がいる場合、発症リスクが高まることが確認されています。最近の研究では、特定の遺伝子がパニック障害に関与している可能性があると言われています。
・脳の機能異常
パニック障害の発症には、脳内の神経伝達物質のバランスが乱れることが関係しています。セロトニンは感情の安定に、ノルアドレナリンはストレス反応に、GABAは脳の興奮を抑制する役割を持ち、これらの物質が不均衡になるとパニック発作を引き起こすと考えられています。
扁桃体は不安や恐怖の処理を行う脳の部位です。パニック障害では、扁桃体が過剰に活性化している場合が多いとされています。また、前頭前皮質との連携が不十分であると、恐怖の反応が抑えられなくなりパニック発作につながることがあります。
・心理的要因
高いストレス状態が続いたり、過去に強い恐怖や不安を感じる経験があると、パニック障害の発症リスクが高まります。常に不安を抱えやすい性格や、自己否定的な考え方を持っている人、完璧主義な人は、パニック障害を発症しやすい傾向があります。
・環境要因
過度なストレスを抱える仕事や、過密なスケジュール、家族内の問題など、生活環境によるストレスが蓄積されると、パニック障害のリスクが高まることがあります。また、アルコールやカフェインの摂取、甲状腺機能の異常、低血糖などの身体的な要因によっても引き起こされることがあります。
・身体的な反応に対する過敏さ
パニック障害の人は、自分の体内での微小な変化に対して過敏になることが多いです。また、一度パニック発作を経験すると、再び発作が起きるのではないかという恐怖感が強まり、心身に対する過剰な注意が常に続きます。
・学習理論と行動パターン
行動心理学の観点からは、パニック発作が一度起きると、その状況や場所が危険として学習されることが多く、その状況を避ける回避行動が強まります。この回避行動が、パニック障害を悪化させる原因の一つとされています。
パニック障害を発症しやすい人
・不安感が強い人
・完璧主義な性格の人
・過去にトラウマやストレスの経験がある人
・敏感で内向的な性格
・ストレスが多い環境にいる人
・家族にパニック障害の人がいる場合
・身体感覚に敏感な人
・心配性で危機回避を重視する傾向がある人

パニック障害の改善には、薬と精神的アプローチが用いられます。一般によく使われる薬はSSRIをはじめとし抗うつ薬と抗不安薬の一種であるベンゾジアゼピン系薬剤です。
SSRIは、神経伝達物質のひとつであるセロトニン(感情や気分のコントロール、精神の安定に深く関わっている)輸送体の作用を遮断することにより、セロトニンの再取り込み阻害剤として作用する薬の一種です。セロトニンの細胞外濃度が増加し、セロトニン作動性神経伝達が増加します。
薬を使うことや改善方法全般に少しでも不安や疑問がある場合、遠慮せずに相談しながら進めましょう。不安を残したまま進めると、改善が遅くなってしまいます。
薬が効き始めて発作が起こらなくなってきたら、徐々に苦手だった外出に挑戦することも改善の一環になります。
認知行動法が、薬と同じくらいパニック障害に効果があることが認められています。
パニック障害の改善方法
・薬
抗不安薬は、短期間で不安を和らげ、急なパニック発作を抑えるために使用されることがあります。
抗うつ薬は、長期的に不安やパニック症状を改善するために使用されます。
βブロッカーは、心拍数の上昇や手の震えなど、パニック発作による身体症状を抑えるために使用されることがあります。
・認知行動療法
不安を引き起こす考え方や思考のクセを変える改善方法でパニック発作を経験したときの思考や、発作が再発するのではないかという恐怖心に対する反応を見直します。発作が起こるかもしれないと不安を感じる状況に徐々に慣れることも改善方法の1つです。慣れによって恐怖を減らしていきます。
・ライフスタイルの改善
睡眠不足は不安を高める要因のひとつです。規則正しい生活リズムを整え、質の良い睡眠をとることで、精神的な安定を目指します。栄養バランスを保った食事、定期的な運動もストレス軽減のために必要です。
・呼吸法とリラクゼーション法
深呼吸をしたり、瞑想やマインドフルネスを用いたり、特定の筋肉を意識的に緩めるリラクゼーション法を行ったりします。

東洋医学の基本原則に「五行」とゆうものがありますが、恐れや驚きの感情を司るのは五臓の「腎」と考えられています。
人が先天的にもつ腎のエネルギーが不足していたり、積み重なるストレスや緊張により「腎気」が弱くなってしまうと、怖くもないのに恐れる、驚いてしまう、焦る、不安になるなどどいった現象が起こります。
腎気が弱くなると連動し、他の臓器の誤作動も生じます。恐れや驚きの感情は「腎」が司るのに対し、喜びは「心」、怒りは「肝」が司りますが、一つでも大きくバランスが崩れることにより、コントロールが効かなくなってしまいます。
コントロール不全により不眠、冷えまたはのぼせ、あるいは両方、浅い呼吸、不安神経症状、頚肩背中の激しい筋緊張などが現れます。
当院では、これらのバランスを根本から改善し、再発させない身体作りを目的としています。
【脳過敏症候群のTさん2回目の施術】
1番気にしているのは鬱やパニックですが、現在地下鉄でなんの抵抗もなく当院までいらっしゃることができていると言われています。
現在サインは2つで右首と左肩です。当院では鬱とパニックは脳過敏からくる症状として施術を行っていますが、症状が良くなったと言って改善している人は一人もいません。みんなだんだん忘れて不安感などがだんだんなくなってくるのです。
ただし、体が安定するのに若干タイムラグがあるため施術後すぐに感じることは難しいです。
Tさんの1番の悩みであるうつ症状は本質的なうつ病ではなく、体や首が問題でパニックにさせられているだけです。安定すれば一時的に落ちたとしても上がってくることができます。
うつ病の種類もたくさんあります。最近はヘルペスウイルスが増殖し脳に刺激を与えてうつ病になることも多いことがわかっています。唾液の中のヘルペスウイルスの量を調べるとうつ病の人のヘルペスウイルスの量が異常に多く、免疫反応が弱くなるとそのような症状が出ます。
さらに脳腸相関といい人間は幸せだと感じるホルモンの90%は腸で作られるためそれが作られにくくなり鬱々としてしまうことも多いです。当院では性格や疲労、社会背景などは一切信用しません。体が良くなれば良くなると考えています。
病気になった時にもっとひどくなるかもしれないと思うことは悪いことではありませんが、それに対して過剰になってしまうことが問題です。その過剰性を改善していきます。
Tさんは後鼻漏になりやすいことも悩みであると言います。後鼻漏には2つのパターンがあります。鼻水が喉のほうに行く流入がひどい人と喉周辺の近くが過敏になり通常の量でも苦しさを訴える人です。後鼻漏の人は鼻水が止まれば気にならなくなるか、脳の過敏症が落ち着いたら気にならなくなります。
このタイプの人は気になる症状がコロコロ変わります。悩みがすり替わって行き最終的に全然違う悩みになるがこれは正常な改善の過程です。
鍼灸師は悩んでいる症状が不安感からくるものなのか体の病的な状態が発しているのかを見極めなければいけません。中途覚醒が悩みであるとしても夜に起きてしまうことは生理反応になるため1回起きてしまうくらいの中途覚醒は特に病気ではないと判断します。元気であれば寝付くまで時間がかかっても中途覚醒しても特に問題ありません。そのような細かいことが気にならなくなることが目標です。
肌を守るためという美容的観点としては日焼けは良くありませんが、日焼けをすることも元気になるためには非常に重要です。
Tさんの経過は順調でした。もう少し良い状態が続くと順応してきて土台が安定してきて良い状態が続くという見込みです。
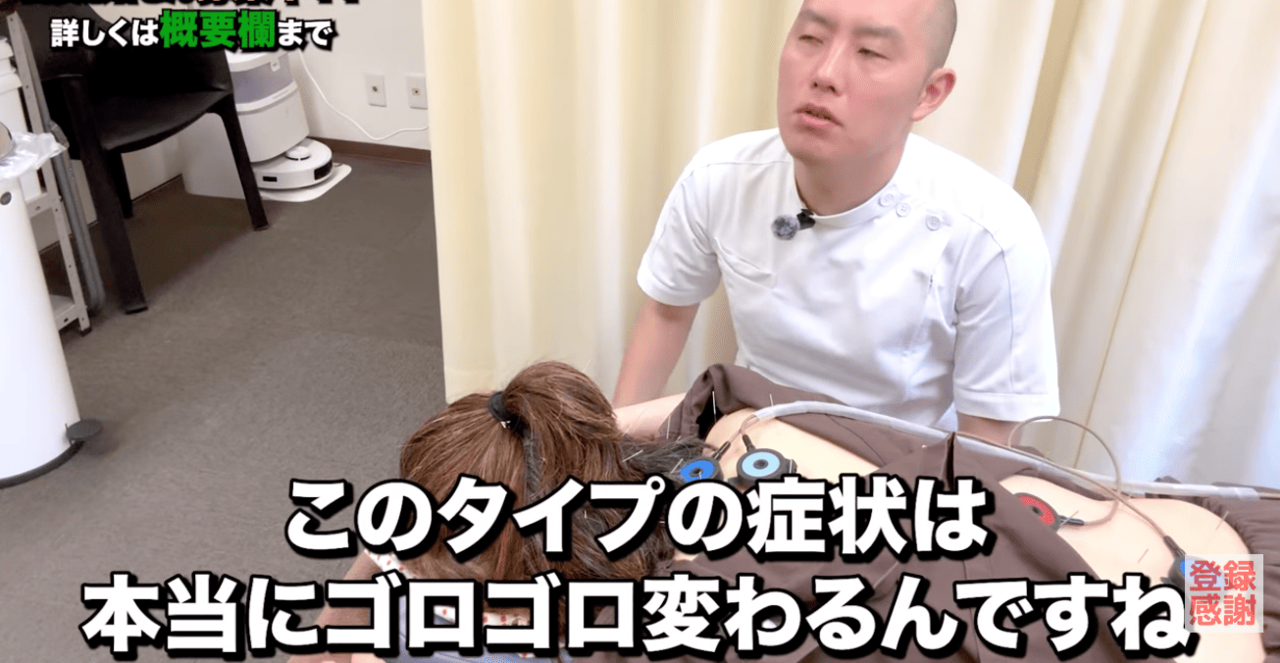

今回Tさんは2回目の施術でしたが、初回の時に確認された首の状態はほとんど改善していました。右首と左肩の影響が残っていましたがそれも今回だいぶ取れたと思います。
お腹の調子も良く極端な動悸や不安感もないということで経過は順調であると判断しました。不安感や微妙な症状は残っていましたが、3回目でそこもだいぶ落ち着くと見込んでいます。