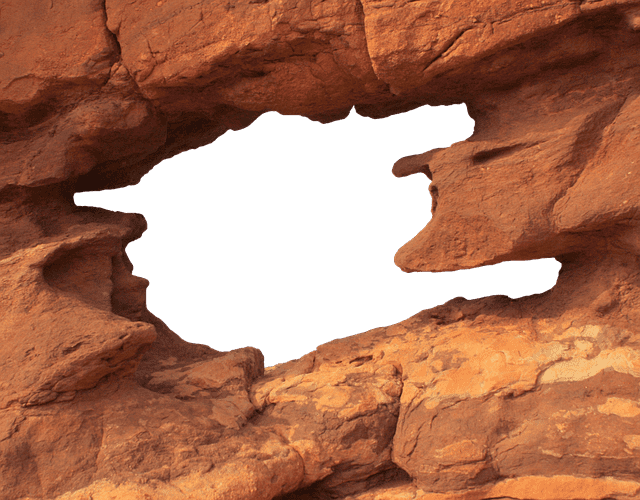脊髄空洞症の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2021年 8月 5日
更新日:2021年 9月 9日
本日は脊髄空洞症について解説させていただきます。

本記事の内容
- 脊髄空洞症とは
- 脊髄空洞症の原因
- 脊髄空洞症の症状
- 脊髄空洞症の改善方法
- 脊髄空洞症のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

脊髄空洞症の原因はいろいろあります。脊髄と脊髄の周りの組織に炎症が起こることや、腫瘍や脊髄の梗塞や出血などによって血管障害が起こること、外傷や奇形など様々です。中には、原因がわからない脊髄空洞症もあります。
脊髄空洞症の原因となる奇形の中でも代表的な奇形は、生まれた時から小脳の一部が脊柱管に落ち込んでいるキアリ奇形です。
脊髄空洞症は遺伝によって起こることはありませんが、一部に血の繋がった人に起こっている例もあります。
そのため、脊髄空洞症の原因の一部には体質や遺伝が関係している可能性があると考えられていますが、今のところ詳しいことはわかっていません。
脊髄空洞症は、脊髄内に液体がたまった空洞が形成される病気です。脊髄空洞症は、痛みや感覚障害、筋力低下などの神経症状を引き起こすことがあります。原因はいくつかありますが、主なものは以下の通りです。
・Chiari奇形
脊髄空洞症の最も一般的な原因は、Chiari奇形と呼ばれる脳の構造異常です。Chiari奇形では、小脳の一部が後頭骨の大孔を通り抜けて脊髄に圧迫をかけるため、脊髄内の脳脊髄液の流れが妨げられ、シリンクスが形成されます。
・脊髄損傷
外傷や事故による脊髄損傷が、脊髄空洞症の原因となることがあります。脊髄損傷が癒着や瘢痕組織を形成し、脳脊髄液の流れが妨げられることで、シリンクスが発生することがあります。
・髄膜炎
髄膜炎は、脊髄や脳を覆う髄膜に炎症が起こる病気です。髄膜炎によって髄膜が瘢痕組織を形成し、脳脊髄液の流れが妨げられることで、脊髄空洞症が引き起こされることがあります。
・脊柱管狭窄症
脊柱管狭窄症は、脊柱管が狭くなる病気で、加齢や変形性関節症などによって発生します。脊柱管狭窄症により脊髄の脳脊髄液の流れが妨げられることで、シリンクスが形成されることがあります。
・先天性異常
先天性の脊髄や脳の異常が、脊髄空洞症の原因となることがあります。これには、脊椎の骨が閉じていない脊椎骨折や、脊髄の神経節が異常に発達した脊髄脂肪腫などが含まれます。
・腫瘍
脊髄や脊柱内の腫瘍が、脊髄内の脳脊髄液の流れを妨げることで、脊髄空洞症を引き起こすことがあります。
・未知の原因
一部の脊髄空洞症では、明確な原因が特定できないことがあります。これを特発性脊髄空洞症と呼びます。特発性脊髄空洞症の場合、原因不明のまま進行することがあります。
脊髄空洞症の原因は人によって異なるため、適切な改善法を選択するためには、まず原因を特定することが重要です。

脊髄空洞症の症状は、片側の腕に感じる重苦しさや痛み、しびれです。
さらに、脊髄空洞症では火傷をしても熱さを感じなかったり、つねっても痛みを感じなかったりしする温痛覚障害が起こります。病気が進むと、しびれがひどくなったり筋肉が痩せたり手足が脱力したりする症状が現れます。
症状が現れる部分は、空洞のできた場所や広がりによって変わります。そのため、現れる部分や程度は人によって差があります。
空洞が延髄まで広がると、脳神経障害や球症状が現れ、関節が障害されたり、手足が異常に大きくなったりや発汗異常や立ちくらみなどの症状が現れます。
脊髄空洞症は、脊髄内に液体がたまった空洞が形成される病気です。シリンクスが脊髄の神経組織に圧迫をかけることで、さまざまな神経症状が現れます。脊髄空洞症の症状は、シリンクスの位置や大きさ、進行速度によって異なります。以下に、脊髄空洞症の主な症状を紹介します。
・痛み
脊髄空洞症では、しびれや鈍痛、焼けつくような痛みが現れることがあります。痛みは首や肩、腕、背中、手、脚などに広がることがあります。
・感覚障害
感覚異常が起こることがあり、温度や触感、痛みなどの感覚が低下することがあります。これにより、火傷や切り傷に気づかないことがあるため、注意が必要です。
・筋力低下
脊髄空洞症によって、筋力が低下し、筋肉が衰えることがあります。特に上肢や手の筋力が低下することが多く、日常生活に支障をきたすことがあります。
・運動失調
脊髄空洞症患者は、歩行や手指の動きに運動失調が現れることがあります。これにより、バランスを失ったり、物をつかんだりするのが難しくなることがあります。
・筋けいれん
脊髄空洞症では、筋けいれんや筋肉の引きつりが起こることがあります。これは、特に患者が寒さや緊張にさらされたときに現れることがあります。
・脊髄反射の異常
脊髄空洞症患者は、膝や足首の脊髄反射が異常になることがあります。これは、神経検査で確認されることがあります。
脊髄空洞症の症状は、進行が遅いことが多く、時には数年以上かけて徐々に悪化することがあります。また、症状は一時的に安定したり、悪化したりすることがあります。脊髄空洞症は個人差が大きく、症状が軽度である場合もあれば、重度で日常生活に影響を与える場合もあります。
・自律神経障害
シリンクスが脊髄の自律神経を圧迫すると、自律神経障害が発生することがあります。これにより、発汗障害や血圧の変動、排尿障害、便秘などの症状が現れることがあります。
・呼吸障害
シリンクスが上部の脊髄に位置する場合、呼吸障害が起こることがあります。これは、横隔膜や胸郭の筋肉の動きが制御される神経が圧迫されるためです。
・頭痛
Chiari奇形を原因とする脊髄空洞症では、激しい頭痛が発生することがあります。これは、脳脊髄液の流れが妨げられることで、頭蓋内圧が上昇するためです。
脊髄空洞症の症状が現れた場合、専門医に相談し、適切な判断と改善を受けましょう。

脊髄空洞症の改善は、症状にあわせて薬を使って行います。場合によっては手術を行うこともあります。
珍しいパターンですが、症状が進んだ後、症状が止まったり改善したりすることがあります。しかし、多くの場合は空洞が大きくなるにつれて、少しずつ症状も進んでいきます。
そのため、専門の医師のもとで適切にきちんと改善を行うことが大切です。
脊髄空洞症は、脊髄内に液体がたまった空洞が形成される病気です。その改善法は、原因や症状の重さによって異なります。以下に、脊髄空洞症の一般的な改善法を紹介します。
・症状管理
軽度の脊髄空洞症で症状が少ない場合、まずは症状管理が行われます。痛みや筋肉の緊張を和らげるために、鎮痛薬や筋弛緩剤が処方されることがあります。また、リハビリテーションが行われ、機能の維持や改善が目指されます。
・関連の病気の改善
脊髄空洞症の原因となる病気がある場合、その病気の改善が行われます。例えば、Chiari奇形や脊髄腫瘍が原因の場合、それぞれの病気に対する適切な改善が行われます。
・外科手術
症状が重度で進行している場合や、神経機能に重大な損傷がある場合、外科手術が検討されます。手術の目的は、シリンクスを縮小し、神経組織への圧迫を解除することです。以下に、一般的な外科手術の方法を紹介します。
a. シャント手術
シリンクス内にチューブを挿入し、液体を他の部位に排出することで、シリンクスの圧力を下げる手術です。ただし、シャントには感染や遊離のリスクがあります。
b. 後頭窩減圧術
Chiari奇形が原因の脊髄空洞症の場合、後頭窩減圧術が行われることがあります。頭蓋骨の後部を削ることで、脳幹や小脳にかかる圧力を緩和し、脳脊髄液の流れが改善されることを目指します。
c. 脊髄腫瘍の除去
脊髄腫瘍が原因の脊髄空洞症の場合、腫瘍の除去が行われることがあります。脊髄腫瘍の場合、腫瘍の種類によって手術方法が異なります。腫瘍の性質によって、完全に切除できない場合もあります。
脊髄刺激療法
外科手術が適さない場合や、手術後に再発した場合は、脊髄を刺激する方法が検討されることがあります。これは、脊髄に電気刺激を与えることで、痛みや筋肉の緊張を緩和する方法です。
・薬
痛みや筋肉の緊張を和らげるために、鎮痛薬や筋弛緩剤が処方されることがあります。また、シリンクスが感染を引き起こしている場合には、抗生物質が使用されます。ただし、薬は症状の改善に限度があるため、他の方法と併用されることが多いです。
脊髄空洞症の改善法は、症状や原因によって異なります。重症の脊髄空洞症では、外科手術が最も効果的であるとされていますが、手術にはリスクも伴います。個々の症状や進行度合い、医師の意見を参考にして、適切な方法を選択することが大切です。

脊髄空洞症を発症した場合は、定期的に適切な頻度で病院に通うことが重要です。脊髄空洞症を予防する方法は特にありませんが、筋力の低下や筋萎縮は脊髄空洞症を誘発する可能性があります。そのため考慮する必要があります。
咳やくしゃみで痛みが起こる原因は、脳脊髄液の圧が急に高くなることです。脳脊髄液の圧が急に高くなることで空洞が広がる可能性も考えられます。
そのため、咳やくしゃみで痛みが起こる人はなるべく咳やくしゃみをしないように注意しましょう。
Aの場合)脊髄空洞症により手足の痺れや痛み、歩行障害などの症状が現れていました。MRIにより、シリンクスの拡大が確認されたため、症状管理のために鎮痛薬や筋弛緩剤が処方されました。さらに、リハビリテーションが行われ、筋力やバランスの改善が目指されました。経過観察の結果、症状が軽減され、日常生活に支障をきたすほどではなくなりました。
Bの場合)Chiari奇形により脊髄空洞症が発生していました。頭痛や手足のしびれ、歩行障害などの症状が現れ、MRIによりシリンクスの拡大が確認されたため、後頭窩減圧術が行われました。手術後は、症状が改善され、日常生活に支障をきたすことがなくなりました。
Cの場合)外科手術が適さないため、脊髄を刺激する方法が行われました。痛みや筋肉の緊張が慢性的に続いていたため、脊髄に電気刺激を与えることで症状の改善を目指しました。経過観察の結果、痛みや筋肉の緊張が軽減され、日常生活に支障をきたすことが少なくなりました。
Dの場合)痛みや筋肉の緊張が続いていたため、鎮痛薬や筋弛緩剤が処方されました。さらに、シリンクスが感染を引き起こしていたため、抗生物質も併用されました。経過観察の結果、症状が改善され、日常生活に支障をきたすことが少なくなりました。