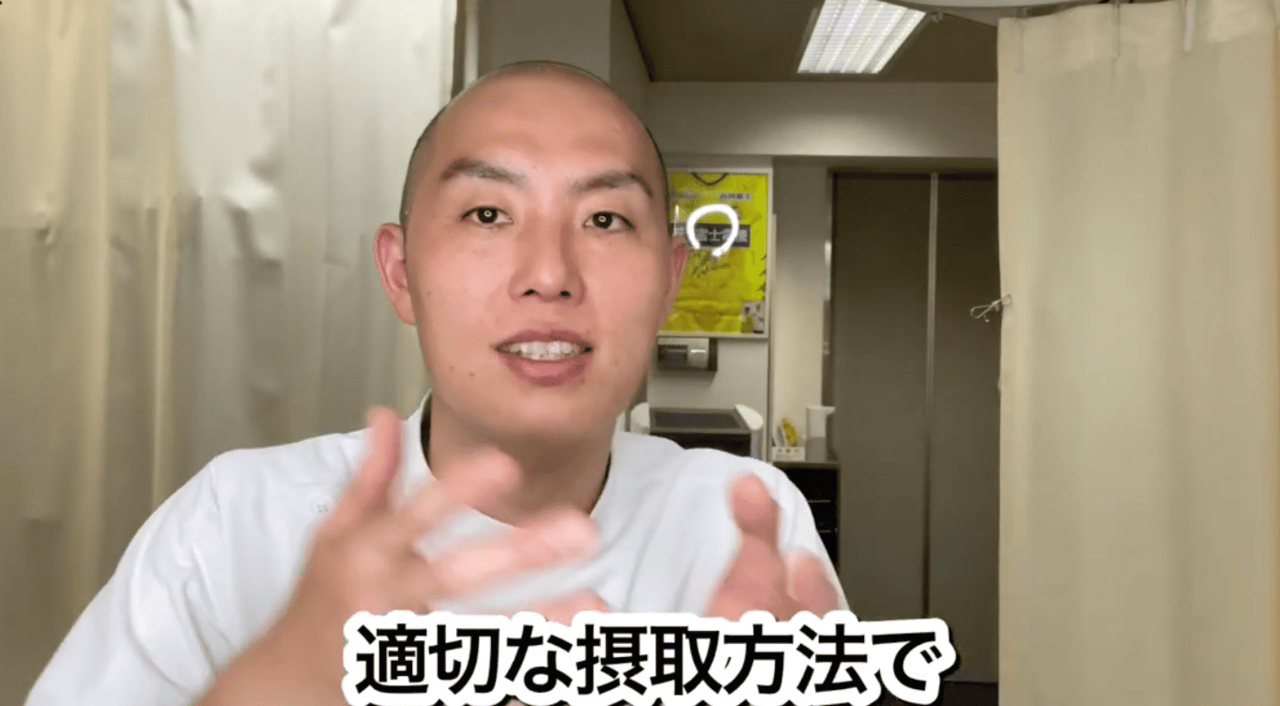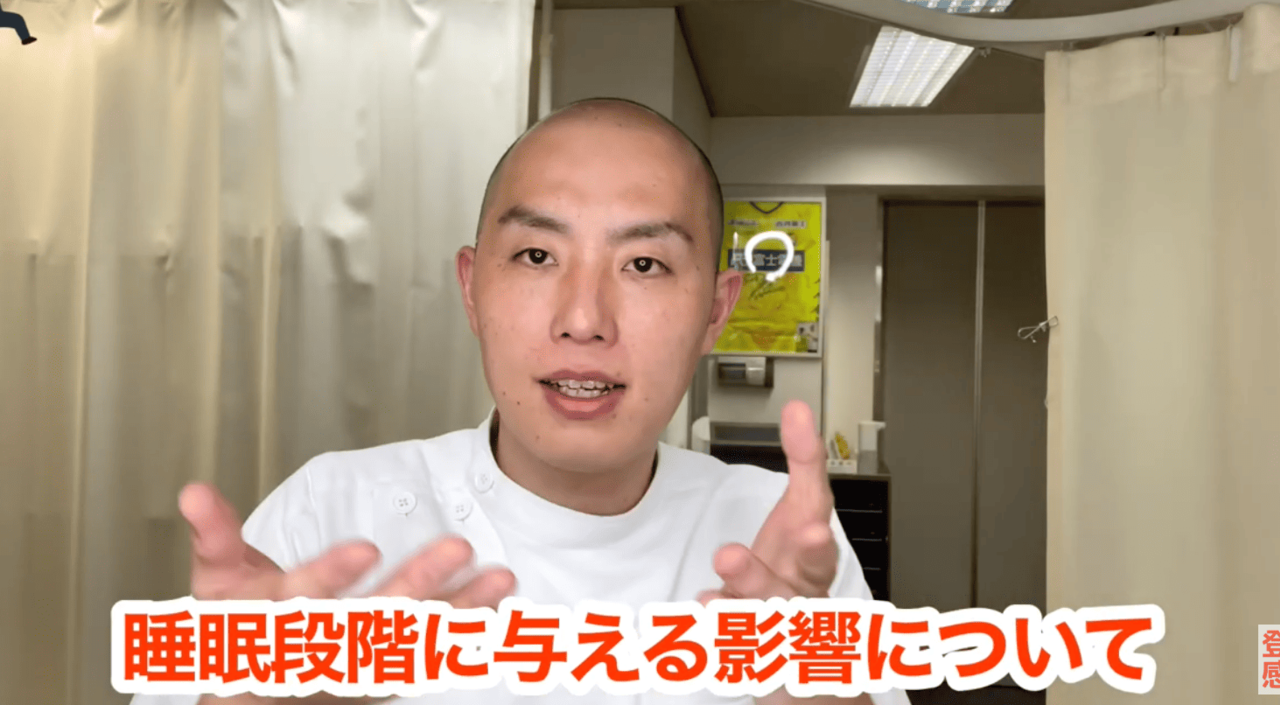アルコール依存症の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2022年 3月23日
更新日:2025年 7月 3日
本日はアルコール依存症について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- アルコール依存症とは
- アルコール依存症の原因と症状
- アルコール依存症症になりやすい人
- アルコール依存症の改善方法
- アルコール依存症のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。
アルコール依存症は、精神的な病気です。何度も繰り返したくさんの量のアルコールを繰り返し摂取することによって、アルコールに依存した状態になり、精神的な障害が起きたりや身体的な機能に障害が起きたりします。
アルコール依存症について意志が弱い、性格の問題であるなどと思う人もいるかもしれませんが、アルコール依存症は個人の性格や意思の問題ではありません。
WHOの策定した国際疾病分類第10版では、精神および行動の障害の中に分類されている病気なのです。
アルコール依存症を発症すると、発症する前は大きな価値をもっていたいろいろな行動よりも飲酒をすることを優先してしまうようになります。
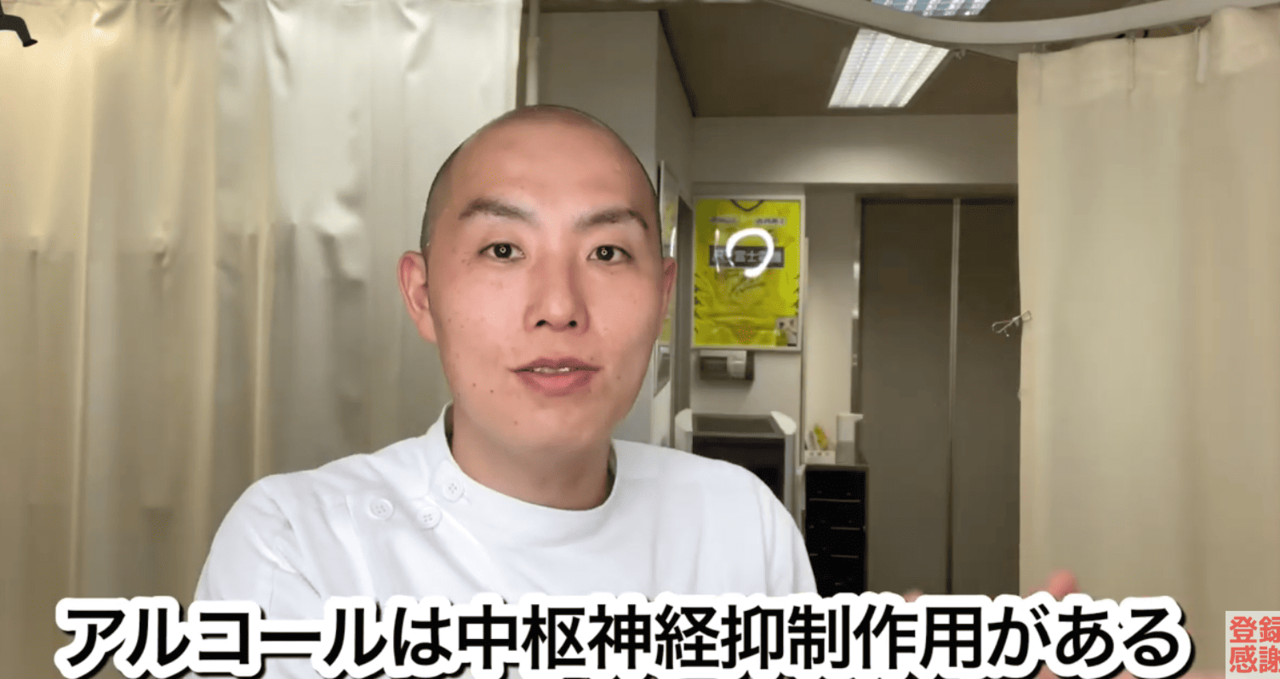
アルコール依存症の原因には、脳の報酬系という神経回路が関係しています。アルコールは麻薬と共通する作用があります。アルコールは、依存性のある薬物なのです。
大量に飲酒をしたり、生まれつきアルコールを分解する能力が高い体質をしていたり、未成年の時から飲酒を行なったりすることが、アルコールに依存する要因になります。
他にもアルコール依存症を引き起こす要因として、うつやパニック障害、摂食障害などの精神的な苦痛が挙げられます。
アルコールを摂取することによって精神的な苦痛を和らげようとして、飲酒するようになり、だんだんと飲酒の量が増えることがあるのです。
アルコールは少しの量であれば、体に対して良い効果もあります。
しかし、長時期間にわたって大量にアルコールを摂取する生活を続けると、理性で抑えられないほどの強い飲酒欲求が生まれ、アルコールに対しての慣れにより摂取する量が増えてしまうようになります。
アルコール依存症で現れる症状は、アルコールが抜けたときの崩れて手の震えや幻覚です。体では肝臓に病気が現れたり、脳萎縮や高血圧、膵炎、食道がん、大腸がんなどを発症する可能性があります。
うつやパニック障害、女性の摂食障害なども合併症として現れることが多いです。妊娠中の女性の場合、赤ちゃんの奇形や精神発達遅滞につながることもあります。
主な原因
①脳の報酬系の異常
アルコールは、脳内の報酬系に働きかけ、ドーパミンという快楽物質を大量に放出させます。一時的な幸福感やリラックス感を得られ、脳がまた飲みたいと強く学習してしまいます。時間が経つと、飲まないとイライラや不安が出るようになります。
②離脱症状による身体依存
長期的に飲酒を続けると、脳がアルコールの存在に慣れてしまい、常にアルコールがあることを前提に機能するようになります。急に飲まなくなると、震えや不安、不眠、けいれんなどが起こります。離脱を回避するためにまた飲む悪循環へ陥ります。
③ストレスや不安の自己処理手段としての飲酒
仕事で疲れたから一杯、人間関係のストレスで飲まずにいられない、不安で眠れないから寝酒をなどの飲酒が続くと、アルコールが感情調整手段になってしまい、依存のリスクが高まります。
④発達特性・トラウマ・愛着の問題
アルコール依存の背景には、以下のような深層心理的な問題があることも少なくありません。幼少期のネグレクトや虐待、自尊心の低さ、孤独感、発達障害によるストレス処理の困難さなどが関係しています。
⑤遺伝的要因
アルコールに強い体質を持っていると、飲酒量が増えやすく依存につながりやすいです。一親等の家族に依存症がある場合、発症リスクは約3~4倍に上がるとされています。
⑥社会的・環境的要因
飲酒が当たり前の文化、一人暮らしや無職など誰にも止められない環境、身近に依存者がいる場合、環境要因は、依存を悪化させるトリガーとして非常に強力です。
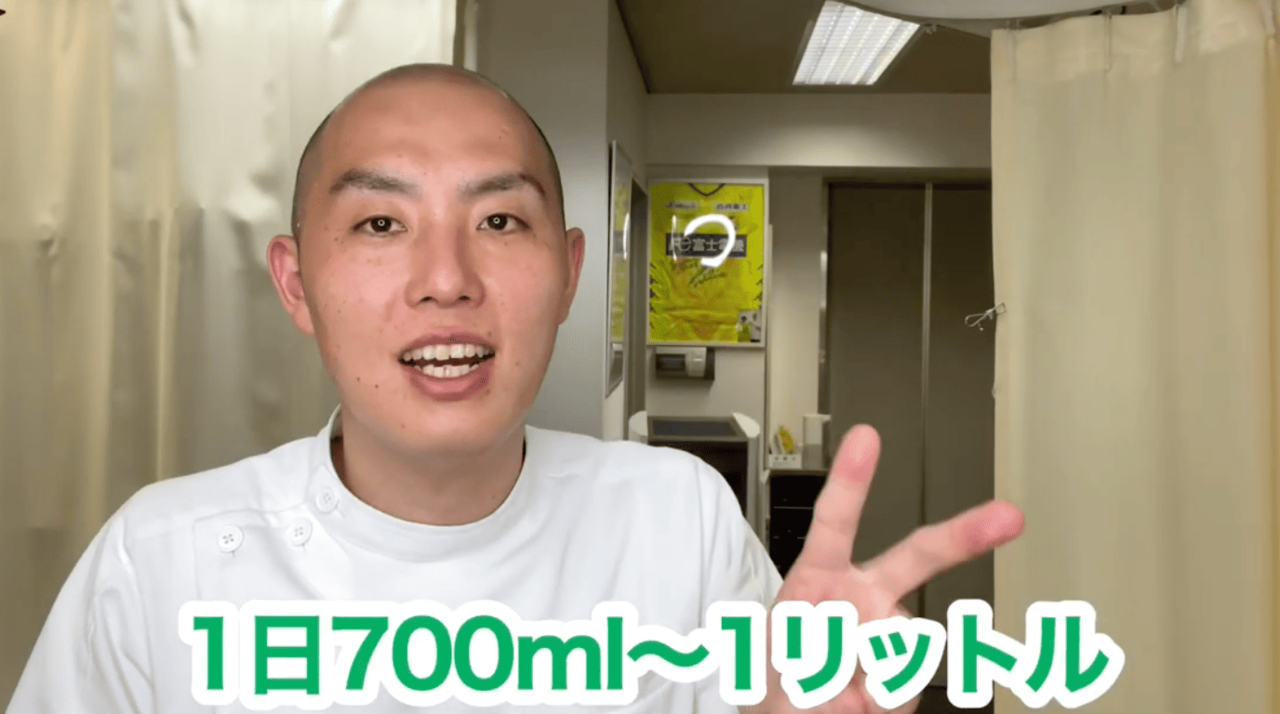
アルコール依存症は、飲酒をする人であれば誰でも発症する可能性があります。ただし、アルコール依存症になりやすい要因もいくつかあります。
未成年の時から飲酒していると、アルコール依存症になりやすいということがわかっています。統計でも、飲酒する年齢が早ければ早いほど依存症になる危険性が高いことが知られています。
家族や親友に飲酒をする習慣がある人が多いことも要因の一つです。家族に飲酒する習慣がある場合、依存症に対して警戒心が低かったり未成年のときから飲酒を認めてしまったりする状態が見られるためです。
親がアルコール依存症の場合では、子供が依存症になる確率が4倍に上がると言われています。依存症の原因の半分は遺伝にあるとも言われているのです。
さらに、アルコール依存症の親の家庭では夫婦での喧嘩が多く子供が暴力を振るわれることもあります。そのため、子供は情緒不安定になり、大人になってからアルコール依存症を発症しやすくなるのです。
アルコール依存症を発症している人は男性の方が多いです。しかし、最近では若い女性のアルコール依存症も増えています。
女性は、男性よりも依存症になるまでの期間が短く、同じ量でも血液のアルコール濃度が高くなるため、問題が起きることが多いと言われています。若い女性だけではなく、高齢者のアルコール依存症も最近増えています。
高齢者のアルコール依存症のきっかけとして多いものは、退職や配偶者との別れなどで孤独になることです。アルコールで満足感や安心感を簡単に得るようになるのです。
うつ病やパニック障害の人も、アルコールで気持ちを解決しようとしてアルコール依存症になることも多いです。
アルコール依存症チェック
- 飲酒量や回数を自分でコントロールできないことがある
- 飲まないとイライラ・不安・手の震え・寝つけないなどの離脱症状が出る
- 飲酒のために大切な仕事や家族との時間を犠牲にしている
- 「今日こそは飲まない」と決めても、結局飲んでしまうことが多い
- 飲酒を隠す、嘘をつく、こっそり飲むことがある
- 飲酒後に覚えていない記憶の欠落がある
- 飲酒のことで家族や友人に注意されたことがある
- 一度飲み始めると、止まらなくなる
- 飲酒によって事故、喧嘩、金銭トラブルなど問題を起こしたことがある
- 飲酒のせいで肝機能異常、高血圧、不眠など健康を害している
- 飲酒に対する罪悪感や後悔を感じることがある
- 「酒がなければやっていけない」と思ったことがある
〈判定の目安〉
0〜2個: 依存のリスクは低いですが、予防意識を持ちましょう。
3〜4個: 軽度のアルコール依存の傾向。生活習慣の見直しが必要です。
5〜6個: 中等度の依存が疑われます。専門家への相談をおすすめします。
7個以上: アルコール依存症の可能性が高いです。医療機関の受診や支援が必要です。
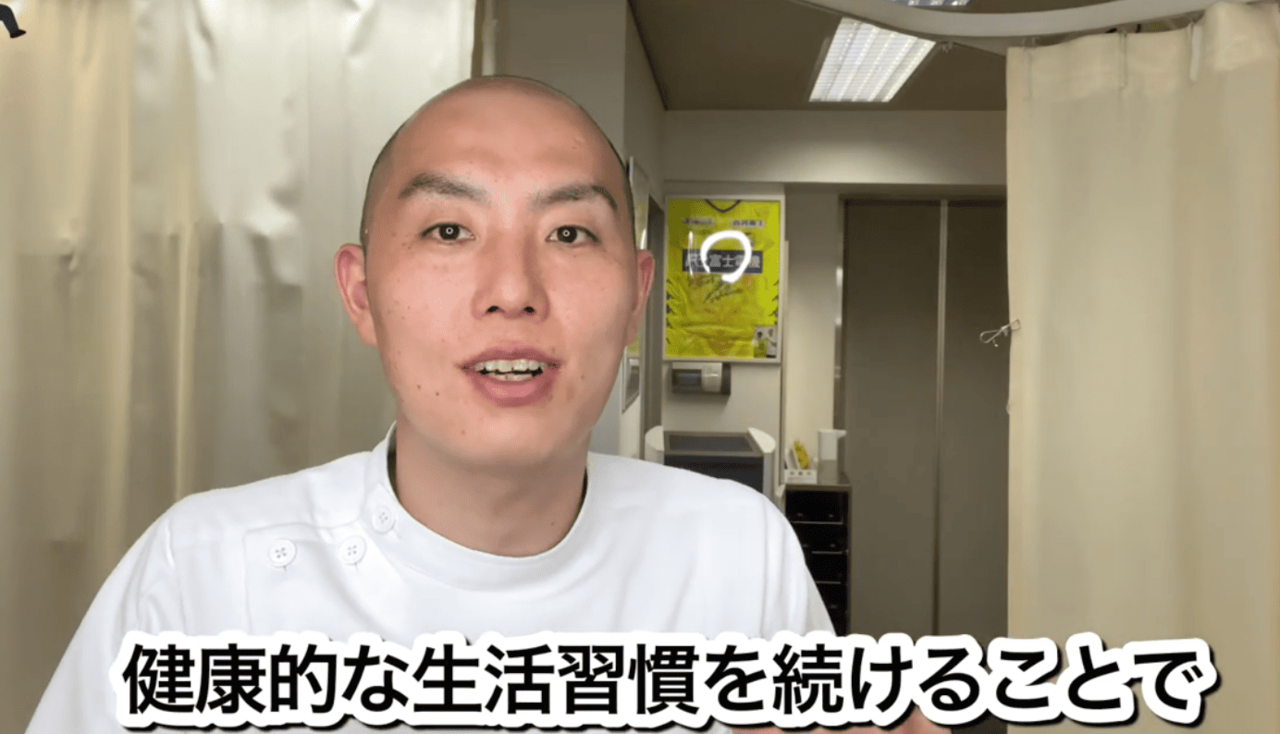
アルコール依存症の改善方法は、カウンセリングや病気の教育、断酒を続ける技術を得ることです。また、飲酒をしない状態で過ごすことのできる生活環境をサポートすることも大事になります。
アルコール依存症の改善の目標は断酒です。ただし、症状が軽く、合併症がない場合は飲酒量を減らすことを目標とする場合もあります。
薬では、離脱症状を抑えるための抗不安薬や人工的に下戸にするための抗酒剤、飲酒の欲求を抑えるための断酒補助剤などを使います。しかし、薬を使うだけでは、断酒をすることはできません。
心理的な面や社会的な面でも断酒ができるように取り組むことが大事になります。
断酒会やアルコホーリクス・アノニマスなどの自助グループもあるため、そのような場所に参加することも改善に役立ちます。
断酒のために参加するのではなく、仲間との交流を通して心理的に改善できるように考えることができたり、コミュニケーションを取ることができたりするために参加をすることで、改善につながる場所になる可能性があるのです。
主な改善方法
①本人が依存症であると気づくこと
改善の第一歩は、自分が病的な飲酒パターンに陥っていると受け入れることです。「意思が弱い」のではなく、「脳の病気」として認識します。恥や罪悪感で隠すのではなく、正しく理解することがスタートです。
②専門医療機関に行く
アルコール依存症は、精神科や依存症外来などで改善を受けることができます。
③自助グループの活用
同じ悩みを持つ仲間とのつながりは、回復において非常に重要です。あなたは一人じゃないと感じられることが、再飲酒を防ぐ最大の力になります。
④再飲酒防止の仕組みづくり
再発は依存症では非常によくあることですが、環境や習慣を見直すことで防ぎやすくなります。現金やクレジットカードを持ち歩かない、一人で飲みやすい店や人間関係から距離をとる、飲酒したくなるきっかけを分析し、回避行動を撮りましょう。
⑤感情コントロール力を養う
多くの方は、ストレスや孤独、怒り、不安をアルコールで処理しようとしてしまいます。マインドフルネス瞑想や深呼吸、日記や感情ログを書く、信頼できる人と気持ちをシェア、軽い運動などをして飲まない生活がつまらないのではなく、飲まなくても楽になれる道を脳に覚えさせることが大切です。
⑥人生の目的や役割を再構築する
依存症からの回復は、やめることではなく別の生きがいを手に入れることです。人とのつながり、新しい趣味や学びで誰かの役に立つ体験をして自己肯定感の再構築をしましょう。回復は新しい自分の人生を築くことです。
⑦鍼灸、東洋医学での補助的サポート
自律神経や情緒の安定を目的とした鍼灸や気功なども、再飲酒予防に効果的です。
鍼灸の効果
①自律神経の安定
依存症では、交感神経が過剰に優位になりやすく、興奮・不安・イライラが強くなります。鍼灸は、副交感神経を活性化させ、脳の緊張を鎮める作用が確認されています。衝動的に飲みたくなる、常にソワソワ・イライラする、心拍数の上昇・動悸などの改善に効果が期待できます。
②不眠や睡眠の質の改善
アルコール依存症の多くの方が、眠れない・眠りが浅い・夜中に目が覚めるなどの不眠を訴えます。鍼灸はメラトニン分泌の促進、脳内GABA活性の向上、血流改善と体温調整による入眠の促進などに効果的です。
③胃腸・肝臓の機能回復
長期の飲酒は、肝機能障害・胃腸の炎症・食欲不振・便秘や下痢などを引き起こします。鍼灸では五臓六腑の「肝・脾・胃」の気血を整え、消化吸収・解毒力を高めるアプローチを行います。
④感情の安定
アルコール依存の背景には、孤独・喪失体験・罪悪感・無力感など、深い感情の傷があることが多いです。鍼灸は、単なる身体への刺激ではなく、経絡を整えることで、感情エネルギーの滞りを解消する効果があります。
⑤再飲酒の抑制
最新の研究では、鍼灸が側坐核や扁桃体に影響を与え、依存傾向を緩和する可能性があることも示唆されています。耳鍼や頭部鍼によって、ドーパミン系の過活動を抑える効果が報告されています。
⑥改善したいという気持ちを強化する効果
鍼灸では、自然に改善する力を呼び覚ますことが基本です。そのため、施術の過程で「自分は変われる」「身体が変化している」という回復の実感が芽生えやすくなります。
アルコールは一時的にリラックスさせる効果がありますが、適量を越えると睡眠に悪影響を及ぼすことがあります。
アルコールは中枢神経抑制作用があるため、リラックス効果をもたらします。しかし、これは一時的で適量を超えると睡眠の質を低下させる原因になります。
アルコールが睡眠段階にもたらす影響
1.睡眠の入りが早まる
アルコール摂取により眠りにつくのが早くなることがあります。ただし、これは一時的な効果でアルコールが代謝されるにつれて中途覚醒が起こりやすくなります。
2.レム睡眠の減少
アルコールは特にレム睡眠の減少を促します。レム睡眠は記憶の整理や情緒の安定に関与するため非常に重要な睡眠段階です。アルコールの摂取が続くと疲労回復が十分にできないことがあります。
3.ノンレム睡眠への影響
アルコールを摂取するとノンレム睡眠の深い睡眠であるデルタ波が減少し、浅い睡眠が増えます。これにより睡眠中の中途覚醒が起こりやすくなり翌朝疲れを残してしまいます。
アルコール摂取の注意点
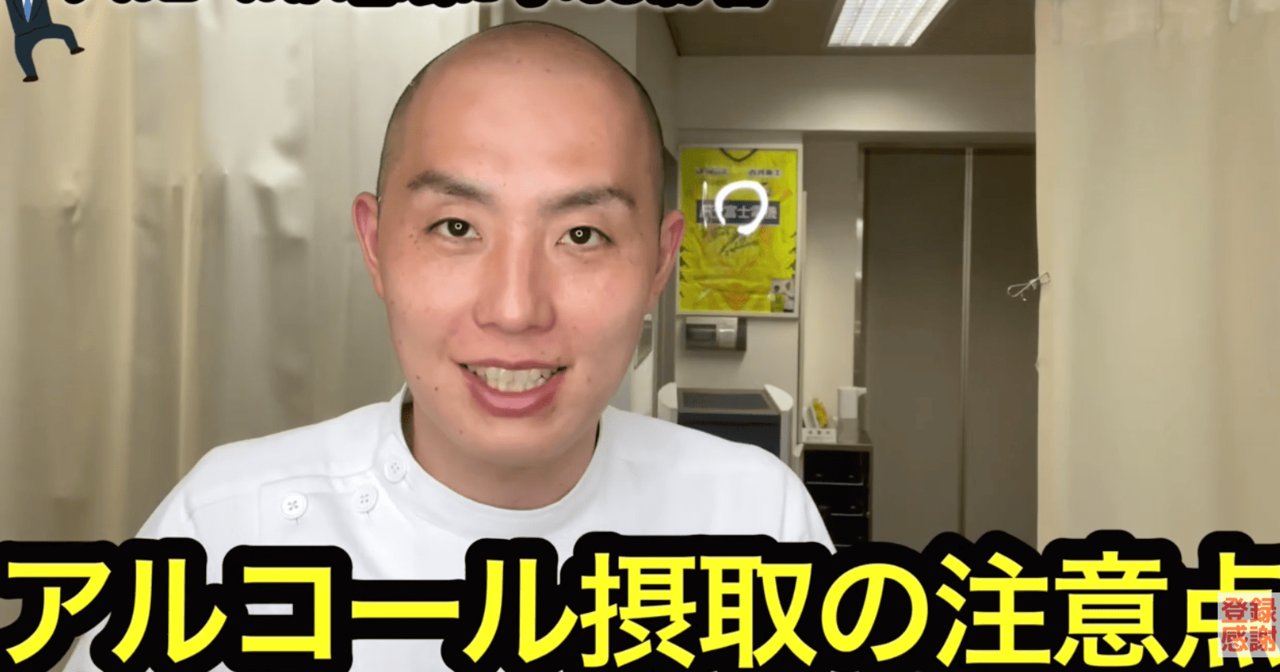
1.適量を守る
適量であればリラックス効果を享受できるため過剰摂取は避けましょう。
2.寝る数時間前に摂取することをやめる
睡眠に影響を及ぼさないために就寝の23時間前にはアルコール摂取を控えることが望ましいです。
3.水分補給を忘れない
アルコールは利尿作用があるため脱水状態になりやすいです。そのためアルコール摂取時は水分補給を十分に行うことが大事です。
4.睡眠環境を整える
アルコール摂取後でも良い睡眠環境を整えることが大事です。寝室は静かで暗くて涼しい状態を保ち、快適な寝具を使いましょう。
5.アルコールの対処を助ける
アルコールを適量に抑えるだけではなく対処を促す食品やサプリメントの摂取も有効です。ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンC、ナイアシンなどのビタミン剤はアルコールの対処を助けます。アルコール摂取時に食事と一緒に取ることでアルコールの吸収を穏やかにすることができます。
6.睡眠リズムを整える
アルコールが睡眠段階に与える影響を最小限にするためには睡眠リズムを整えることが大事です。定時的な起床時刻と睡眠時刻を維持し充分な睡眠時間を確保しましょう。
アルコール飲料に含まれるエタノールの割合を示し濃度によって影響が異なります。
〈アルコール度数別の適量摂取量〉
ビールやワインなどアルコール度数5〜12%程の低アルコール度数に対しては、男性の場合1日2〜3缶、高齢者は1日1缶、女性の場合1〜2缶を目安にしましょう。弱い人は1日1缶以下で抑えましょう。
ただしこれは一般的な目安で、個々の体質や健康状態で適量が変わります。妊娠中や授乳中の女性、アルコール依存症、肝臓の病気の方は医師と相談の上で摂取量を考えましょう。適切な度数と量を守ることでリラックこ効果を享受しつつ睡眠の質を維持させましょう。
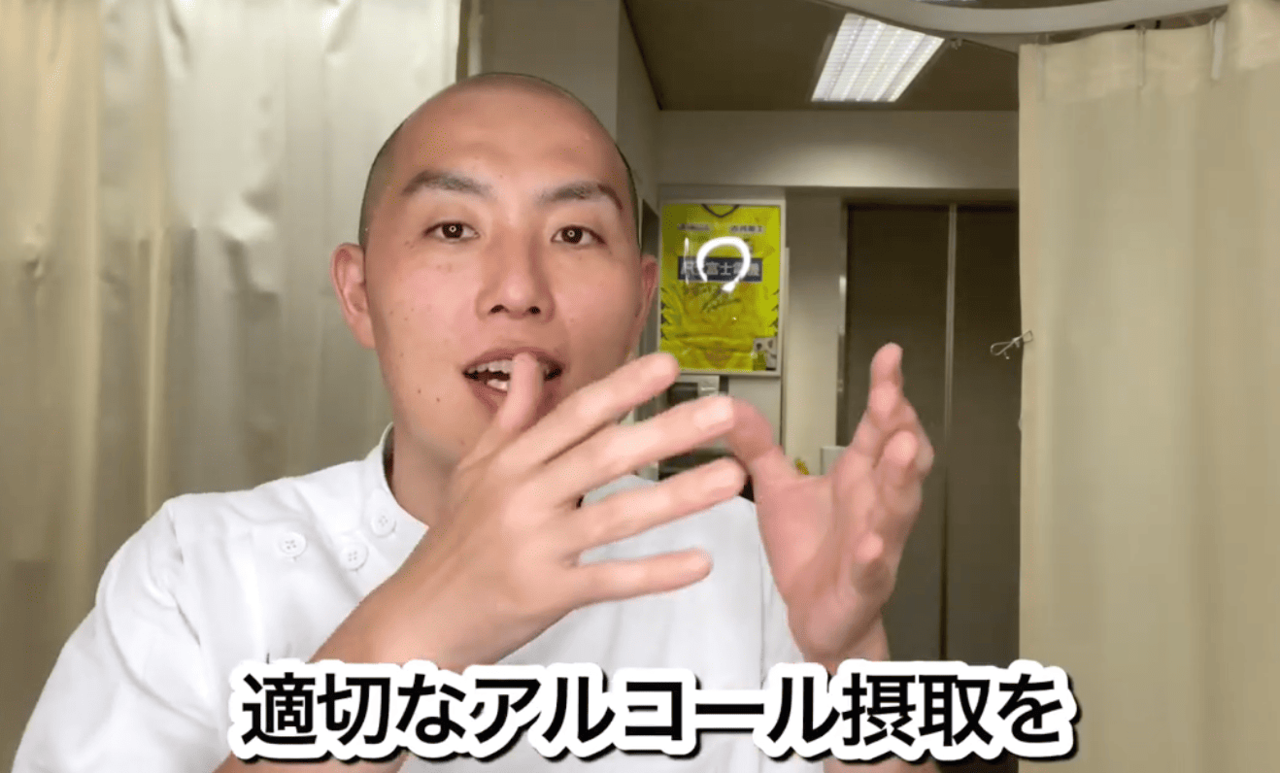
アルコール依存症を防ぐためには、飲み過ぎないように注意をすることが大事です。
アルコール依存症を発症してしまった場合には、なるべく早く改善を行うことが大事です。お酒の量を減らすためには、毎日飲酒した量の記録をつけることから始めると良いでしょう。
アルコール依存症は改善を行なっても、約7割の人が1年後に大量の飲酒をしてしまうようになるという報告もあります。アルコール依存症は非常に再発しやすい病気なのです。
最近では都道府県や政令指定都市ごとに依存症の専門病院や相談窓口の整備も進められています。問題を抱え込まず、早めに相談することで改善につながります。