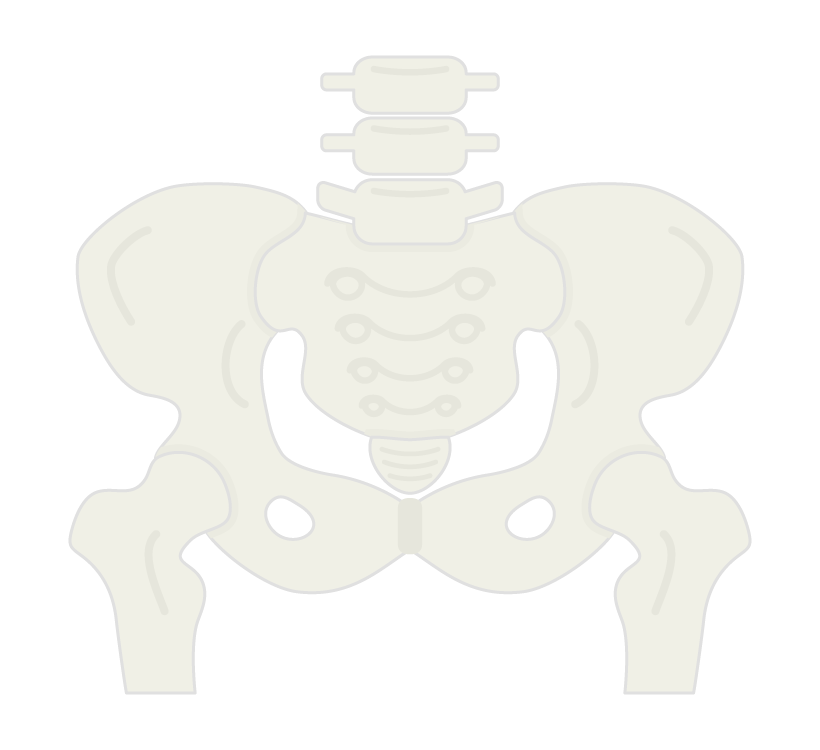溢流性尿失禁の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2022年 10月23日
更新日:2023年 12月 1日
本日は溢流性尿失禁について解説させていただきます。

☆本記事の内容
- 溢流性尿失禁とは
- 溢流性尿失禁の原因
- 溢流性尿失禁の症状
- 溢流性尿失禁の改善方法
- 溢流性尿失禁のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。

溢流性尿失禁の前提には、排尿障害があります。排尿障害は、尿路が閉塞することで尿の流れが妨げられたり、神経の損傷や排尿筋の筋力の低下によって膀胱の収縮力が弱くなったりすることで起こります。
排尿障害を発症する代表的な病気には、前立腺肥大症や膀胱結石、尿道結石、尿道狭窄症、神経因性膀胱などが挙げられます。
女性の場合は、子宮筋腫や子宮脱、膀胱瘤も排尿障害の原因になることがあります。このような原因によって排尿障害があることが溢流性尿失禁の原因になるのです。
溢流性尿失禁は、膀胱が過剰に満たされた状態で、尿が膀胱から漏れ出る状態を指します。主な原因は以下の通りです。
膀胱の出口の障害:尿道や膀胱の出口の障害により、尿の流れが妨げられることがあります。前立腺の問題(前立腺肥大や前立腺癌)、尿道狭窄、尿道結石などが原因となり得ます。
膀胱筋の機能不全:膀胱筋(特に膀胱の収縮筋)の弱さや機能不全により、尿が完全に排出されないことがあります。これは膀胱筋の神経障害によるものか、直接的な筋肉の損傷によるもののいずれかです。
神経系の障害:神経系の障害が膀胱の感覚や収縮機能に影響を及ぼすことがあります。糖尿病性神経障害、脊髄損傷、多発性硬化症、脳卒中、パーキンソン病などが原因となることがあります。
薬剤の副作用:特定の薬剤(抗コリン薬、抗精神病薬、鎮痛薬、高血圧治療薬など)が膀胱の機能に影響を及ぼし、溢流性尿失禁を引き起こすことがあります。
手術後の合併症:特に骨盤内や腹部の手術後に、膀胱や尿道の機能障害が生じることがあります。
溢流性尿失禁は、特に男性に多く見られる症状ですが、女性でも発生する可能性があります。

溢流性尿失禁の症状は、自分の意思と関係なくだらだらと尿が漏れることです。
他にも、排尿を始めるまでの時間がかかることや尿意があるのかないのかはっきりとわからないこと、尿が少しずつしか出ないこと、力を入れなければ尿が出ないこと、残尿感があることなどもあります。
溢流性尿失禁をそのまま放っておくと、膀胱にたまっている尿に細菌が繁殖し、細菌が腎臓まで達し腎盂腎炎を引き起こすこともあります。腎盂腎炎を起こすと、場合によっては腎不全などの状態につながることもあるため注意が必要です。
溢流性尿失禁は、膀胱が過剰に満たされた結果、尿が小量ずつ漏れ出る状態を指します。このタイプの尿失禁に伴う主な症状は以下の通りです。
頻繁なまたは持続的な尿漏れ:膀胱が過剰に満たされると、尿が少量ずつ漏れることがあります。
尿の排出が困難:尿を始めるのに時間がかかる、尿流が弱い、尿が細い線状にしか出ない。
尿流の途切れ:尿流が途切れ途切れになることがあります。
膀胱が常に一部満たされている感覚:排尿後も膀胱に尿が残っているような感じがします。
排尿後の滴下:排尿後も尿が少量漏れ続けることがあります。
排尿の回数の増加:尿閉により頻繁にトイレに行く必要がありますが、一度に排出される尿量は少ない。
夜間の頻尿:夜間に何度も尿意で目が覚めることがあります。
尿意の感じにくさ:尿意を感じる能力が低下していることがあります。
溢流性尿失禁は、前立腺肥大、膀胱の筋肉機能不全、神経障害などが原因で起こることが多いです。男性に多く見られますが、女性でも発生することがあります。

溢流性尿失禁の改善方法は、原因によって違います。前立腺肥大症などによって尿路が閉塞することが原因の場合は、手術で肥大した前立腺の一部や全体を摘出します。
前立腺の縮小や肥大は、場合によっては薬を使うことによって止められることもあるため、薬による改善を行うこともあります。
再発性の尿路感染症や水腎症などの合併症を防ぐために、カテーテルを膀胱の中に入れて膀胱から一定時間ごとに尿を排出する方法を行うこともあります。
溢流性尿失禁は、膀胱が過剰に満たされて尿が漏れる状態です。原因によって改善法が異なりますが、以下に主な改善方法を挙げます。
膀胱の訓練:定期的な排尿スケジュールを設定し、膀胱の過剰な満たし方を防ぎます。一定の時間間隔でトイレに行く習慣をつけることが有効です。
間欠的自己導尿(ISC):特に神経障害による膀胱の機能不全の場合、定期的にカテーテルを使用して膀胱を空にする方法があります。
薬:前立腺肥大や膀胱の筋肉の緊張が原因の場合、アルファ遮断薬(例:タムスロシン)や5-アルファ還元酵素阻害薬(例:フィナステリド)などが処方されることがあります。
骨盤底筋トレーニング:骨盤底筋を強化する運動(ケーゲル運動など)が、膀胱のコントロールを改善するのに役立つことがあります。
手術:前立腺肥大が原因の場合、前立腺を縮小する手術が行われることがあります。尿道の狭窄が原因の場合、尿道拡張術や尿道形成術が必要な場合があります。
水分摂取の管理:適切な水分摂取量を維持し、過剰な水分摂取を避けることで、膀胱の過負荷を防ぎます。
便秘の予防:便秘は膀胱への圧迫を増やすため、食物繊維の豊富な食事や十分な水分摂取で便秘を予防します。
これらの方法は、溢流性尿失禁の原因と全体的な健康状態に基づいて個別に選択されるべきです。
溢流性尿失禁の改善において使用される薬物は、症状の原因に応じて選択されます。主な薬のオプションは以下の通りです。
アルファ遮断薬:前立腺肥大が原因の場合、膀胱の出口と尿道の圧力を減少させるために用いられます。
例えば、タムスロシン(フロマックス)、アルフズシン(ユロキサトラール)、ドキサゾシン(カルデュラ)、テラゾシン(ヒドリン)など。
5-アルファ還元酵素阻害薬:前立腺肥大を縮小させる効果があります。
例えば、フィナステリド(プロスカー)やデュタステリド(アボダート)。
抗コリン薬(特に神経原因による場合):過活動膀胱を抑制し、膀胱の収縮をコントロールします。
例えば、オキシブトニン(ディトロパン)、トルテロジン(デトロール)。
カフェインやアルコールの避ける:カフェインやアルコールは膀胱を刺激し、症状を悪化させる可能性があるため、これらの摂取を控えることが推奨されます。
これらの薬はそれぞれ異なる副作用を持つ可能性があります。アルファ遮断薬は低血圧やめまいを引き起こすことがあり、抗コリン薬は口渇や便秘などの副作用を引き起こすことがあります。
また、薬だけでなく、生活習慣の変更や骨盤底筋トレーニングも重要な役割を果たすことがあります。

溢流性尿失禁を防ぐためには、溢流性尿失禁の原因になる病気を防ぐことが大事です。原因になる可能性がある病気を発症している場合は、進行しないよう心がけることも大事です。
前立腺肥大症の場合は、肥満や高血圧、高血糖、脂質異常症などの生活習慣病と関係があると言われているため、食習慣や運動習慣を見直すことが大事です。
抗コリン薬や抗ヒスタミン薬などは、溢流性尿失禁の原因になることもあるため、気になる場合は医師や薬剤師に相談をしましょう。

・中極
・次髎
・水泉
中極
中極の効果は、尿の排出のリズムを整えることです。そのため、尿失禁や頻尿や生理痛、生理不順、前立腺肥大症などに対して有効であると言われています。
中極への刺激は、前立腺肥大症などの病気から溢流性尿失禁を発症することもあることや、尿失禁に効果があることから溢流性尿失禁にも効果が期待できるのです。
次髎
次髎は、排尿障害や生殖器の問題、腰痛や冷え性などに効果を発揮するツボです。
溢流性尿失禁は前提に排尿障害があります。そのため、排尿障害を和らげることができれば、溢流性尿失禁の予防にもつながるのです。
次髎は、骨盤の中の臓器の調整する効果もあるため、女性の子宮や卵巣の機能を助けて働きを良くすることにも効果的です。
水泉
水泉は、体の中の水分代謝を助ける作用があり、排尿障害や浮腫などに効果的なツボです。溢流性尿失禁は排尿障害があることによって起こります。そのため、排尿障害に効果があるということは溢流性尿失禁にも有効なのです。
ホルモンバランスを整える効果もあり、浮腫などにも有効です。
ツボの位置と押し方
中極
中極の場所は、へその下側に指をあて、下に指幅4本分下がった箇所です。
押すときは、親指の腹を使って押します。ゆっくりと弱い力で押すことが大事です。
次髎
次髎は、骨盤の中央の仙骨にあるくぼみのうち、上から2番目にあるくぼみにあります。
押すときは、中指や人差し指の腹を使って押します。押してみて、痛気持ちいいと感じる場所をほぐすような感覚で押しましょう。
水泉
水泉は、かかとと内くるぶしを結んだ線の中間にある骨のへこみにあります。
押すときは、親指を使って押します。押すときの強さは、響きを感じるような強さで押します。押す時間は約3秒です。3秒かけて押し、3秒かけて離します。