前頭側頭型認知症の鍼灸【原因・定義・症状】
公開日:2021年 12月 2日
更新日:2024年 12月12日
本日は前頭側頭型認知症について解説させていただきます。
☆本記事の内容
- 前頭側頭型認知症とは
- 前頭側頭型認知症の原因
- 前頭側頭型認知症の症状
- 前頭側頭型認知症の改善方法
- 前頭側頭型認知症のまとめ

銀座そうぜん鍼灸院の宗前です。
このページを書いている私は、鍼灸師として13年、担当した利用者様数80,000人を誇り、病気の休職者300人を社会復帰できるまで回復させてきた実績があります。
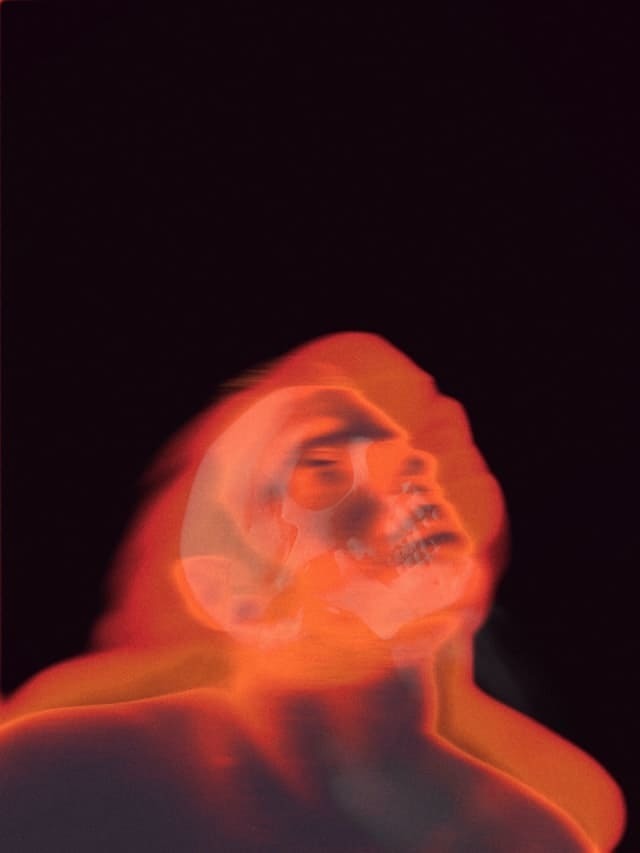
前頭側頭型認知症の原因は、前頭葉や側頭葉が萎縮することです。前頭葉や側頭葉の萎縮は、脳に異常なたんぱく質がたまることによって起こります。
前頭側頭型認知症では、脳にタウ蛋白、TDP-43、FUSと呼ばれるたんぱく質の性質が変わったものがたまることで前頭葉や側頭葉が萎縮すると言われています。
日本では、遺伝が原因で前頭側頭型認知症を発症している例はほとんどありません。欧米では3~5割ほどは遺伝が関係して発症している例があると言われています。
主な原因
1. タウタンパク質の異常
前頭側頭型認知症では、タウタンパク質が異常に蓄積し、神経原線維変化を引き起こします。タウの凝集が神経細胞内で塊を形成し、神経細胞の死滅を促します。
2. TDP-43タンパク質の異常
TDP-43が神経細胞内で異常に蓄積し、神経細胞の機能を阻害します。特に、行動変化型FTDや筋萎縮性側索硬化症に関連することが多いです。
3. 遺伝的要因
前頭側頭型認知症の30~50%は遺伝的要因に関連しています。MAPT遺伝子とGRN遺伝子、C9orf72遺伝子の異常が発症に関係しているとされています。
4. 神経炎症
炎症性サイトカインの放出が神経細胞の損傷を加速します。タウやTDP-43の蓄積と関連して炎症が悪化するという悪循環を引き起こします。
5. 細胞間シグナルの異常
シナプスの異常が情報伝達の効率を低下させます。神経細胞を支えるグリア細胞の機能不全が、神経変性を加速させます。
6. 環境的および生活習慣的要因
脳外傷、慢性ストレス高血圧、糖尿病、肥満などの生活習慣病が発症に関係しているとされています。
7. 年齢と性別の影響
50~60歳代での発症が最も多く、若年性認知症の原因として注目されています。行動型の場合は男性に多く、言語型の場合は女性に多い傾向があります。
8. 他の神経変性の病気との関連
筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病のような症状が現れることもあります。

前頭側頭型認知症の症状は、社会性が失われることや性格が変わることです。周りの目を気にせず自分勝手な行動がみられるようになるのです。認知症の症状として多い、もの忘れなどの認知機能障害は目立って現れません。
毎日同じ道を散歩したり同じ時間に同じ行動をしたりするという症状もあります。他にも、過食や食行動の変化、自発性の低下、他人への共感や感情移入が難しくなるなどの症状も見られます。
前頭側頭型認知症では、思考や理性、社会性などに関わる前頭葉と知識や記憶、感情などを司る側頭葉に障害が起きるため、他の認知症とは違った様々な症状が現れるのです。
主な症状
1. 行動変化型FTD
前頭葉が主に萎縮する場合、以下の行動や人格の変化が現れます。
① 人格の変化
無関心(アパシー):以前楽しんでいた活動への興味を失い、無気力になる。社会的関心や仕事への意欲が低下。
衝動性:突発的で計画性のない行動をとるようになる。
社会的規範の欠如:場の空気を読めず、不適切なジョークやコメントを言う。公共の場でのマナーが守れなくなる。
② 感情制御の障害
感情の平坦化:喜怒哀楽が乏しくなり、感情をほとんど表さない。
共感の喪失:他人の感情や状況を理解できなくなる。家族や友人への思いやりが減少。
③ 強迫的・常同行動
反復行動:同じ動作や言葉を繰り返す。
儀式的行動:不必要なルーチンを頑なに守る。
過剰な収集癖:不要な物を溜め込む。
④ 食行動の変化
食欲の変化:特定の食品への執着(甘い物、脂っこい物など)。
暴食:食べ物に対する抑制が効かなくなり、一度に大量に食べる。
2. 言語変化型FTD
側頭葉が主に萎縮する場合、言語機能が中心的に障害されます。
① 非流暢性変異型PPA
言葉を発する能力が低下します。
発語のぎこちなさ: 話すペースが遅くなり、言葉が出にくい。
文法エラー: 単純な文章でも構成が難しくなる。
発音の困難: 正確に発音できなくなる。
② 意味変異型PPA(svPPA)
言葉の意味理解が損なわれます。
単語の意味を忘れる: 例えば、普通の物の名前を理解できなくなる。
抽象的な概念の喪失: 会話の文脈が理解できなくなる。
③ ロゴペニック変異型PPA(lvPPA)
記憶力と言語の流暢性の低下が混在します。
言葉の検索が遅い: 言いたい言葉を思い出すのに時間がかかる。
会話の途中で言葉に詰まる。
3. 運動関連症状
一部では、運動機能にも影響が及びます。これは、筋萎縮性側索硬化症との関連が深い場合に見られます。
① 筋力低下
手足や体幹の筋力が低下し、歩行や日常動作が難しくなる。
② 振戦
手足の震えや筋肉のけいれん。
③ パーキンソン症状
動作が遅くなる。
筋肉の硬直。
4. 認知機能障害
行動や言語の変化に加え、次第に認知機能全般が低下します。
① 記憶力の低下
短期記憶や新しい情報の記憶が難しくなる。
② 判断力の低下
日常の意思決定が困難になる。
③ 注意力の低下
一度に複数のことをこなす能力が低下する。
5. 感覚や知覚の異常
聴覚の変化:音に対する過敏反応や鈍感さ。
視覚の変化:見慣れた物や人を認識できない。

前頭側頭型認知症の根本的な改善方法は今のところありません。症状の進むスピードを遅くする方法もありません。
そのため、基本的には生活環境の調整などを行います。しかし、症状によって行動があまりにも常識と離れていたり、暴力があまりにもひどかったりする場合は入院が必要になることもあります。
主な改善方法
1. 薬
FTDでは、行動や感情のコントロールが難しくなるため、これらを緩和する薬が用いられることがあります。
抗精神病薬:リスペリドンやクエチアピンなど。攻撃性や幻覚、妄想がある場合に使用されます。
※副作用として筋肉の硬直や転倒リスクがあるため、慎重に使用します。
抗うつ薬:SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)(例: セルトラリン、フルオキセチン)。抑うつや不安、強迫的な行動の軽減に効果が期待されます。
気分安定薬:バルプロ酸など。感情の急激な変化や衝動的な行動を抑えるために使用されます。
2. 行動
問題行動を減らし、社会的なやりとりを改善するためにトリガーとなる環境や状況を特定し、それを避けるか、環境を調整します。
3.言語療法
言語機能の維持とコミュニケーションの改善するために言葉の検索や発音を助ける練習をします。
4.作業療法
日常生活の自立を維持し、QOLを向上するために日常生活動作の訓練を行います。
5.リラクゼーション法
ストレスの軽減と落ち着きを促進するために音楽、アロマセラピー、軽いマッサージなどを取り入れます。
栄養と食事管理、環境の管理について
病気の進行に伴い、嚥下障害や食行動の変化が見られることがあります。そのため、以下の管理が重要です。
食行動の改善:暴食や特定の食品への執着を和らげるために、食事の量やタイミングを管理します。
嚥下障害への対応:嚥下訓練を行い、食事形態を柔らかい食品やゼリー状に変更し誤嚥性肺炎の予防に努めます。
栄養補助食品の活用:栄養不足を防ぐため、必要に応じて栄養補助食品を導入します。
また、安心して生活できる環境を整えることも重要になります。
住環境の整備:転倒防止のための手すりを設置、鍵付きの戸棚で危険物を管理します。また、過度に刺激されないよう、静かで穏やかな環境を作りましょう。

初めの段階では、毎日同じ時間に同じ行動をするというこだわりが現れたり、欲求を抑えることができず本能のまま行動したりするようになります。
痴漢行為や万引きなど社会的に問題となる行動を行うこともありますが、本人は悪いことをしているという自覚がありません。
病気が進むと、意欲や活動性が明らかに下がっていき、非常識な行動や暴力などはだんだんと目立たなくなります。さらに病気が進むと、感情がなくなり話すこともしなくなります。
1日何もせずに横になったまま過ごすようになり、寝たきりになってしまいます。




